- m3.com 電子書籍
- 小児の頭蓋健診・治療ハンドブック~赤ちゃんの頭のかたちの診かた
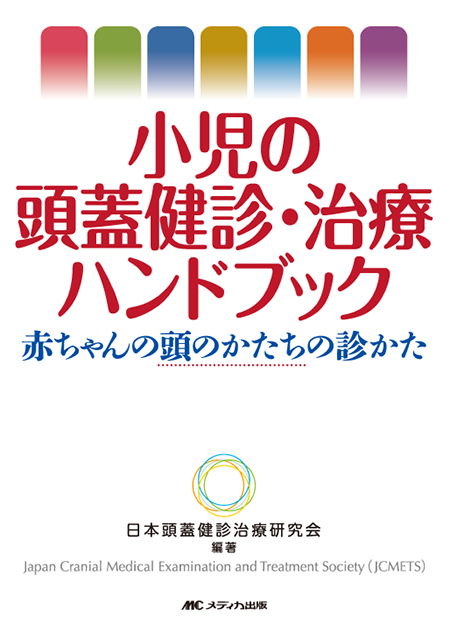
小児の頭蓋健診・治療ハンドブック~赤ちゃんの頭のかたちの診かた
日本頭蓋健診治療研究会 (編著) / メディカ出版
- ページ数 : 168頁
- 書籍発行日 : 2022年4月
- 電子版発売日 : 2022年6月22日
商品情報
内容
乳幼児の頭蓋変形への関心が高まり、一部の医療機関では矯正ヘルメットによる治療法が導入されているが、健診や外来での対応は必ずしも定まっていない。本書は、子どもの成長・発達上重要な意味をもつ頭のかたちとその診断・治療について言及した国内初の専門書。健診時のスクリーニング、病的な頭蓋変形と向きぐせを誘因とする位置的頭蓋変形の鑑別、ヘルメット矯正治療の適応と効果について解説するとともに、家族の疑問・不安にもQ&Aで答えている。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序にかえて
医療・医学は、先人の汗と努力の結晶で到達したエビデンスを基盤に、長い時間をかけて熟成し構築されてきた歴史がある。そして、それが「当たり前(常識)」となって後世に伝承されていく。伝達役となる現世の医療に携わるわれわれには、そのエビデンスをただ右から左へと移行させるのではなく、自らの手の中で転がし、触り、さまざまな角度から見つめ直して検証する「勇気」が必要ではないだろうか。
新生児・乳児の頭の形と大きさの診断は、その後の児の成長・発達にとって非常に重要な意味をもつ。しかしながら、わが国では、原疾患の有無を問わず頭蓋変形の診断について明確にまとめられた基準値が存在しない。病的頭蓋変形症から向きぐせを誘因とする位置的頭蓋変形症の診断に至るまで、乳幼児健診をはじめとした小児医療現場では診断、そして早期治療の正しい選択をめぐって、混沌としているのが現状である。
受け継いだ「当たり前(常識)」は本当に「当たり前」なのか、「当たり前でないこと(未常識)」を見落としてはいないか、後世に伝承すべき新たな提言はないのか。そのような観点から、われわれは2020年、「日本頭蓋健診治療研究会(Japan Cranial Medical Examination and Treatment Society:JCMETS)」を創設し、未来を担う子どもたちの健康を「頭蓋健診」という学術的見地から議論する場として活動を始めた(研究会の詳細については後述する)。
位置的頭蓋変形症は、乳児において出生前後に生じる頭蓋の多平面変形である。
これは、他の多くの「非閉鎖頭蓋縫合」頭部変形に関する記述および報告の実態と同様に、もし未治療のまま放置された場合には、重大な機能的、神経学的、美容的、および心理学的な影響をもたらす可能性がある。たとえば、眼窩内の筋肉や神経などにかかる圧力は、感覚障害や運動障害を引き起こす1)。その結果、頭蓋変形のある乳児は、空間における頭部の向きの異常をまかなうべく、眼や前庭の機能障害を引き起こす可能性がある2)。また、頭蓋骨の成長の85%が生後1年以内に完了することを考えると3)、この短期間での早期発見と治療が何よりも重要であると言える4)。
本書では、頭蓋変形の概念、一般の乳幼児健診の場でのスクリーニング方法、専門の医療機関における診断、治療の導入方法について、ハンドブックとしてわかりやすく記載した。さらに、頭蓋変形に関する家族からの質問に答えるQ&A集、一読すべき関連論文についても紹介した。本書を通じて、「頭蓋変形」という病態について、「伝承」をよりよき医学的「伝統」へと昇華できることを切に願うものである。
2022年4月
日本頭蓋健診治療研究会
【参考文献】
1) Rekate HL. Occipital plagiocephaly:A critical review of the literature. J Neurosurg. 89(1), 1998, 24-30.
2) Argenta LC, David LR, Wilson JA, et al. An increase in infant cranial deformity with sleeping position. J Craniofac Surg. 7(1), 1996, 5-11.
3) Aihara Y, Komatsu K, Dairoku H, et al. Cranial molding helmet therapy and establishment of practical criteria for management in Asian infant positional head deformity. Childs Nerv Syst. 30(9), 2014, 1499-509.
4) Graham JM Jr., Charman CE, Chaisson R, et al. Postnatal head deformation:anthropological observations and applications to the treatment of postnatal plagiocephaly. Proceedings of the Greenwood Genetic Center 7, 1988, 156-59.
目次
序にかえて
日本頭蓋健診治療研究会について
【第1章】頭蓋変形の概要
1 定義・頻度
2 タイプと機序
3 発達への影響
①システマティックレビューによる報告
②早産児に関する報告
【第2章】乳幼児健診時および一般医療機関での頭蓋変形への対応
1 頭蓋変形の進行および診察法
①母体内胎児期
②出生後の入院中
③1か月児健診までの新生児期
④1か月児健診
⑤1か月児健診から3~4か月児健診の間
⑥3~4か月児健診
⑦3~4か月児健診以降
2 頭蓋変形への介入および専門医療機関への紹介
①寝かせる位置・向きの工夫
②タミータイムの導入
③生活上の工夫
④ヘルメット矯正治療の適応判断
【第3章】専門医療機関での頭蓋変形への対応
1 頭蓋変形診断のための基本事項
①頭蓋変形の指標
②頭蓋変形とSIDS
③頭蓋縫合早期癒合症
④位置的斜頭
2 位置的斜頭の理解
①「位置的」という表現がもたらす誤解
②さまざまな変形
③頭蓋変形に対する矯正治療とその文献的考察
④発育の重要段階と位置的斜頭
⑤斜頸と位置的斜頭
3 鑑別診断
①水頭症
②頭蓋縫合早期癒合症
③鑑別診断後の確定診断
4 頭蓋変形の全身への影響
①まず「ずれ」を理解する
②「ずれ」から二次的に生じる合併症
5 頭蓋変形における乳幼児健診の重要性
①1か月児健診の重要性
②至適矯正治療開始月齢に関する情報提供
6 頭蓋変形における問診と診察のポイント
①遺伝的/環境的 両面からの情報収集
②両親の悩みを傾聴する
③問診項目と診断・分類
④診察の実際
7 頭蓋変形測定に基づく診断
①頭蓋変形率(CA)の算出方法
②アプリを用いたスクリーニング
8 矯正効果期待値
①治療効果に関する質問にどう答えるか?
②大泉門の開存率が重要指標
9 専門医療機関からのフィードバック
①早期の治療介入が必要な場合
②経過観察とする場合
③頭囲成長が少ない場合
④自然矯正が困難な場合
10 頭蓋矯正治療のメカニズムと矯正ヘルメットの内層構造
①「ずれ」を正しい位置にもどす
②皮膚トラブルを防ぐ低反発素材の導入
③変形パターンに合わせたオフセット位置の設定
11 矯正ヘルメット装着の実際
①治療期間と1日の装着時間
②発汗の増加、体幹温度の上昇への注意
③児が矯正ヘルメットを嫌がる場合の対応
12 病的疾患群に対するヘルメット矯正治療
①水頭症(脳室-腹腔シャントバルブ留置)
②頭蓋縫合早期癒合症
③未熟児網膜症
④CPAPマスク装着
⑤斜頸・股関節脱臼
13 ヘルメット矯正治療の課題と展望
①矯正メカニズムとその効果
②頭蓋変形に対する治療の真の目的とは何か?
③各専門分野の横断的な連携を
【第4章】頭蓋変形Q&A
1 頭の歪みに関する基本的な質問
2 受診の目安に関する質問
3 初めての受診にあたっての質問
4 ホームケア、その他の治療に関する質問
5 頭蓋変形が及ぼす影響に関する質問
6 ヘルメット矯正治療に関する質問
・治療の適応・開始のタイミングについて
・治療のノウハウについて
・治療への疑問・不安・心配事について
・治療による効果について
・治療にかかる費用について
・治療中の注意点について
・矯正ヘルメットのメンテナンスについて
【第5章】一読すべき論文
【第6章】用語集
資料編
・治療用装具の療養費に関する説明
・日本頭蓋健診治療研究会活動の記録
索引
執筆分担
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:12.1MB以上(インストール時:26.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:48.2MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:12.1MB以上(インストール時:26.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:48.2MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784840478694
- ページ数:168頁
- 書籍発行日:2022年4月
- 電子版発売日:2022年6月22日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。


