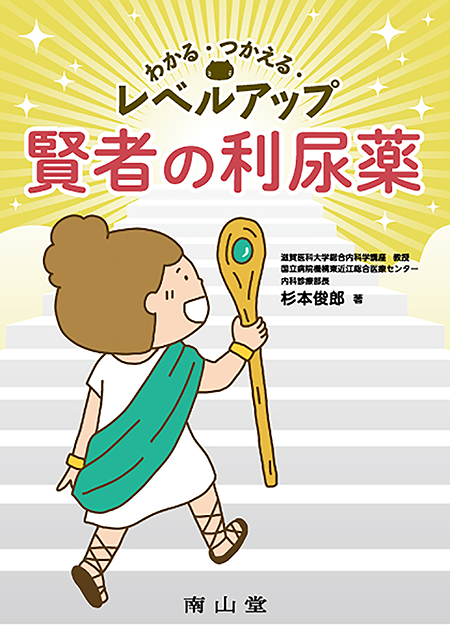- m3.com 電子書籍
- 南山堂
- わかる・つかえる・レベルアップ 賢者の利尿薬
商品情報
内容
本書は著者の「利尿薬を適正に使用すれば,心不全・腎不全の入退院を防ぐことができるはず」という提言を基に刊行されました.薬物動態や薬力学の基本,著者の10年以上における総合内科医としての経験と最新のエビデンスを取り入れ,利尿薬の使い方の実際が理解できる構成となっています.さらに,水・電解質と酸塩基平衡にやたらと詳しい猫「きどにゃん」も友情出演するなど,理解が深まりながらも面白く読み進められます.
心不全や腎不全,肝硬変を普段から診療している方,さらに在宅や外来での使用方法もあるので地域医療に従事している方にもオススメな一冊となっています.
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
推薦の言葉
利尿薬を切り口とした最新の心不全診療の指南書である
自分が医師になって30年以上の時間が経ちました.初めての当直の夜に搬入された急性心不全患者に上級医とともに対応したことを今でも明確に覚えています.ライン確保の後に「ラシックス® 1 A」を静注すると,尿道バルーンのチューブに透明感の高いループ利尿薬への反応尿が充満するとともに,患者さんの自覚症状は目に見えて改善したのです.「ラシックス®」の凄さが脳裏に焼き付いた瞬間でもありました.
その後に,利尿薬は大きく進化しました.トルバプタンやSGLT 2阻害薬に代表される新規薬剤が臨床現場に導入されました.利尿薬がもっとも必要とされる心不全の治療戦略にも大きな変革がおきています.本書は,利尿薬の使い方の教科書を装いながら,実は心不全診療の指南書です.心不全という病態と治療を,利尿薬という薬剤を通じて解説した珠玉の名著といえます.若手医師の中には,新規の利尿薬に目を奪われ,以前からあるループ利尿薬やサイアザイド系利尿薬の価値を否定的に捉えるものもいます.本書では,新規薬剤を活かすためにも,病態生理に基づいて従来の利尿薬も含めて,使用法をわかりやすく解説しています.日本はもとより,ヨーロッパや米国においても心不全治療のガイドラインは次々とアップデートされています.本書では2022年4月の米国でのガイドライン改訂までを網羅しており,まさに最新の情報を満載した書籍といえます.
医学書には,1人がすべてを書き上げた単著のものと,多くの執筆者が分野別に執筆し編集されたものがあります.単著の書籍は,全編を通じて背後に潜む執筆者のフィロソフィーを感じ取ることができることが魅力です.本書から著者である杉本俊郎先生の,心不全診療に打ち込む姿勢と,若手医師を育成しようという熱い血潮が伝わってきます.さらに「Column: コラム」と題して,短文ながら深堀りされた情報が書籍内にちりばめられています.非常に読み応えがあり,ウンチクと博識を感じながら杉本ワールドへと読者を導く仕掛けです.ちなみに自分にとって,一番のお気に入りのコラムは「むくみをとるのは,医師の処方の基本である」という一節です(p. 13).まさに「賢者の利尿薬」という言葉がピッタリの内容です.
著者の杉本先生は,東近江総合医療センターで内科診療部長として臨床の現場を指揮するとともに滋賀医科大学の総合内科学講座の教授として学生教育にも尽力するという,八面六臂の活躍をなされている医師です.近江は淡海とも記載することもあり,「おうみ」は「淡水のうみ」つまり琵琶湖を意味します.ポイントは,琵琶湖は塩分を含まない淡水で構成されていることです.人間をはじめとする陸上動物の祖先は,海から陸にあがってきた時,レニン・アンジオテンシン系という体内を海水と同じような環境に保つようなシステムを身につけました.これが,体内のナトリウム(Na)含量と水分量を調整し,血圧調節や心不全の発症にも関与しています.塩分と水分の関係について深く考察する本書が,近江の地から上梓されたのは偶然ではなく必然ではないかとも感じます.
本書は,心不全についての知識を総合的に習得したい若手の医師にもっとも相応しいものです.初学者ばかりではなく,すでに心不全の治療経験のある者にも有益です.最新の情報を入手し新規薬剤の使用法についても具体的に学ぶことが可能だからです.さらには医学部附属病院などの医育機関に勤務する者には,利尿薬の使い方や心不全についての講義を学生に行う際のポイントとウンチクが満載されている本書は役に立つこと間違いありません.このように素晴らしい書籍を書き上げてくれた,杉本先生に感謝と敬意をささげます.
2022年5月
滋賀医科大学循環器内科
中川義久
序
本書は,患者さんの適切な体液量を維持するために有用とされる手段の一つである「利尿薬の適正な使い方」について解説したものです.うっ血性心不全などの体液過剰をきたす疾患に対して,尿量の増加(diuretics)から,症状の改善をはかることは,現在使用されている利尿薬が開発される前から行われてきた方法といわれています.しかし,私は過去10年間,地域の中核病院において,総合内科医として勤務していますが,うっ血性心不全,慢性腎臓病,肝硬変などの疾患による体液過剰(うっ血症状・浮腫)の増悪により,入退院を繰り返す高齢者を多数経験してきました.この地域医療における大きな問題の一つは,「利尿薬を適正に使用する」ことで,解決できるのではないかと私は考えるようになりました.
私の考えに賛同いただいた南山堂雑誌「治療」編集部のご好意により,2019年7月〜2020年6月の計12回にかけて,雑誌「治療」と「薬局」に,「超高齢社会シコウ(志向)の利尿薬適正使用シコウ(思考)」という提言を連載いたしました.本書は,この連載に基づき,私の「利尿薬の適正な使い方」に関する考えをさらにまとめたものです.
利尿薬は,投与された後に腎臓に到達し,腎尿細管に作用して,利尿(diuretics)効果を発揮します.よって,利尿薬を適切に使用するためには,利尿薬が腎臓へ到達するまでの問題であるpharmacokinetics(PK)と,そして,利尿薬が作用を発揮するための腎臓における反応性の問題であるpharmacodynamics(PD)を理解する必要があると思います.「利尿薬の適正な使用」に関する,PK, PDに関する問題点を,主に,腎生理の観点から解説したことが,本書の特徴の一つであると考えています.よって,私の友人である,「きどにゃん」にも,再度登場してもらいました.腎生理の観点からみると,本書は「きどにゃん」シリーズのスピンオフに相当するものと私は考えています.
さらに利尿薬は,患者さんにとって非常に不快な症状である,呼吸困難・浮腫(むくみ)などの体液過剰・うっ血の症状を改善させるためには欠かせない薬剤であります.よって,利尿薬を適正に使用することは,人口の高齢化が進行する地域医療の現場(例:進行したうっ血性心不全・慢性腎臓病例に対するうっ血改善による緩和ケアなど)において,欠かすことのできない方略の一つであると私は考えています.本書を手にとっていただいた読者の皆様が,「利尿薬の適正な使用」について再考する機会になれば望外の喜びです.
最後に,筆者に本書を執筆する機会を与えてくださり,連載の時から,企画・編集に多大なご尽力を賜りました南山堂の古賀倫太郎氏,小池亜美氏,小林薫子氏,推薦のお言葉を賜った滋賀医科大学循環器内科教授 中川義久先生,本書の最初の読者であり,適切なコメントをいただいた東近江総合医療センター後期研修医 山田安希,中島興,両先生に,心から感謝の意を表します.
2022年4月
滋賀医科大学総合内科学講座 教授
東近江総合医療センター 内科診療部長
杉本俊郎
目次
問題提起編
1 なぜ今,利尿薬の使い方なのか?
2 現状の利尿薬の使い方の問題点 ~なぜ適切に利尿薬を使用できないのか?~
基礎編
1 利尿薬を使うために必要な知識 ~体液過剰・うっ血・浮腫の病態生理~
2 利尿薬を使うために必要な知識 ~各種利尿薬の薬理学的特性~
3 利尿薬を使うために必要な知識 ~利尿薬と腎生理~
臨床基本編
1 うっ血性心不全における利尿薬の使い方
2 体液過剰状態のネフローゼ・慢性腎臓病に対する利尿薬治療
3 肝硬変(腹水貯留例)
4 急性期医療・集中治療と利尿薬
5 降圧薬としての利尿薬
臨床実践編
1 ADHF─利尿薬の初期投与
2 ADHF─利尿薬の効果判定
3 ADHF─電解質異常への対応
4 ADHF─腎機能障害への対応
5 ADHF─利尿薬の効果の減弱
6 ADHF―入院から外来診療への移行
7 慢性うっ血性心不全─慢性期・外来における利尿薬の使い方
8 慢性うっ血性心不全─外来・在宅療養症例などにおける利尿薬の使い方
9 慢性うっ血性心不全─外来診療における,新しい利尿薬の使い方
10 高齢者のうっ血性心不全・腎硬化症─外来での心腎症候群
11 高血圧─難治性高血圧の一例
12 肝硬変─腹水貯留例
13 体液過剰状態の慢性腎臓病に対する利尿薬治療
症例編
1 急性うっ血性心不全の一例
2 進行した腎機能障害を呈している高齢糖尿病性腎臓病の一例
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:11.3MB以上(インストール時:28.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:45.1MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:11.3MB以上(インストール時:28.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:45.1MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784525412319
- ページ数:255頁
- 書籍発行日:2022年7月
- 電子版発売日:2022年6月24日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。