- m3.com 電子書籍
- 金原出版
- 産婦人科の実際 2019年6月臨時増刊号 68巻7号 産婦人科診療decision makingのためのMRI・CT【電子版】
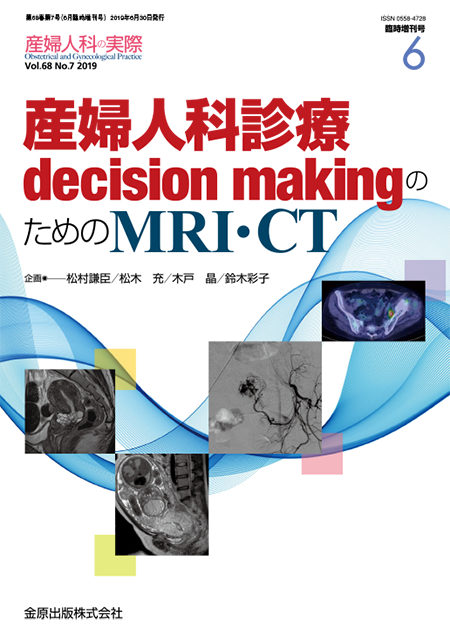
産婦人科の実際 2019年6月臨時増刊号 68巻7号 産婦人科診療decision makingのためのMRI・CT【電子版】
/ 金原出版
- ページ数 : 313頁
- 書籍発行日 : 2019年6月
- 電子版発売日 : 2019年10月30日
商品情報
内容
※p.776~781,p.882~886の図は使用許諾の関係で収載していません。
序文
患者本位の産婦人科診療のために画像を読み解く
MRI、CT、PET-CTなどの画像診断の進歩によって、様々な疾患・病態を治療前に詳細に評価できるようになってきた。しかし、産婦人科医である読者諸氏は、画像診断に求めることと放射線診断医からの読影レポートに解離を感じたこともあるのではないだろうか。一方、産婦人科医によるオーダー方法に対する放射線診断医からの不満もしばしば伝え聞く。
日本は人口あたりの病院数、CTやMRIの設置台数、人口あたりの撮影頻度が世界でも最も多いが、CTやMRI1台あたりの稼働率は悪く、各施設が収益を上げようとしているためか撮影頻度はさらに増加しつつある。一方、人口あたりの医師数は少なく、それは放射線科も例外ではない。その結果、常勤の放射線科医がいない施設が多く、撮影されたCTやMR画像のうち、放射線専門医による読影が行われないものも多い。また、放射線診断医には得意とする専門領域があり、必ずしも産婦人科疾患の病態や画像所見に精通しているとは限らない。日本の医療制度では、正確な画像診断よりは稼働率が病院の収益に直結するため、患者が置き去りになってしまうリスクがある。
このような状況において、画像診断を通じて患者本位の医療を行うためには、放射線画像をオーダーする診療科医師の努力が必要である。すなわち、産婦人科医がよい産婦人科医療を行うためには、MRI、CT、PET-CTそれぞれの利点、欠点、限界について熟知し、適切なタイミングで最適な検査をオーダーする必要がある。そして、読影レポートを鵜呑みにするのではなく、画像の読み方について理解し、自らの目で画像を見て診療を行う習慣を身につけることが重要である。
これまでに、産婦人科領域の画像診断に関する書籍は多数出版されてきた。しかし、産婦人科医として知りたい画像診断の基本的な事項や、診療方針決定のためにクリティカルな局面での画像診断、そして画像診断の限界についての記載は必ずしも十分ではなかった。
今回は、産婦人科医自身が画像を見て日常診療でdecision makingを行うことを想定し、そのような局面でただちに役立つ内容となることを目指した。そして、産婦人科領域における画像診断のエキスパートの先生方に執筆をお願いして、産婦人科医でもわかるように平易に記載していただいた。
放射線診断医が常勤している施設では、産婦人科医と放射線診断医がカンファレンスを行いディスカッションを重ねることで、画像診断のクオリティは飛躍的に高まるであろう。本特集が、読者諸氏の施設における産婦人科医と放射線診断医のディスカッションを促し、産婦人科画像診断の質を向上させ、日常診療に役立てば幸甚である。
近畿大学医学部産科婦人科学教室
松村 謙臣
「一緒にカンファレンスしませんか」
私が画像診断医を目指した頃はMR診断の指導者は少なかったが、それでも早くから興味を持ったのが婦人科領域のMR診断である。なぜ興味をもったのか? それは何よりも富樫かおり先生(京都大学医学部附属病院放射線診断科 現・教授)が執筆された「婦人科疾患のMRI診断(医学書院、1990年)」にある。この本を通して、婦人科領域の正常解剖から多くの疾患のMR所見を学び、私だけでなく、現在の婦人科領域の画像診断医の礎になったといっても過言ではない。その後、私はサブスペシャルティの道を選ばず、general radiologistという道を選んだが、現在も婦人科領域のMR診断はライフワークのひとつである。
そうこうしているうちに昨年の夏、放射線科医、産婦人科医、病理医が合同で開催する第19回JSAWI(Japanese Society for the Advancement of Women's Imaging)にて、京都大学医学部放射線診断科の木戸晶先生、近畿大学医学部産婦人科の鈴木彩子先生から松村謙臣教授が企画された今回の特集の編集に加わっていただけないかというお話をいただいた。もちろんこの"豪女*"に挟まれて、NOという返事はなかったが、それよりも富樫先生のもとで学び、診断や診療に携わってこられた先生方からのお誘いで、少しでも恩返しできればとの気持ちで承諾した。
その後、すぐに松村先生の企画書が届き、"産婦人科医にとって日常臨床で必要な画像診断"について詳しく、細部まで記載されており、この執筆に協力できることの喜びを感じた。その後、これをきっかけに産婦人科医、病理医とカンファレンスを行うようになった。カンファレンスを始めて早々に印象に残ったものに、松村先生が何気なしに発したひと言がある。そのひと言とは、「腫瘍色」である。この特集で神戸大学の神田知紀先生も触れられているが、放射線科コミュニティ内で使われている言葉で、さかのぼれば京都大学放射線診断科医が流行らせた言葉である。そのひと言で婦人科領域の画像診断にかかわる縁や共通認識を感じ、現在、カンファレンスを通じ、昔の「婦人科疾患のMRI診断」を読み始めた頃の高揚感を感じている。
今回は、木戸先生とともに多くの婦人科画像診断のエキスパートの先生がたに執筆をお願いした。すべての原稿に目を通したが、どの原稿も松村先生が企画した日常臨床に即した素晴らしい内容で心より感謝申し上げる。私からのメッセージとして、この特集を通して、知識を増やすとともに、一人でも多くの産婦人科医、放射線科医が「一緒にカンファレンスしませんか」といえることが最高の産婦人科診療への一歩になりうるものと確信する。
*豪女とは、そんじょそこらの男に負けない豪腕、豪快さを持ち合わせた女性のこと。
近畿大学医学部放射線医学教室放射線診断学部門
松木 充
目次
産婦人科診療 decision makingのためのMRI・CT
I.総論
1)放射線診断専門医による画像診断
2)単純MRI、造影MRI
3)単純CT、造影CT
4)PET/CT
5)妊婦におけるMRI、CT検査のリスクと有用性
6)水、血液、石灰化、脂肪、粘液、癌組織の画像上の特徴
II.卵巣の良性疾患および悪性腫瘍との鑑別診断
1)充実部と嚢胞部が混在する卵巣腫瘍の鑑別診断
a.上皮性卵巣癌の画像診断
b.卵巣漿液性腺線維腫の画像診断
c.卵巣境界悪性腫瘍の画像診断
d.Polypoid endometriosis(ポリープ状子宮内膜症)の画像診断
e.顆粒膜細胞腫の画像診断
f.卵巣甲状腺腫の画像診断
2)卵巣チョコレート嚢胞と出血性機能性嚢胞の鑑別診断
3)子宮内膜症の部位
4)卵巣腫瘍茎捻転の画像診断
5)成熟奇形腫・未熟奇形腫の鑑別診断
6)成熟奇形腫悪性転化の鑑別診断
7)骨盤内充実性腫瘤の由来臓器に関する画像診断
8)放線菌症の画像診断
III.子宮の良性疾患および悪性腫瘍との鑑別診断
1)子宮内膜の生理的な変化と内膜ポリープなどの腫瘤性病変との鑑別診断
2)子宮奇形の画像診断と治療方針
3)子宮筋腫と子宮腺筋症の鑑別診断
4)子宮内膜ポリープ、子宮内膜増殖症と子宮内膜癌の鑑別診断
5)子宮筋腫と子宮肉腫(平滑筋肉腫、内膜間質肉腫)の鑑別診断
6)子宮頸部嚢胞性病変の鑑別診断-ナボット?胞、トンネルクラスター、LEGH、MDA-
IV.悪性腫瘍の診療方針決定のための画像診断
1)子宮頸癌(扁平上皮癌)および頸部腺癌の局所進展の画像診断
2)子宮内膜癌の局所進展の画像診断
3)癌肉腫と通常の内膜癌の鑑別診断
4)リンパ節転移の画像診断
5)腹膜播種の画像診断
6)子宮頸癌放射線治療後の残存病変の画像診断
V.子宮・付属器以外の疾患
1)腹膜封入嚢胞(peritoneal inclusion cyst)の画像診断
2)術後合併症の画像診断
3)放射線治療後の不全骨折の画像診断
VI.胎盤・妊娠関連
1)異所性妊娠の画像診断
2)癒着胎盤の画像診断
3)胎盤ポリープ(RPOC)の画像診断
4)分娩後の大量出血に関する画像診断
5)胎児MRI(MR fetography)
a.甲状腺腫
b.先天性横隔膜ヘルニア
6)内膜症性嚢胞の脱落膜化の画像診断
7)Hyperreactio luteinalis(黄体化過剰反応)の画像診断
8)子宮筋腫赤色変性の画像診断
9)胎盤血管腫の画像診断
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:118.7MB以上(インストール時:242.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:474.8MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:90.8MB以上(インストール時:187.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:363.2MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。


