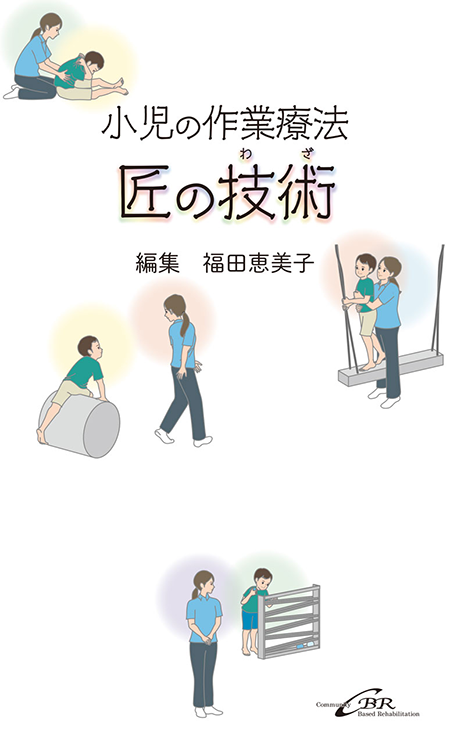- m3.com 電子書籍
- シービーアール
- 小児の作業療法 匠の技術
商品情報
内容
「匠」とは、「何らかの優れた技術を持つ人」と言われているが、作業療法の場合は「何らかの気づき」、「気づきのタイミング」を対象児・者と保護者に使いこなせる人が匠と言えるだろう。作業療法とは何かをしなくても、生理学(大脳と運動)や生態学・人間発達学を熟知していれば、疾病に照らし合わせて判断でき、その気づきがタイミングの良さとなり、対象児・者が自ら作業療法士の意図したことをしてくれるのではないだろうか?
本書は、長年、臨床現場で試行錯誤しながら、技術のみでなくアイデンティティや根源を見い出して小児作業療法の哲学に触れている「匠」たちならではの、具体的な場面において一歩踏み込んだ「観察」、「把握」、「察知してからのかかわるタイミングの良さ」に触れることで「作業療法の匠」の考え方を知ることができる1冊となっている。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序文
2022(令和4)年4月の日本作業療法士協会誌(JAOT)によると,2021年度の養成校数は205校(209課程)で,入学定員は7,820名です.有資格者数は104,277名で,10万人を超えました.
医療の臨床現場や教育・福祉の療育現場には,夢と希望を抱いた新卒の作業療法士が就職し,先輩の行動を模倣しながら経験を積んでセラピーの実感を体験しているのではないでしょうか〔本文の表記を作業療法士(以下,OTR)といたしました〕.
作業療法においても,医療現場のみならず教育・福祉の現場からのニーズが高まっている昨今,他職種と連携・協働して仕事をしている現状にあります.
教科書や臨床実習を通して学んでいた学生時代は,単位取得,国家試験合格を目標にして,どちらかというとやらされて取り組んでいると感じていたのが本音ではないでしょうか? 教科書で学んだことは,基本となる概念であり,観念を磨き上げるきっかけを作っていると思います.概念は,作業療法の本質を問うもので,包括的な意味内容を把握し,観念として,内的・個人的に認識され,作業療法についての認識を深め,作業療法に対するイメージを豊富にすることにつながっているのではないでしょうか.
「小児の作業療法 匠の技術(わざ)」の書籍に取り組んだきっかけは,長年作業療法の仕事を外部から見ていて背中を押してくれている方が,「作業療法は対象児・者と会話をしたり,必要になる作業を提供したりして,楽しそうにかかわりながら効果を出しているのに,外見的には,ただ話をしているとか,遊んでいるとか,作業をしているだけにしか見えないからわかりにくいよね.何か見えるようなものが提示されると,新人や素人にもわかるのかな~」と呟かれたことにあります.個人的にもこのようなご指摘にもがきながら,臨床や学生の養成にかかわっていました.しかし,「まあいいか! わかってくださる人がいれば!」とわが人生で処理していたのでは,作業療法の仕事は存続していかないと感じ,作業療法の匠の方々に登場いただいて書籍を作ることになった次第です.
「匠」とは「何らかの優れた技術を持つ人」と言われていますが,作業療法の場合は,「何らかの気づき」,「気づきのタイミング」を対象児・者と保護者に使いこなせる人が匠なのではないかと感じています.作業療法とは何かをしなくても,生理学(大脳と運動)や生態学・人間発達学を熟知していれば,疾病に照らし合わせて判断でき,その気づきがタイミングの良さとなり,対象児・者が自らOTRの意図したことをしてくれるのではないでしょうか? 自発的行動とか自主性,能動性が重要視されるようになっています.近年ではAI(人工知能)が発展していますが,AIでは不可能なことを,OTRが気づいて,きっかけ作りをしているのではないでしょうか? AIにも柔軟性があるようですが,個々人に合わせて必要なタイミングを察知してかかわる作業療法であることを意識して,効果を発揮できる作業療法であってほしいと願っています.執筆者の方々には,長年,作業療法を臨床現場で試行錯誤しながら,匠となる技術のみでなくアイデンティティや根源を見い出して小児作業療法の哲学に触れている方々です.一般的に言われている技術の提示ではなく,匠のOTRの脳内現象をのぞかせてほしいとお願いいたしました.
評価・治療・リスク管理など教科書で学んできていますが,具体的な場面において一歩踏み込んで,「匠」ならではの「観察」,「把握」,「気づきからのタイミングの良さ」に触れていただき,「自分であったらこのようにする!」というactive learningの気持ちが沸々と湧き出ることを,そしてそのときにこの書籍がお役に立ってくれることを願っています.
書籍の企画・編集・制作にあたり,株式会社シービーアールの永井友理様とそれを引き継いでくださっている大澤佳苗様には大変お世話になり感謝申し上げます.書籍の制作のみならず,作業療法の熟知者,よき理解者,応援者となってくださっていることにも,心から「ありがとうございます!」と申し上げます.
2022年10月
福田恵美子
目次
第1章 障害児・者支援における社会保障制度の理解
第2章 保健領域―肢体不自由/知的・情緒発達障害
Ⅰ 発達障害児への早期介入の必要性
Ⅱ 年齢別支援
Ⅲ 事例
第3章 医療領域―肢体不自由/知的・情緒発達障害
1.軽中度
2.重度
第4章 福祉領域―肢体不自由/知的・情緒発達障害
1.乳幼児期
2.学童期(放課後等デイサービス、保育所等訪問)
第5章 就労領域―肢体不自由/知的・情緒発達障害
Ⅰ 就労支援に関する施設と内容
Ⅱ 働くことの意義
Ⅲ 就労に必要な能力とは
Ⅳ 就労に向けたプログラムを作成するポイント
Ⅴ 就労支援の実際と課題
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:18.6MB以上(インストール時:43.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:74.2MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:18.6MB以上(インストール時:43.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:74.2MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784908083839
- ページ数:308頁
- 書籍発行日:2022年12月
- 電子版発売日:2023年2月3日
- 判:B6変型
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。