- m3.com 電子書籍
- 周産期初期診療アルゴリズム PC3ピーシーキューブ公式コースガイド
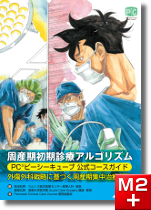
周産期初期診療アルゴリズム PC3ピーシーキューブ公式コースガイド
荻田 和秀 , 渡部 広明 (編) / Perinatal Critical Care Course運営協議会 (著) / メディカ出版
- ページ数 : 128頁
- 書籍発行日 : 2017年9月
- 電子版発売日 : 2018年7月27日
商品情報
内容
周産期医療に携わる医療スタッフであれば誰でも直面する可能性のある妊産婦の急変対応に必要なスキルをトレーニングするとともに、シナリオを通して母児の救命を目指した治療戦略を学習することを目的とするPerinatal Critical Care Course(PC3:ピーシーキューブ)のコースガイド。
序文
確実な母体救命の道標
今から10年ほど前,私が大阪府立泉州救命救急センター(当時)の所長に就任して2〜3年の頃だったと思う.30余年に及ぶ救命医人生の中でも,生涯忘れることのできない一症例を経験することになった.
救急隊からの通報では,30代女性,呼吸不全,高濃度酸素を投与しても酸素飽和度が80%台ということであった.搬入時,患者は起坐呼吸でチアノーゼ著明,冷や汗をかき意識は朦朧としていた.重篤な呼吸不全および循環不全状態と判断して,直ちに輸液路を確保するとともに気管挿管を行い,呼吸循環管理を開始した.初療で施行した胸部レントゲン写真で心拡大と肺門部の血管陰影の増強,いわゆるバタフライ像を認め,急性心不全状態と判断した.
同時に,腹部超音波検査を施行していた医師が「えっ!」と奇声を発した.「この患者さん妊娠してはります」.そのとき同伴していた患者の母親も妊娠の事実に気づいていなかった.近年問題となっている未受診妊婦で,だれも彼女の妊娠のことを知らなかったようであった.
彼女の呼吸循環不全は極めて重篤で,直ちに集中治療と集学的な治療が必要と判断し,救命救急センターの集中治療室(E-ICU)に入室となった.りんくう総合医療センター周産期センターのチームを招集して,今後の治療方針が検討された.すでに臨月間近で,胎児の心拍は保たれていた.周産期心筋症による重篤な心不全状態にあり,呼吸は100%酸素投与下にhigh-PEEPをかけてようやく最低限の酸素化を維持できる状態であった.もはや手術室への移動は困難と考え,救命救急センターの集中治療室で帝王切開を施行することになった.新生児科のスタッフも招集し,必要な器材を持ち込み,E-ICUで帝王切開術が施行され,胎児は無事に娩出された.
E-ICUでの娩出についてはさまざまな意見があろう.早期にPCPS(経皮的心肺補助装置)を導入していれば,より安全に手術室で帝王切開術を施行できたかもしれない.この治療方針の是非はともかくとして,私を驚かせたのは,その後の褥婦の経過である.産科の医師にとっては当たり前のことかもしれないが,手術室への移動すらはばかられる重篤な心肺機能不全に陥っていた妊婦が,胎児の娩出後は瞬く間に心機能が回復し,翌日にはE-ICUから産科の病棟に移動することが可能になった.この事実は,胎児の妊婦に与える影響の凄さを物語っており,重症合併症妊婦に対して確実な妊婦蘇生を施行しつつ迅速な胎児娩出を行うことが,妊産婦死亡の回避につながることをあらためて痛感させられた.
この一例からも明らかなように,最重症合併症を有する妊産婦の救命には,救命救急センターと周産期センターとの協働が必須である.われわれは2008年の泉州広域母子医療センターの立ち上げに伴い,りんくう総合医療センターの周産期センターと泉州救命救急センターとの協働体制を確立し現在に至っている.特に,2013年4月にりんくう総合医療センターと泉州救命救急センターが統合し,ひとつの医療機関になってからは,その連携は一層強固なものになった.
われわれはわが国における妊産婦死亡「ゼロ」を目指して,これまでの経験を基に周産期初期診療トレーニングコース「Perinatal Critical Care Course:PC3;ピーシーキューブ」を開発した.重篤な合併症を有する妊産婦に対する初期診療を学習するoff-the-job トレーニングコースであり,重篤な合併症を有する妊産婦の診療に携わる,また周産期救急にかかわる全国のすべてのスタッフにぜひとも受講を勧めたい.現在,本コースを全国展開中である.
本書はPC3の公式コースガイドであり,PC3で教える重篤な合併症を有する妊産婦に対する初期診療に加えて,妊産婦に対する集学的かつ根治的な治療戦略や新生児蘇生についても解説している.われわれの目標は「防ぎ得た周産期の死亡」の回避であり,そのためには妊産婦の生理学的徴候(ABCDE)の安定化が基本となる.生理学的異常の早期認知およびその安定化に着目した診療を行い,特に呼吸循環(ABC)の安定化に努めることが重要である.同時に,妊産婦の特殊性を勘案した産科的エッセンスを加えることにより,確実な妊産婦の救命が可能になる.このアプローチをPC3-PS(primary survey)と名称した.PC3-PSの実施により生理学的徴候が安定化してはじめてPC3-SS(secondary survey)に進み,詳細な産科的診断と治療とが可能になる.
ただし,日本における出産は必ずしも高度な救命処置や産科的治療が可能な医療機関で行われているとは限らないのが現実である.したがって,重篤な合併症を有する妊産婦の救命には,地域における周産期診療システムを構築し,高次医療機関への妊産婦搬送体制を確立することが重要である.「妊娠は病気ではない」と言われる.私もそう思う.しかしながら,いったん異常が生じると,妊産婦以外では想定できないような生体反応が引き起こされるのも事実である.本書が,日々不安を抱きながら周産期救急診療に従事されている方々の一助になれば幸甚である.
最後に,PC3の構築および本書の出版にあたり心血を注いでいただいた荻田先生と渡部先生,りんくう総合医療センター周産期センター,大阪大学産科学婦人科学教室およびその関連施設,大阪府泉州救命救急センターの全スタッフに敬意を表したい.本書の出版に多大なるご尽力をいただいた,株式会社メディカ出版の編集担当者の方々にも心から謝辞を申し上げる.
2017年7月
地方独立行政法人りんくう総合医療センター 副病院長・救急診療部長
松岡 哲也
目次
・確実な母体救命の道標
・「強い」周産期施設に
・PC3とは
・執筆者一覧
Part1 周産期救急の新しい流れ:外傷初期診療×周産期救急
ABCDEFアプローチ
コマンド&コントロールによるチームアプローチ
標準化された輸血戦略
周産期救急におけるdamage control surgery
Part2 Perinatal Critical Care Course
1 PC3のプライマリーサーベイ(PC3-PS)
2 PC3のセカンダリーサーベイ(PC3-SS)
3 妊産婦の心肺蘇生
4 産科スキル
5 コースの構成
a スキルブースとシナリオステーション
b BLS・第一印象ブース
c 気道管理ブース
d モニター・電気ショックブース
Part3 死戦期(周死期)帝王切開シミュレーションガイド
シミュレーションガイド
シミュレーションシート
シナリオ
Part4 「アウェイ」での新生児蘇生
・索引
・執筆者紹介
・ピーシーキューブ
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:25.8MB以上(インストール時:56.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:103.2MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:21.4MB以上(インストール時:53.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:85.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784840457538
- ページ数:128頁
- 書籍発行日:2017年9月
- 電子版発売日:2018年7月27日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。


