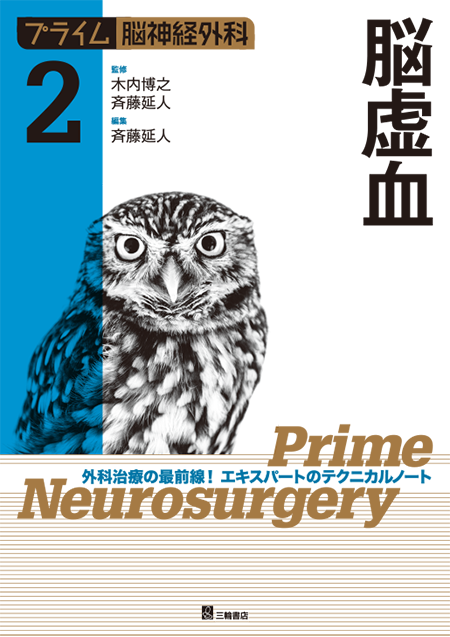- m3.com 電子書籍
- 三輪書店
- プライム脳神経外科 2 脳虚血
商品情報
内容
シリーズ第2巻「脳虚血」は、総論や内科的治療についてもしっかりと取り上げ、ひとつの手技でも複数の執筆者が解説することで多くの方法が学べるように工夫しています。
>「 プライム脳神経外科」シリーズはこちら
序文
第2巻の序
この『プライム脳神経外科』シリーズは,これまでにないユニークな方針で編集されています.ひとつには図を多用して,視覚的にわかりやすい本を目指しています.イラストの質にはとことんこだわり,タッチや色使いまで事前に吟味して統一した方針で描画しています.手術記録を描く時に,例えば手術動画をキャプチャして,ある場面を見えるままに記録しても,多くの場合手術の内容はよくわかりません.手術記録を描くとは,様々な場面をつなぎ合わせて,わかりやすいように頭の中でシェーマ化して構成されたものを提示することになります.本書でも,そのようなシェーマ化されたイラストを多用しています.一方で,文章は簡潔を旨として箇条書きを中心に構成されています.手術の前に本書をパラパラとめくり,頭にイメージをたたき込んで手術に臨むような使い方を想定しています.また,執筆陣も臨床の最前線で活躍している将来の脳神経外科を担う第一級の若手脳神経外科医を起用して,教科書的で網羅的なものでなく実践的でポイントを押さえた技術書を目指しています.
さて,第2巻では「脳虚血」をテーマとしています.脳虚血の手術手技のカテゴリーを見れば,極論するとバイパス術と頚動脈内膜剥離術(CEA),血管内治療ではステントと血栓回収となり,一見バリエーションは少ないのですが,いくつかの工夫を加えることにより内容に厚みを増しています.ひとつには,総論的な事項や内科的治療についても取り上げました.また,手術手技には流派のようなものがありますので,ひとつの手技でも複数の執筆者にお願いし,なるべく多くの方法が学べるようにしています.
内容構成としては,まず総論的事項として,第Ⅰ章と第Ⅱ章に脳虚血の病態と診断についてまとめてあります.次いで頭蓋内血行再建術の手技として,STA─MCA anastomosis,OA─PICA anastomosis,STA─SCAバイパス術,もやもや病の間接血行再建術を取り上げています.頚動脈病変の治療としてCEAと頚動脈ステント留置術(CAS)の治療選択を述べていただいた後に,まずCEAの基本手技やその応用,術中モニタリングと術中診断,術後過灌流障害の対策について解説していただきました.次いで,CASについて,ステントの種類と使い分けについて解説していただいた後に,PRECISEⓇ,PROTÉGÉTM,Carotid WALLSTENTTM MonorailTMEndoprosthesis など実際のデバイスの使い方を紹介しています.さらに,プロテクションデバイスについてもその種類と使い分けにはじまり,FilterWireⓇ EZ,SpiderFXTM,CarotidGUARDWIREⓇ,Mo.Ma UltraTM,OPTIMOTMの使い方について解説していただきました.ステントについては術前後の治療も大切ですので,周術期抗血栓療法,ステント血栓症とプラークシフトについても取り上げています.
近年,デバイスの進歩が著しい急性期脳梗塞の血管内治療についても,まず,血栓回収デバイスの適応と各方法の使い分けについて解説した後に,PenumbraⓇ,SolitaireTM,TrevoⓇなど実際のデバイスの使い方について解説していただきました.頭蓋内動脈の狭窄の治療として,頭蓋内動脈ステント留置術(WingspanⓇ)とballoon PTA(GatewayTM,UNRYUTM)を取り上げました.最後に,内科的治療法についても取り上げ,急性期と慢性期の抗血小板療法や抗凝固療法をそれぞれ解説していただきました.
末筆になりましたが,ご多忙にもかかわらず,快く御執筆をお引き受け下さいました著者の皆様にこの場をお借りして厚く御礼を申し上げます.また,本書の編集を担当していただいた三輪書店の久瀬様に感謝申し上げます.本書が皆様の日常診療に必須の一冊となることを願っています.
2017年8月
東京大学 脳神経外科
斉藤 延人
目次
第Ⅰ章 脳虚血の病態と診断
1 脳虚血の病態と分類
2 脳卒中の重症度分類
3 高次脳機能障害の診断
第Ⅱ章 脳虚血の画像診断
1 MRI
2 CT
3 核医学
01_SPECT
02_PET
4 頚動脈プラークの総合的画像診断
第Ⅲ章 頭蓋内血行再建術
1 STA-MCA anastomosis①:良好な結果を得るための基本手技
2 STA-MCA anastomosis②:トラブルの事前回避と的確なリカバリーショット
3 OA-PICA anastomosis
4 STA-SCAバイパス術
5 間接血行再建術を用いたもやもや病の治療
6 もやもや病の複合血行再建術:STA-MCAバイパス術+EDMAPS
7 もやもや病のSTA-MCA anastomosis
第Ⅳ章 頚動脈病変
1 頚動脈内膜剥離術と頚動脈ステント留置術の治療選択
2 頚動脈内膜剥離術
01_頚動脈内膜剥離術の基本手技①:シャントを使用しない血栓内膜剥離術の解説と適応
02_頚動脈内膜剥離術の基本手技②:シャントの使用
03_高位病変の頚動脈内膜剥離術:高位病変に対する工夫
04_パッチを用いた頚動脈内膜剥離術
05_術中モニタリングと術中診断
06_過灌流障害の対策
3 頚動脈ステント留置術:ステント
01_ステントの種類と使い分け
02_PRECISE®
03_PROTÉGÉ
04_Carotid WALLSTENT Monorail Endoprosthesis
4 頚動脈ステント留置術:プロテクションデバイス
01_プロテクションデバイスの種類と使い分け
02_FilterWire® EZ
03_SpiderFX
04_Carotid GUARDWIRE®
05_Mo.Ma Ultra
06_OPTIMO
5 頚動脈ステント留置術:周術期抗血栓療法
6 頚動脈ステント留置術:ステント血栓症とプラークシフト
第Ⅴ章 急性期脳梗塞の血管内治療
1 頭蓋内動脈の急性閉塞
01_血栓回収デバイスの適応と各方法の使い分け
02_Penumbra®
03_Solitaire
04_Trevo®
2 頭蓋内動脈の狭窄
01_適応と各方法の使い分け
02_頭蓋内動脈ステント留置術(Wingspan®)
03_Balloon PTA(Gateway,UNRYU)
第Ⅵ章 内科的治療法
1 急性期内科的治療法
01_虚血性脳血管障害におけるrt-PA静注療法の適応と実際
02_抗血小板療法
03_抗凝固療法
2 慢性期内科的治療法
01_抗血小板療法
02_抗凝固療法
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:26.7MB以上(インストール時:59.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:106.8MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:84.4MB以上(インストール時:174.3MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:337.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784895905886
- ページ数:272頁
- 書籍発行日:2017年9月
- 電子版発売日:2019年6月26日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcher(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。