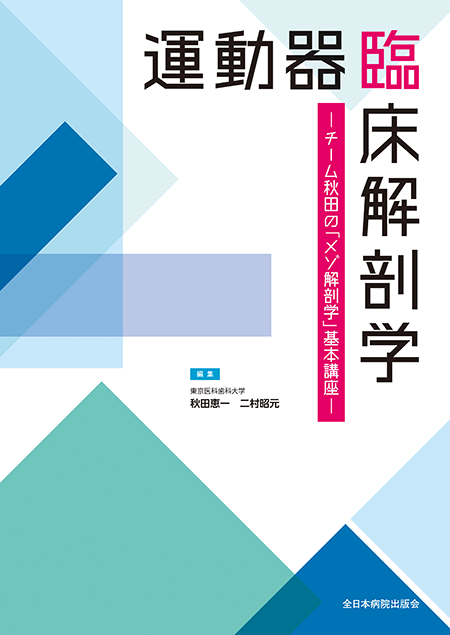- m3.com 電子書籍
- 運動器臨床
- 運動器臨床解剖学―チーム秋田の「メゾ解剖学」基本講座―
商品情報
内容
肩、肘、手、股、膝、足を中心に今までの解剖学の「通説」を覆す新しい知見を一書にまとめました。
マクロよりも詳しく、ミクロよりもわかりやすい「関節鏡視下手術時代に必要なメゾ(中間)解剖学」を扱う本書は、解剖学を学ぶ人のみならず、運動器を扱うすべての方必読です!!
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
いささか,本書のタイトルが気恥ずかしいが,お許し願いたい.本書は,我々の研究室で行ってきた研究のうち,特に運動器についての研究をまとめたものである.もともとは,「実臨床に直結する・役立つ知識を得られる書」を目指したものであったが,まとめていくうちに,「我々がどのようなことを考えて研究を行ってきたか」をわかっていただきたいという気持ちのほうが強く現れてしまった.多くの仲間達と,ともに悩み,学んできたことが形として一冊の本にまとめられたことが何よりの喜びである.
ミレニアム・イヤー(2000 年)前後は,整形外科の手術に関節鏡の使用が拡大した時であった.また,それに伴い,若手の外科医が解剖学的知見に興味を示してくれた時期でもあった.その時期に始めたのが本書で紹介されている研究である.
関節鏡により,拡大率も高まり視野が拡大した.様々な構造をこれまで見られなかったような角度から見ることが可能になった.それにより,局所における詳細な位置関係や,その組織学的性質までが注目されるようになったのである.我々は,臨床医から寄せられた多くの疑問に答えられるよう,これまでとは異なる視点での解剖を進め,構造の理解に努めてきた.はじめは膝関節,肩関節が中心であったが,多くの方々のご意見を参考にしながら,対象領域を拡大してきた.その結果,多くの領域に応用できる形態的共通性を明らかにし,これまでの形態の理解に数多くの誤解があったことが明らかになった.
解剖学は,人体を扱うための基本であると言われる.しかし,これまで一般的に理解されてきたことと異なるような新しい所見が得られたとしても,現時点での臨床に影響を与えることはそれほど大きくはない.それほど,現代では臨床医学の進むスピードが早く,立ち止まることができない状況なのである.『精神と物質
分子生物学はどこまで生命の謎を解けるか』(立花隆,利根川進. 文藝春秋,1990 年)の中で,ノーベル賞学者の利根川氏は,「より一般性のある,より普遍性のある原理や法則を見つけて行くことが科学の発展というものでしょう.(中略)ところが現実には,各論の中でもとりわけどうでもいいようなことをやってる人が多すぎるんです.」と述べている.これは,各論をいくらやっても科学的な原理には近づかないのだというような文脈の中で述べられたことである.確かに,肉眼解剖学的な所見をいくら明らかにしても,各論の域をでるものではなく,科学の進歩において「どうでもいいようなこと」ばかりであるかもしれない.ただ,我々は,これまでの知見を追認してきただけではない.本書を眺めていただければ,関節を中心とした運動器の解剖学に対する新しい考え方や手法がいくつも示されていることに気づいていただけると思う.これらの考え方や手法は,これから臨床解剖学的研究を進めていくうえで,部位を問わず有用となりうるものである.また,それらをもとに,まだ解き明かさなくてはならないテーマが多いことを示唆している.この本が,運動器の解剖学を学ぶ人にとって,また,新しい次元で臨床医学の発展を考える人にとって少しでも参考になるのであれば,望外の喜びである.
我々の教室の研究をサポートし,東京医科歯科大学にジョイントリサーチ講座「運動器機能形態学講座」を設置してくださった一般社団法人 JA 共済総合研究所に深謝いたします.本書の内容は,JA 総研との長い共同研究を核として発展させ,結実したものが中心となっています.大学の使命である学術研究と,JA 総研が目指す生活者の健康向上との橋渡しを本書が担うことを願っております.
また,本書に示された研究や解剖学的な考え方の非常に大きな礎となっている,運動器以外の分野の研究を支えてくれた教室員,教室のOB に深く感謝いたします.
本書の企画をいただいてから形になるまで,3 年余りもかかってしまいました.そして,最後の段階になって,コロナウイルス感染拡大などに伴う諸事情も加わってしまいました.その間,多くの示唆をいただき,本当に忍耐強くサポートしてくださった,全日本病院出版会の田澤佳枝氏,小林玲子氏に心より感謝申し上げます.
2020年5月
東京医科歯科大学臨床解剖学分野 秋田恵一
東京医科歯科大学運動器機能形態学講座 二村昭元
目次
Ⅰ章 総論
■チーム秋田の臨床解剖学とは/秋田 恵一
Ⅱ章 各論<部位別トピックスと新たな臨床解剖学的知見>
肩関節の解剖
1 肩関節包による肩関節安定化/二村 昭元
2 肩甲帯を支配する神経の解剖/那須 久代
3 腱板前上方断裂に関する解剖/新井 隆三
4 腱板後上方断裂に関する解剖/望月 智之
5 小円筋の臨床に関係する解剖と筋活動/浜田 純一郎
6 肩鎖関節脱臼に関する解剖/中澤 正孝
7 小胸筋に関する解剖/吉村 英哉
肘関節の解剖
1 肘関節の安定性に関する前方・外側軟部組織の解剖/志村 治彦
2 肘関節内側部の安定化/星加 昭太
手関節の解剖
1 母指MP関節尺側側副靱帯損傷に関する解剖/佐藤 哲也
2 橈骨遠位端掌側部の軟部組織構造/那須 久代
3 橈骨遠位端掌側部の骨構造/那須 久代
股関節の解剖
1 股関節手術に必要な短外旋筋群の解剖/田巻 達也
2 股関節包前上方部の寛骨臼付着に関する解剖/堤 真大
3 中殿筋腱断裂に関する解剖/堤 真大
4 ハムストリング筋群,特に大腿二頭筋の長頭と半腱様筋の起始部の特徴/秋田 恵一
膝関節の解剖
1 下腿前面の皮神経の分布と鵞足周囲の筋膜の層構造/秋田 恵一
2 前・後十字靱帯の解剖/塚田 幸行
3 内側膝蓋大腿靱帯の解剖/秋田 恵一
4 膝前外側支持組織の解剖/那須 久代
足関節の解剖
1 足関節外側靱帯損傷の解剖/服部 惣一
2 足根洞症候群と距骨下関節不安定症に関する解剖/山口 玲子
3 成人扁平足の病態と足関節内側安定化機構/天羽 健太郎
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:18.9MB以上(インストール時:43.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:75.7MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:18.9MB以上(インストール時:43.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:75.7MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784865192742
- ページ数:186頁
- 書籍発行日:2020年5月
- 電子版発売日:2021年8月6日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。