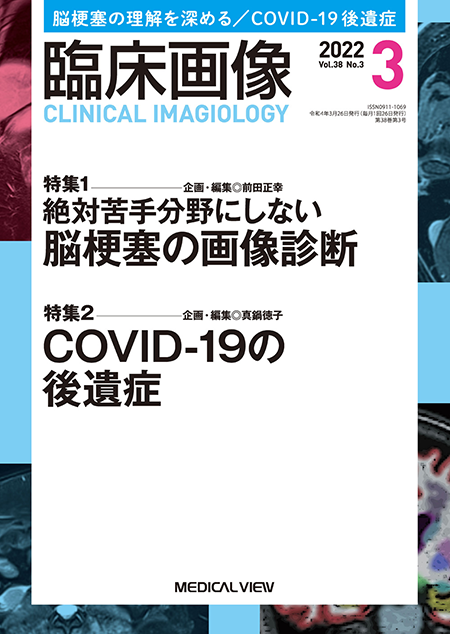- m3.com 電子書籍
- 雑誌
- 臨床医学:その他
- 臨床画像
- 臨床画像 2022年3月号 特集 1:絶対苦手分野にしない 脳梗塞の画像診断/特集 2:COVID-19の後遺症
商品情報
内容
急性期脳梗塞のCT診断
脳梗塞のMRI診断
急性期脳梗塞におけるtarget ミスマッチ評価 ほか
≫ 「臨床画像」最新号・バックナンバーはこちら
≫ 臨床画像(2022年度年間購読)受付中!
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
特集1 絶対苦手分野にしない 脳梗塞の画像診断:序説
脳梗塞は最も多い中枢神経系疾患であり,ほとんどの放射線診断医が画像の読影を経験する疾患である。院内の読影やカンファレンスのなかでも脳梗塞を目にする機会が多いことから,若手であってもすでに脳梗塞の理解とその画像の読影に自信があると感じている先生方も少なくないかもしれない。脳梗塞のなかでも急性脳梗塞の画像所見は単純CTによる早期虚血変化として知られ,また,MRIでは特に拡散強調像によってどこに梗塞があるのか,どの程度のサイズの梗塞であるのかがより明確にわかるようになった。さらに,造影剤を使った灌流画像によって得られるペナンブラの情報は,急性期脳梗塞の血管内治療に大きな役割を果たすと期待された。しかしながら,急性期脳梗塞の血管内治療の選択基準にCTやMRIの画像が使われ,それに基づいた治療の有効性が証明されたのは比較的最近のことである。
わが国で発症4時間半以内の急性期脳梗塞に対する静注血栓溶解療法(tPA静注療法)の臨床導入後17年が経過した。また,最近では発症24時間以内の急性期脳梗塞症例に対する機械的血栓回収療法の有効性のエビデンスが明らかとなった。これを受け,再開通療法を行う際の画像を含む適応や禁忌に関して,ガイドラインの追補,変更点が出た。現場で必要とされる画像撮影法とその読影のポイントにも新たな変化が出てきている。このような急性脳梗塞診療の過渡期のなか,放射線診断医が今まで学習してきた知識と脳卒中診療を専門とする医師がもつ知識には乖離が生じていると思われる。
今回の企画では,若い先生方が脳梗塞に関する基本的な知識を改めて学ぶとともに,脳卒中診療を専門とする医師と同じ土俵で急性期脳梗塞の治療戦略と,それに必要な画像診断を語れるための知識のアップデートを図ることを目的としている。執筆の先生方には,若い先生方にも十分理解できるような平易な文章で解説をお願いし,また適切で典型的な画像を提示していただいた。本特集号によって,脳梗塞の画像診断の理解が深まり,日々の診療にお役に立てば幸いである。
企画・編集:前田正幸
三重大学大学院医学系研究科 地域支援神経放射線診断学講座
特集 2 COVID–19の後遺症:序説
新型コロナウイルスのデルタ株が猛威を振るった2021年の夏の第5波が終わり,ようやく医療体制が元にもどったのもつかの間,年が明けてあっという間にオミクロン株による第6波に突入した。2022年1月現在,国内の累積感染者数は200万人を超えている。
初期のCTによる肺炎評価にどう対応するかというフェーズは過ぎ,オミクロン株は肺炎像が少ないこともあり,現在はむしろ増え続ける感染後の後遺症患者にどう対応するかが社会的に問題となり,long COVIDともよばれる病態も少しずつクローズアップされてきている。
今回の特集では,心血管および中枢神経系の後遺症にフォーカスして,新型コロナウイルス後遺症外来で多くの患者さんを実際に診察しておられる循環器内科の相川忠夫先生,そして米国の現状にもお詳しい黒川真理子先生らに病態や画像所見について解説いただいた。
また,ワクチン後の副反応も腕の痛みや発熱に加えて,若年層では心筋炎合併が問題となっており,国民の大部分が受けるであろう3回目ワクチン後の副反応についてわれわれの知識をアップデートする時期にきていると考えている。
新型コロナウイルスのパンデミックが始まってから2年が経とうとしているが,ウイルスの変異はまだ続くであろうし,現時点での皆様の知識の整理に役立てていただければ幸いである。
企画・編集:真鍋徳子
自治医科大学附属さいたま医療センター 放射線科
目次
特集 1:絶対苦手分野にしない 脳梗塞の画像診断 企画編集 前田正幸
序説
急性期脳梗塞のCT診断
脳梗塞のMRI診断
急性期脳梗塞におけるtarget ミスマッチ評価
急性期脳梗塞の治療:機械的血栓回収療法を前提とした画像検査の実際
特殊な栓子による脳梗塞
全身疾患と脳梗塞
脳静脈(洞)血栓症
脳梗塞の画像所見に類似する疾患
特集 2:COVID-19の後遺症 企画・編集 真鍋徳子
序説
総論:COVID–19後遺症とは
Brain Fogとは:神経系の後遺症
COVID–19関連の心血管後遺症
Report
日本スカンジナビア国際放射線医学シンポジウム報告
Pr ogress in Radiology 2021:Joint meeting of the 13th Symposium of Japanese Scandinavian Radiological Society and 16th Nordic Japan Imaging Informatics Symposium
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:16.5MB以上(インストール時:35.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:66.0MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:16.5MB以上(インストール時:35.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:66.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784008004203
- ページ数:0頁
- 書籍発行日:2022年2月
- 電子版発売日:2022年2月21日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。