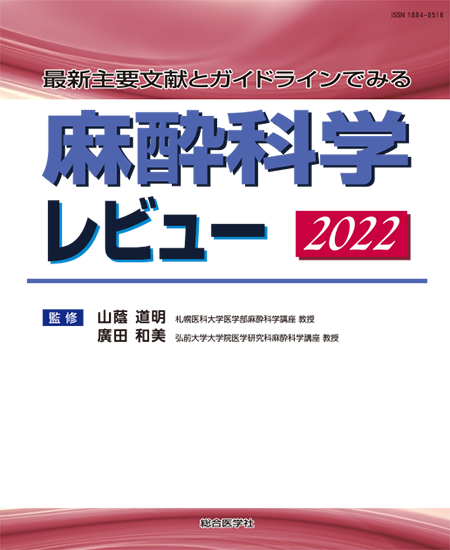- m3.com 電子書籍
- ���������������
- 最新主要文献とガイドラインでみる 麻酔科学レビュー2022
商品情報
内容
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序文
今年も「最新主要文献とガイドラインでみる麻酔科学レビュー2022」をお届けするに至りました.原則として,2020年8月~2021年7月までの1年間に,国内外で発表された主要文献を,それぞれの領域における第一人者にpick upして解説いただいたものを2022年版として発行しています.2022年版も2021年版と同様,本“ 序文” を書いている2022年4月の時点で新型コロナウイルス感染症が猛威を振るっており,多くの執筆者が日常臨床で対応いただいている中,何とか全員にご執筆いただき,遅滞なく発刊することができ,監修者としてホッとしているところです.項目に関しては昨年とほぼ同様ですが,執筆者を数名若手のエキスパートと交替し,刷新を図りました.4年前からの試みとして,ガイドラインが発表されている項目に関しては,どんどん取り入れていただき,麻酔科医や集中治療医にとって日常臨床に有効活用できる内容と確信しております.
さて,今回のレビューの特徴として,引き続き“ 新型コロナウイルス感染症” に関する話題が多く掲載されております.医療者側が感染の機会に曝露される「麻酔と気道管理・確保」,「麻酔と呼吸機能」,「麻酔領域での経食道心エコー(TEE)による評価」,「手術室危機管理・安全対策」,ならびに「WHO安全な手術のためのガイドライン」では,いくつかのガイドラインや対応策などが報告されており,現場で活躍する麻酔科医や集中治療医,さらには救急医療医にとっても目を通すべき論文や資料が多いかと思います.前号に引き続き,この感染症のパンデミックに伴い,依然として献血の機会が少なく(「輸血と輸液」),同種血輸血製剤のひっ迫に伴う「自己血輸血」の重要性が語られています.本邦でも厚労科研で研究が行われましたが全国的に手術件数が減少し(「心臓・大血管手術の麻酔」),重症患者に多くの麻酔科医が対応している現状から,麻酔科医不足(「麻酔科医と救急医療」)やそれに伴って手術室の運営にも影響を与えています(「手術室の効率化と安全」).一方,デルタ株で注目された血栓症や出血などに関する凝固異常のエビデンスもいくつか紹介されており,これも日常臨床を行う際に有用な情報となるでしょう(「抗血栓療法ガイドライン」).
一方,新型コロナウイルス感染症とは関係ありませんが,興味深いエビデンスも紹介されています.本邦において定期手術の絶飲食時間はまだ長過ぎはしないか(「術前絶飲食」)?滅多に遭遇しないが悪性高熱症の新たなガイドラインが発表されたためきちんと目を通しておく必要はないか(「悪性高熱症ガイドライン」)? 本邦だけで臨床使用されているレミマゾラムをもっと熟知しておく必要はないか(「新しい全身麻酔薬レミマゾラム」)? 日々多くの高齢者麻酔を行っているわれわれ麻酔科医としてより良い周術期管理は何か(「麻酔と脳神経機能」,「高齢者麻酔」)? など麻酔科医としての興味は尽きません.これら麻酔科領域におけるトピックスを自分で選択し,重み付けをして,さらに読み解くにはどれだけの時間と労力を必要とするかを考えると,少々高い医学書と思ったとしてもかなりお得な感じがします.事実,監修し,執筆者達のゲラ原稿を読んでいるだけでも知識の整理ができて充実した気持ちになりました.ここから新たな臨床研究や基礎研究のヒントを得るのも一考かと思います.
本著は,専門医はもちろん,これから専門医を目指す麻酔科専攻医,あるいは麻酔科領域に興味のある医師が読者対象になります.麻酔科診療に携わる多くの先生方がこの本を手にし,是非ご一読いただき,目の前にいる患者さんに役立つことができれば,監修者として望外の喜びです.
2022年6月
監修
山蔭 道明
廣田 和美
目次
1 麻酔前投薬と術前評価
2 術前絶飲食
3 周術期禁煙ガイドライン
4 麻酔と気道管理・確保
5 吸入麻酔薬
6 悪性高熱症ガイドライン
7 静脈麻酔薬(麻薬を除く)
8 新しい全身麻酔薬レミマゾラム
9 筋弛緩薬と拮抗薬
10 局所麻酔薬
11 心・血管作動薬
12 麻酔に用いられる麻薬性鎮痛薬と鎮静薬
13 麻酔と呼吸機能
14 麻酔と心機能
15 麻酔と冠循環
16 麻酔と肝機能
17 麻酔と腎機能
18 麻酔と脳神経機能
19 麻酔薬と臓器保護作用
20 麻酔深度とモニター活用法
21 麻酔領域での経食道心エコー(TEE)による評価
22 超音波診断と末梢神経ブロック
23 周術期ポイントオブケア超音波~ABCD sonography~
24 輸血と輸液
25 宗教的輸血拒否
26 危機的出血への対応
27 自己血輸血
28 全静脈麻酔(TIVA),鎮静(MAC)
29 手術室危機管理・安全対策
30 WHO安全な手術のためのガイドライン
31 硬膜外麻酔と脊髄くも膜下麻酔
32 小児麻酔
33 高齢者麻酔
34 緊急手術の麻酔
35 産科麻酔
36 産科危機的出血への対応ガイドライン
37 内視鏡・ロボット手術の麻酔
38 日帰り手術の麻酔
39 心臓・大血管手術の麻酔
40 小児心臓手術の麻酔
41 脳外科の麻酔
42 Awake craniotomyの麻酔
43 移植手術の麻酔
44 抗血栓療法ガイドライン
45 麻酔関連偶発症
46 痛みの生理学
47 術後の疼痛管理
48 ペインクリニック
49 緩和ケアとがんの痛みの治療
50 麻酔科医と救急医療
51 心肺蘇生と脳保護
52 手術室の効率化と安全
53 麻酔科領域の新機材,新技術,新知見
54 新しい人工呼吸
55 集中治療(1)呼吸・循環管理
56 集中治療(2)体液,栄養,感染の管理
57 集中治療(3)ICUにおける鎮痛と鎮静
58 集中治療(4)ICUにおけるモニター
59 集中治療(5)小児集中治療
60 血液浄化療法
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:16.3MB以上(インストール時:43.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:65.1MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:16.3MB以上(インストール時:43.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:65.1MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784883787487
- ページ数:352頁
- 書籍発行日:2022年6月
- 電子版発売日:2022年6月10日
- 判:AB判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:2
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。