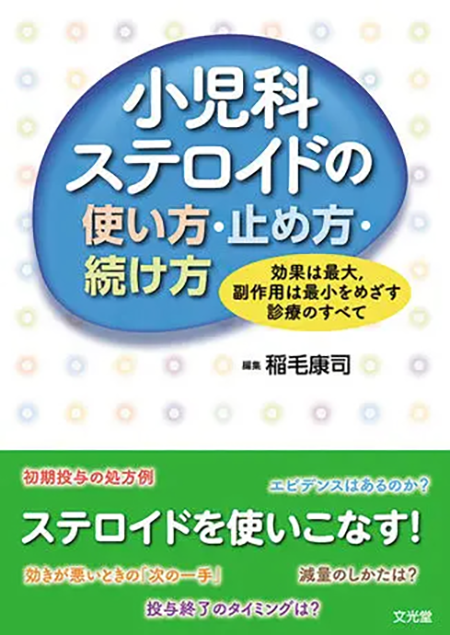- m3.com 電子書籍
- 小児科ステロイドの使い方・止め方・続け方
商品情報
内容
小児診療におけるステロイド薬の使い方について,common disease(気管支喘息やアトピー性皮膚炎など)から専門領域(腎疾患,膠原病や眼科疾患など)まで解説.初期投与の処方例,減量のしかたや投与終了のタイミング,注意すべき副作用とその対応,効きが悪いときの「次の一手」など,実際の臨床で知りたい,知っておくと役立つポイントを,エビデンスを交えながら,病態・疾患ごとに解説した.小児科医をはじめ,小児を診る機会のあるすべての臨床医に役立つ一冊.
序文
序
小児科診療において,正確な診断と的確な治療が大原則であることはいうまでもない.この的確な治療にあっては,輸液療法,抗菌薬療法,ステロイド療法が三本柱である.いかに切れ味のよい治療が達成可能かはこれらの三療法に精通しているかによる.中でも,ステロイド療法は伝家の宝刀である.とっておきの切り札だが,使い方を誤ると自らが怪我をしてしまう.そうかといって,副作用を恐れて臆病になるのも困ったものである.ステロイド薬の特性を知った上で,大上段に構えて相対する病態に一撃を加えてほしい.
ステロイド療法を扱った図書は数多くあるが,小児科領域に特化した参考書は見当たらない.本書は「小児科ステロイドの使い方・止め方・続け方」と題して,小児科領域に関わるあらゆる疾患におけるステロイド療法を幅広くカバーした現在唯一の参考書である.本書で取り上げた疾患すべてが,ステロイド療法の適応というわけではない.むしろ,ステロイド薬を使用しないほうがよいと論述している疾患項目もある.指南書として,必ずやお役に立てるものと確信をしている.
本書を企画する中で,たまたま病棟医から寄せられた質問が気になった.経口プレドニゾロン薬10mgと水溶性プレドニゾロン薬10mgはともに等力価なのだから効果も同じはずなのに,どうして経口プレドニゾロン薬を優先して使用するのかがわからない,という内容であった.なるほど説明するとなると,なかなかの難問である.実際にリウマチ膠原病診療では,同じ力価であっても,経口投与のほうが静脈投与よりも効果がある.成書には静脈投与をする場合,経口投与量の1.5~2倍に増量(2分割で)したほうがよいとされている.
ステロイドの基本骨格はシクロペンタノヒドロフェナントレン環であり,脂溶性で水に溶けにくい特性がある.コハク酸でエステル化して水溶性にしたのが,水溶性プレドニゾロン薬(プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム)である.水溶性プレドニゾロン薬を静注すると,体内で加水分解されてプレドニゾロンとなって種々の作用を発揮する.どの程度の加水分解が起こって,遊離型プレドニゾロンに変化するのかは,個体差で異なる.血中濃度でみた薬物動態では,経口プレドニゾロン薬も水溶性プレドニゾロン薬も差異はないという報告が多く,用量依存性では説明できない.これらの報告では,平均滞留時間(mean residence time:MRT)について言及はされておらず,薬効を理解するには不十分であった.
そのような中で,体内での水溶性プレドニゾロン薬静注後のプレドニゾロンとしてのMRTは,経口プレドニゾロン薬のMRTの49%であり,血中からの消失が速く,体内を通過するのに要する時間が短いことを報告している論文に出会った.これは,静脈投与量を増量する考えを支持するものである.また,経口ステロイド薬投与では,腸で自然抗体や自己抗体を産生するB-1 B細胞に作用することが優れた治療効果に関係しているという推論もある.
併せて,ステロイド薬の抗炎症効果はコルチゾール血中濃度で1μg/mL(プレドニゾロン10mg/日相当)で得られ,免疫抑制効果はコルチゾール血中濃度で2.6μg/mL(プレドニゾロン25~30mg/日相当)で得られる.ステロイド投与量を,抗炎症と抗免疫作用を分けて考えることが大切である.
先の質問は,投与するステロイド薬,投与方法,投与量,剤形の違いで,生理学的,薬理学的作用も変わり,結局のところ臨床効果を左右する範例として取り上げてみた.なかなか,ステロイド療法は奥深く,科学的に説明したくとも経験則が優先される不可思議なところがある.とはいっても,常に合理的に病態生理に沿って,ステロイド療法を行う上での心構えとしてご参考になればと思う次第である.
多忙にもかかわらず,本書の企画に賛同していただきご執筆下さった,斯界のエキスパートの先生方に深謝をいたします.また出版にあたりまして,文光堂編集企画部の佐藤真二氏,臼井綾子氏のご協力をいただいたことに感謝をいたします.
2019年1月
稲毛 康司
目次
I 総論
A ステロイドの作用機構と薬理作用,副作用
B ステロイド療法の実際
1.投与方法
2.ステロイド薬の使い分け
C ステロイド薬の副作用
1.全身投与ステロイド薬(経口薬,注射薬)
a.概説
b.成長障害
c.グルココルチコイド誘発性骨粗鬆症
d.ステロイド緑内障・白内障
e.ステロイド糖尿病
f.高血圧・可逆性後頭葉白質脳症など
2.吸入ステロイド薬(鼻,気管支)
3.皮膚外用ステロイド薬
D ステロイド薬に対する過敏反応(ステロイドアレルギー)
E その他
1.患者・家族への説明─日常生活上の注意点
2.ステロイドと予防接種
II 各論
A 病態に応じたステロイド療法
1.敗血症性ショック
2.緩和ケア─がん疼痛
3.移行期医療─ステロイド薬と妊娠
4.周術期管理,ステロイドカバー
5.ステロイド離脱症候群
B 疾患別のステロイド療法
1.リウマチ膠原病
a.若年性特発性関節炎(JIA)
b.全身性エリテマトーデス(SLE)
c.若年性皮膚筋炎・多発性筋炎,免疫介在性壊死性ミオパチー
d.IgA血管炎(Henoch-Schönlein紫斑病)
2.自己炎症性疾患
a.PFAPA症候群
b.ステロイド療法が主に行われる自己炎症性疾患
TRAPS,PAPA症候群,Blau症候群/若年発症サルコイドーシス,中條-西村症候群,高IgD症候群,クリオピリン関連周期熱症候群
3.免疫疾患
a.IgG4関連疾患
コラム 原発性免疫不全症とステロイド療法
4.感染症
a.細菌性髄膜炎
b.マイコプラズマ肺炎
c.ウイルス性肺炎
d.伝染性単核球症
e.敗血症
5.川崎病
6.菊池病
7.神経疾患
a.急性脳症
b.重症筋無力症
c.免疫性中枢性神経疾患
多発性硬化症,視神経脊髄炎,急性散在性脳脊髄炎
d.免疫性末梢性神経疾患
Guillain-Barré症候群,Fisher症候群
e.自己免疫性脳炎・脳症
NMDAR脳炎,橋本脳症
8.筋疾患
a.デュシェンヌ型筋ジストロフィー
9.循環器疾患
a.心筋炎
10.内分泌疾患
a.リンパ球性漏斗神経下垂体炎
b.亜急性甲状腺炎
11.消化器疾患
a.炎症性腸疾患
潰瘍性大腸炎,Crohn病
b.好酸球性消化管疾患
好酸球性食道炎,好酸球性胃腸炎
12.肝疾患
a.自己免疫性肝炎
13.血液疾患
a.免疫性血小板減少症
b.血栓性血小板減少性紫斑病
c.血球貪食症候群
d.Kasabach-Merritt現象
e.好酸球増加症
コラム TAFRO症候群
14.腎疾患
a.ネフローゼ症候群
b.紫斑病性腎炎
15.呼吸器疾患
a.クループ症候群
b.特発性間質性肺炎
c.過敏性肺炎
16.アレルギー疾患
a.アレルギー性鼻炎
b.気管支喘息
1)長期管理
2)急性増悪(発作)
17.眼科疾患
a.アレルギー性結膜炎
b.ぶどう膜炎
18.耳鼻咽喉科疾患
a.突発性難聴,ANCA関連血管炎性中耳炎
b.顔面神経麻痺
19.皮膚科疾患
a.アトピー性皮膚炎
b.Stevens-Johnson症候群・中毒性表皮壊死症
c.薬剤性過敏症症候群と急性汎発性発疹性膿疱症
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:11.2MB以上(インストール時:28.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:44.8MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:38.5MB以上(インストール時:82.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:154.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784830630408
- ページ数:224頁
- 書籍発行日:2019年1月
- 電子版発売日:2019年3月22日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。