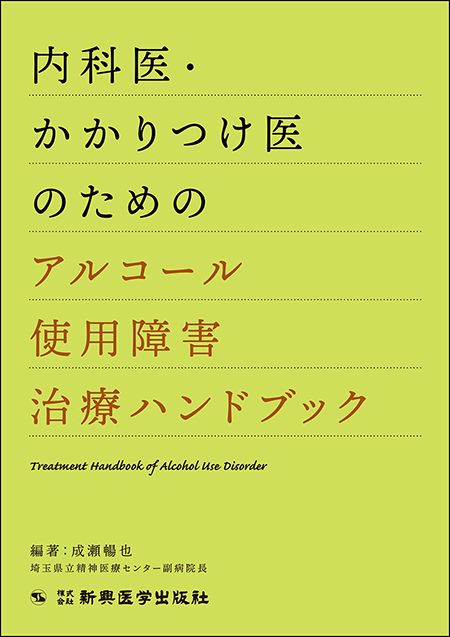- m3.com 電子書籍
- ���������������������
- 内科医・かかりつけ医のためのアルコール使用障害治療ハンドブック
商品情報
内容
糖尿病、脂肪肝、不眠にはアルコール問題が隠れているかもしれません。外来男性患者の10人に1人が問題飲酒者とされています。消化器内科医やかかりつけ医が健康診断や日々の診療で気づき、減酒指導を始めることが重症化を防ぎます。飲酒量低減薬ナルメフェン活用術や減酒外来の取り組みを多数紹介した、今日からできる臨床医向けハンドブックです。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序
平成26年6月,アルコール健康障害対策基本法が施行され,さまざまなアルコール関連問題に関心が高まっています.しかし,アルコール依存症の治療・支援はこの流れに追いついておらず,他の精神疾患の治療に比べて遅れていると言わざるを得ません.この原因はどこにあり,どのように対処すればよいのでしょうか.
わが国で107万人と推定されるアルコール依存症患者のうち,5万人程度しか治療につながっていないというトリートメントギャップをどのように考えればよいのでしょうか.どうして治療が必要な患者に治療を提供できていないのでしょうか.
最大の原因は,アルコール依存症に対して深刻な誤解と偏見があり,正しい認識がされていないこと,そして,いまだに依存症が進行・重症化してから専門医療機関で入院治療を行う形が治療の「ひな型」になっているからだと考えます.患者は医療機関を敬遠し,医療機関は患者を敬遠しています.がん治療に喩えると,末期になるまで何もしないで,「末期・重症化したがん患者だけを専門医療機関で治療しているようなもの」です.100万人とも推定される早期軽症患者を放置してはならないのです.
この状況を打開するためには,アルコール依存症に対する誤った認識を払拭することが不可欠です.私たちは,最重症のアルコール依存症のみをアルコール依存症と認識していなかったでしょうか.このような状況で,米国精神医学会の国際的診断基準であるDSM—5では,「依存症」の診断名を廃止し,依存と乱用を合わせた「使用障害」を新たな診断名として採用しました.診断名を「使用障害」とすることで,「依存症」診断よりもさらに軽症群を取り込み,依存症診断に纏わりつく誤解や偏見から解放されることが期待できます.
そもそもアルコール依存症の「中核群」は,現在治療対象とされている「進行群・重症群」ではなく,大多数を占める依存症治療につながっていない「軽症群」のはずです.この未治療の多数の患者への介入が中心とならなければ重症化を防ぐことはできません.そして,その治療を行うのは,限られた少数の専門医療機関ではなく,広く提供されるプライマリ・ケアです.さらには,消化器内科をはじめとした身体科医療機関,一般精神科外来です.内科などでは身体健康問題として,精神科ではメンタルヘルス問題として,他のありふれた疾患同様「普通に」関わる視点が重要であると考えます.
本著は,平成30年8月に「プチ・アルコール依存に気づく―誰にでもできるアルコール使用障害への対応―」のテーマで,「Modern Psysician」誌に特集として掲載された内容をもとに,さらに新たな執筆陣に加わっていただき充実を期したものです.
この間にもさまざまな変化が起きています.依存症の治療ガイドラインに飲酒量低減を治療目標とすることが初めて採用され,飲酒量低減薬であるナルメフェンが内科医でも処方が可能になり,いわゆる「減酒外来」が専門医療機関でも実施されるようになりました.また,「無理にやめさせようとはしない」ハームリダクションの考えが依存症臨床に取り入れられ始めており,肝硬変の治療ガイドラインにもハームリダクションが取り上げられるなど,アルコール依存症を取り巻く状況は大きく変わり始めています.単行本化に際して,これらの最新の情報についても,実践報告も含めてご執筆いただきました.
つまり「何が何でも断酒しかない」という考えから,「やめられないならダメージを減じる支援から始めよう」と現実的な対応が選択肢として採用されたことになります.無理にやめさせようとしてきたことによって,治療経過で無用な対立を生み,患者・治療者双方が傷つき不快な思いを重ねてきました.このことを払拭するだけでも,治療は格段に円滑に進むはずです.そのために依存症を正しく理解し,適切な対応を身につけることは重要です.
内科医やかかりつけ医は,すでに多くのアルコール使用障害の診療を行っています.一般の精神科医よりもその経験は豊富だと思います.その治療の過程で,「酒を控えなさい」「これ以上飲んだら死ぬよ」だけではない対応を,短時間でも提供していただけるなら,わが国のアルコール依存症患者の惨憺たる状況を変えられると期待しています.
その際に,疾患としては「糖尿病モデル」が参考となるでしょう.また,さまざまな診療科で関わり,複雑な問題や問題行動,精神疾患の合併がある場合は精神科で診るという治療構造は,「てんかんモデル」と言えるのではないでしょうか.
アルコール依存症は決して特別な疾患ではありません.誰もがなりうるありふれた疾患です.患者は特別な人たちではありません.そして特別な治療が必要なわけでもありません.アルコール依存症が特殊な専門治療を要する疾患から,プライマリ・ケアで対応可能な疾患であるという認識が広がることを期待しています.そして,依存症より軽症例を取り込んだアルコール使用障害に対して,適切に対応できる体制が広がることを願っています.本書がその端緒となるならば,編者としてこれ以上の喜びはありません.
さいごに,ご多忙のなか優れた原稿をご執筆いただいた第一線の内科医,精神科医の先生方に心より感謝いたします.また,私の無理なお願いを快く受け入れていただいた新興医学出版社社長林峰子様,編集にご尽力いただいた宮澤咲様に心よりお礼を申し上げます.
2022年10月
成瀬暢也
目次
chapter 1 アルコール使用障害治療の大きな転換
1 軽症群に対する早期介入の推進の重要性
chapter 2 アルコール使用障害の基本を理解する
1 アルコール依存症とアルコール使用障害の違い
2 アルコール依存症の大多数は治療につながっていないのか
3 アルコール健康障害対策基本法の施行に伴う動向
4 アルコール使用障害の背景に何があるのか
5 アルコール使用障害はどのように治療し回復するのか
6 アルコール使用障害のスクリーニングと重症度評価
chapter 3 プライマリ・ケアや産業保健でのアルコール使用障害への介入
1 プライマリ・ケアにおけるアルコール使用障害への介入
2 総合病院におけるアルコール使用障害の治療
3 アルコール使用障害の治療のポイント
4 プライマリ・ケアでできるブリーフインターベンション
5 アルコール使用障害患者のために内科医はどのような連携をとるべきか
6 地域保健におけるアルコール使用障害患者への対応
7 職場におけるアルコール使用障害者への対応
8 産業保健におけるブリーフインターベンションの効果
9 プライマリ・ケア,産業医から専門医療機関へのつなぎ方
chapter 4 飲酒量低減外来とナルメフェン導入が治療を変える
1 飲酒量低減薬を使ったアルコール使用障害の治療の実践
2 飲酒量低減薬を使った治療の実践
①湘南慶育病院消化器内科
②北茨城市民病院附属家庭医療センター
③佐賀県医療センター好生館
④さくらの木クリニック秋葉原
⑤各務原病院
3 専門医でなくてもできる介入
①波乗りクリニック
②ロコメディカル江口病院
③兵庫県立はりま姫路総合医療センター
chapter 5 専門医はどのような治療を行っているか
1 外来専門医療機関での治療
2 専門医療機関における減酒外来の実際
3 依存症専門医から内科医への助言と応援
4 アルコール使用障害を抱える人と関わるコツ
5 動機づけ面接の実際
6 ワークブックを使った認知行動療法的アプローチの実際
7 女性の患者の特徴と治療
8 高齢の患者の特徴と治療のコツ
9 自助グループへの誘い方
付録 内科医と精神科医のためのアルコール問題に役立つツール
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.7MB以上(インストール時:26.9MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:42.8MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:10.7MB以上(インストール時:26.9MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:42.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784880029238
- ページ数:280頁
- 書籍発行日:2023年3月
- 電子版発売日:2023年1月20日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。