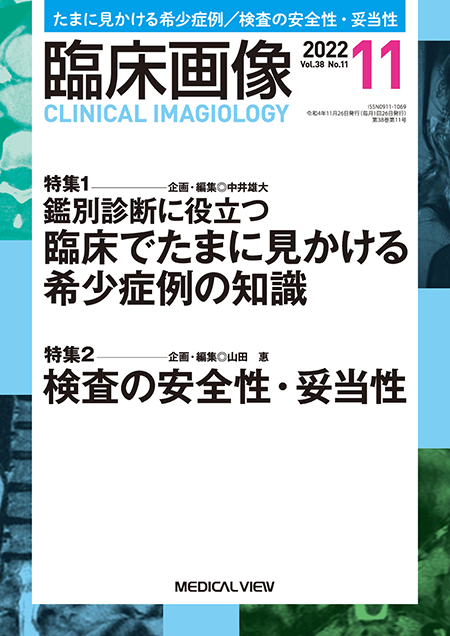- m3.com 電子書籍
- ������
- ������������������������
- ������������
- 臨床画像 2022年11月号 特集1:鑑別診断に役立つ 臨床でたまに見かける希少症例の知識/特集2:検査の安全性・妥当性
商品情報
内容
序説 中井雄大
臨床でたまに見かける中枢神経疾患
知っておくべきまれな頭頸部の病態
ほか
≫ 「臨床画像」最新号・バックナンバーはこちら
≫ 臨床画像(2022年度年間購読)受付中!
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序説
数年前,前方視的には診断の難しい症例を報告し,医局の大先輩と「こんな所見に気付くの無理ですよね〜。」と話していたら,「これを指摘するのが放射線科医の仕事でしょ。」という厳しいひと言をいただいた。放射線科医の仕事に誇りをもち,臨床医と密に連携をとっていないとなかなか出ない言葉だろう。彼だからこそ言える言葉だと思ったが,同時にまったくそのとおりだとも感じた。
放射線科医の担う画像診断の役割はさまざまだが,臨床医がわかっていることだけを述べるだけでは価値は生まれない。それは臨床医の気付いていない所見を拾い上げることだったり,所見に対して正確な解釈を行うことだったり,適切な次の一手を示すことだったりするが,疾患名を言いあてるということも大きな要素だろう。画像診断の楽しみ方はさまざまだと思うが,特に未診断の疾患を自ら診断するというのは放射線科医の醍醐味の1つといえる。
放射線診断医が円滑な診療を行ううえで,臨床医と良好な関係を築くというのは欠かせない要素であるが,赴任後間もない病院などではなかなかすぐに信頼は得づらい。common diseaseをこつこつと診断して信頼を勝ち得るのが王道だが,rare diseaseを的確に診断して臨床医をうならせるというのも1つの手である。もちろんいつもホームランを狙って空振りしていては逆に信頼を落とすことになりかねないので,何事もバランスが大事ではあるが,画像診断医としてはぜひ両方の側面を楽しみたいものである。
今回,臨床ではなかなか出会わないが,知っておくと役に立つ希少疾患の知識ということで編集の機会をいただいた。特定の領域を網羅する類の企画ではないため,各著者の先生方が経験された貴重な症例をベースにして,ただ珍しいだけではなく,特徴的な画像を呈する疾患や臨床医に伝える意義の大きな疾患について自由に執筆いただいた。企画の性質上,明日からすぐ役に立つとはいえない疾患がそろったが,示唆に富んだ症例が数多く記載されており,筆者も大変勉強になった。画像診断の好きな先生方に大いに楽しんでいただけると思う。そして読者諸氏のなかで一部の症例だけでもいつか臨床の役に立ち,臨床医の信頼を勝ち得,患者の人生に還元されることを心より願う。
最後になるが,筆者のような若輩者に貴重な編集の機会をいただいたこと,そして快く原稿の執筆をお受けくださった先生方に心より感謝申し上げたい。
中井雄大
序説:検査の安全性・妥当性を担保するには?
画像診断領域における業務量の増加は世界的現象のようだ。これにより各国で深刻な人手不足が生じている。実は相当な数の放射線科医がいるとされるアメリカですら不足している1)。このような人員不足の主因はズバリ,人口の高齢化である。これに加えて医療の専門分化も画像診断の需要を加速させる因子だ。これらが相乗的に働き,人手不足が生じているのだろう。
わが国における放射線科医の数は世界的にみても群を抜いて少ないことが知られている2)。従って業務量増加に伴う多忙さは他国と比べて異次元レベルにあるのだろう。例えば検査の適応を決めるところに,放射線科医の権限が及んでいない施設がかなりあるという。今回編集部から特集の企画立案を持ちかけられたときに最初に浮かんだアイデアが,全国の放射線科における実態調査である。メインテーマとして選んだのが「検査の安全性・妥当性」である。
各施設に執筆の依頼を出すに際して,お願いした具体的なポイントが大きく分けて2点ある。1つ目が適応についてである。最も極端な例として「放射線科医が検査を断ることがありますか?」という問いかけを行った。同時に造影剤の使用に関する決定権についても問うた。2つ目のポイントとしてお願いしたのが,検査の安全性や妥当性を担保するために行っている具体的な工夫についてである。写真を交えて環境整備を例示いただくようお願いした。
集まってきた玉稿はいずれも躍動感に溢れるものだ。現状を飾ることなく,ありのままの運営状況をご提示いただけたと思う。また文中には著者らの小さな工夫が散りばめられており,アイデアの宝庫となっている。さらにいえば各施設における部門の運営哲学についても,ご披露いただいたものがあり,著者らの職務への情熱が伝わってくるようだ。
これらを通読し各施設の現状を俯瞰することで,われわれのコミュニティに新たな共通認識ができることであろう。それはわれわれの診療形態が欧米のそれと相当異なるだけではなく,国内においてもバリエーションがあるという事実だ。国内のバリエーションは少ないほうがよいに決まっている。今後わが国においても欧米並みの標準化が進むことが切望される3)。そして,標準化しなければ人材の流動性は担保できない。逆に標準化を達成するには人材を流動させることも必要だ。本特集がそういうことを意識するきっかけになれば望外の喜びである。
それでは本特集をぜひとも,じっくりとお楽しみいただきたい。
文献
1) https://www.rsna.org/news/2022/may/Global-Radiologist-Shortage
2) Nakajima Y, et al:Radiologist supply and workload:international comparison:Working Group of JapaneseCollege of Radiology. Radiat Med, 8:455–465, 2008.
3) OECD Economic Surveys:Japan 2001
https://read.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveysjapan-2001_eco_surveys-jpn-2001-en#
山田 惠
目次
特集1 鑑別診断に役立つ 臨床でたまに見かける希少症例の知識 企画・編集:中井雄大
序説 中井雄大
臨床でたまに見かける中枢神経疾患 黒川 遼
知っておくべきまれな頭頸部の病態 神田知紀
胸部 松下 周ほか
肝胆膵 吉田耕太郎ほか
腎・泌尿器 八木文子ほか
女性生殖器 伊藤久尊ほか
まれであるが画像的特徴を有する骨軟部疾患 福田健志ほか
全身性疾患 中井雄大
特集2 検査の安全性・妥当性 企画・編集:山田 惠
序説 山田 惠
[検査の安全性・妥当性を担保するには?]
ミシガン大学編 永縄将太郎ほか
京都府立医科大学編 中井義知ほか
千葉大学編 向井宏樹ほか
弘前大学編 掛田伸吾ほか
札幌医科大学編 畠中正光
岡山大学病院編 児島克英ほか
鹿児島大学病院編 福倉良彦
ハンブルク・エッペンドルフ大学医療センター編 山村 仁
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
- 全文・
串刺検索 - 目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
- PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
- 南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:21.3MB以上(インストール時:45.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:85.3MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:21.3MB以上(インストール時:45.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:85.3MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784008004211
- ページ数:145頁
- 書籍発行日:2022年10月
- 電子版発売日:2022年10月18日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。