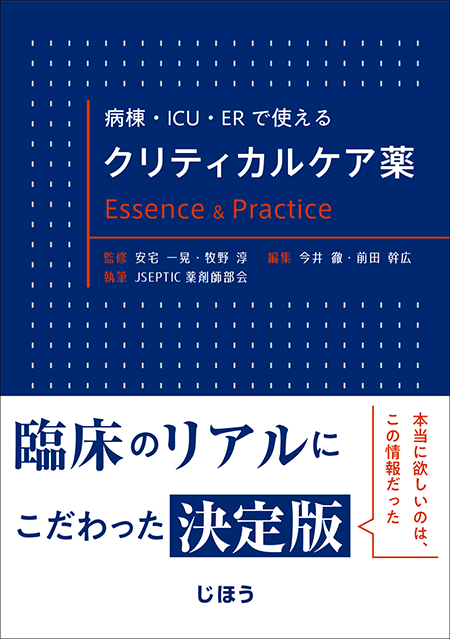- m3.com 電子書籍
- 病棟・ICU・ERで使える クリティカルケア薬 Essence & Practice
商品情報
内容
●重症患者の処方に関わる全ての医療者へ
●機能低下時、機器使用時、相互作用・副作用……現場が本当に欲しい情報を完全網羅
クリティカルケアで処方される頻用薬の使い方・押さえておくべきポイントを豊富なエビデンスに基づき網羅。医療機器使用時や機能低下時の使用方法・留意点など、本当に現場が求めている情報を臨床の目線にこだわってまとめました。重症患者に関わる全ての医療従事者におすすめです。一般病棟、ICU、ERを問わず、重症患者への適切な処方設計や副作用対応に実践的に活用できるほか、施設内の勉強会のテキストとしても使えます。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
監修のことば
クリティカルケアというと,人工呼吸器やECMO を始めとする多くの医療機器がまず頭に浮かぶ.これらの医療機器に関しては巷に多くの解説本や講習会がある.しかし,医療機器は各臓器機能の一部をサポートしているものであり,原因治療となる場合はそれほど多くない.反対に原因治療という面からクリティカルケアをみると,その中心には薬物療法がある.薬物療法は,その投与量やタイミングによって予後を大きく変化する.
一方,クリティカルケアでは対象が全臓器に及ぶので,特定の分野の薬物を知っていれば事足りるものではなく,すべての分野の薬物をクリティカルケアの側面から理解する必要がある.例えば,クリティカルケアの現場では患者が腎不全や肝不全に陥っていたり,さらに持続腎代替療法(CRRT)を実施しているために薬物代謝が変化する場合や,心停止や呼吸不全に対してECMO を開始したために分布容積が大きく変わってしまう場合もある.それぞれに投与回数や投与量の変更が必要であるが,その指針となるべきものが手元にないために,薬物動態や薬力学を調べるものの途中で挫折し,経験に基づく処方となることが多い.さらに,最近では免疫チェックポイント阻害薬のような新薬の開発,既存薬の適応拡大,ジェネリックの使用促進なども加わり,すべての薬物を使いこなすことは不可能である.世の中には薬物の解説本は沢山あるので,それらを参考にするものの,クリティカルケアの分野にターゲットをおいて書かれたものはほとんどなく,また,添付文書からの抜粋・要約にとどまるものが多く,現場では使いにくいと感じることが多い.
今回,本書ではクリティカルケアで働く薬剤師が現場で医師や看護師と協働していくなかで必要と思われる部分,実際の臨床で使える部分を強調した.全体の構成として,前半部分では,薬物を使用するうえで必要な基本的な知識をまとめ,クリティカルケアの治療と連結させながら解説し,後半部分では各薬剤の特徴と具体的な使用法をまとめた.クリティカルケアの臨床現場における疑問に答えるという点では画期的なものであると思う.クリティカルケアに携わるすべてのメディカルスタッフに必須のものが出来上がったと自負する.是非,多くの人に使っていただき,一人でも多くの患者を救命できることを切に願うものである.
2021年8月
奈良県総合医療センター 集中治療部 部長
安宅 一晃
監修のことば
救急・集中治療領域で使用されている薬剤の多くは,良くも悪くも患者の命へ直結する可能性を秘めている.救急・集中治療医は平時から同時並行で多くの患者診療へ従事しており,外来診察や診断検査,患者への病状説明,点滴挿入・気管挿管などの手技で忙殺されるために薬物療法へ費やす時間は限られている.そのため,忙しい中で起こりやすい薬物誤投与の防止や薬物療法の意思決定支援において薬剤師の果たす役割は大きい.
薬剤科からはよく,“ 〇〇先生,すでにご存じかもしれませんが×× 様の腎機能が悪化しており,△△の投与量は減らした方がよいかと思います” といった趣旨のご連絡を頂くことがあるが,正直なことを言えば,その情報へたどり着くまでの時間的余裕はなかったことが多い.そのため,日頃からこのような耳より情報はとても有り難く,薬剤師の方々には例え些細な事柄であっても遠慮せず積極的に報告をして欲しいと願っている.
また,医師は疾患や病状に応じた薬剤の選択まではできても,薬剤の適正投与量や投与間隔,薬物モニタリング,他剤との薬剤相互作用まではインプットできていないことがほとんどである.特に,救急・集中治療領域の患者の多くは多臓器障害を合併しており,薬剤投与は慎重に判断しなくてはならない.このような時,臨床現場に相談できる薬剤師がいてくれるととても心強い.近年は,集中治療医の先導するICU 多職種連携が推奨されるようになり,筆者の施設でもICU 専従薬剤師が薬物誤投与の防止をはじめ,薬物療法の意思決定支援,院内プロトコルへの遵守や院内オーダーセットの適正使用モニターなどへ積極的に関わり,院内医療安全へ貢献している.
さて,本書は救急・集中治療の臨床現場で医師をはじめ様々な医療スタッフから沸き上がってくる臨床疑問に対して答えられるような実践的な内容へ仕上げられている.臨床医学であるが故に未知の内容も多く存在はするものの,これまでの知見から現時点までに得られた最善のエビデンスが集約されており,読者の方々が本書を通じて多くのことを学んでいただけることを祈念している.
2021年8月
東京都立墨東病院 集中治療科 部長
牧野 淳
編集のことば
生命の危機的状況にある急性・重症患者に対して行われるクリティカルケアは,迅速かつ適切な全身管理が必要とされ,初期蘇生,人工呼吸管理,栄養管理などに加え,適切な薬物治療が重要となる.クリティカルケアにおいては,多臓器にわたり急速に増悪する病態を把握し,それに合わせた適切な薬物治療が必要となり,教科書的な画一的な知識では太刀打ちできないことをよく経験する.患者を救うためには,エビデンスに加え,基礎的知識とともによりエキスパートな薬物治療の理解が必須となる.
本書は救急治療,集中治療,周術期はもちろん一般病棟を含め,あらゆる治療の場に求められるクリティカルケアの薬物治療をまとめた書籍である.総論から各論まで1,000 ページを超えるボリュームとなったのは,本書1 冊を持つことで医療者の基礎的な知識の向上に加え,臨床の緊迫した現場でもすぐに調べられるようにと考えて意図した結果である.
総論は,各薬物治療の基本的な考え方や各薬剤の比較,注意すべきピットフォールなどを記載しており,初学者からエキスパートまでがじっくりと薬物治療を学ぶことができる内容となっている.各論は,薬剤の詳細な情報を記載しているが,忙しい臨床現場ですぐに使いやすいように,各項の先頭には必要最低限の情報を記載した簡易版を作成し,その後詳細な情報を調べられるように二段構えの構成とした.特徴は,第一線で活躍している薬剤師が中心になり執筆することで,臨床で実際に投与する時の調製法や効果発現・持続時間,副作用への対応やそのモニタリング方法など,他の類書ではあまり記載されていないクリティカルケアで重要なエッセンスを濃縮している点である.
エビデンスに基づいて,わかりやすくまとめられた本書は,クリティカルケアに関わる全医療スタッフにとって,大いに役立つ一冊に仕上がっている.また,医学部や薬学部の教育にも活用し,未来の医療従事者の育成にも役立てて欲しいと考えている.ぜひ多くの方が本書を手にし,クリティカルケアという荒波を乗り越えるための羅針盤になることを願っている.
2021年8月
日本大学医学部附属板橋病院 薬剤部
今井 徹
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部
前田 幹広
目次
Introduction クリティカルケアの流れと薬の位置付け
略語一覧
Ⅰ章 クリティカルケアでのアセスメントと薬物療法
1 集中治療
1 重症患者の薬物動態
2 器官系統別評価
3 バンドル
2 周術期
Ⅱ章 病態に応じた薬の選び方・使い方
1 機能低下時
薬物動態パラメータの変動要因からみた薬物の特徴づけ
1 侵襲時
2 心機能低下時
3 腎機能低下時
4 肝機能低下時
2 医療機器使用時
1 CRRT
2 IRRT
3 血漿交換療法
4 ECMO
Ⅲ章 クリティカルケアでの薬物相互作用
1 薬物相互作用の種類
2 クリニカルクエスチョンの考え方
Ⅳ章 クリティカルケアと副作用
1 クリティカルケアと副作用
2 薬剤性腎障害
3 薬剤性肝障害
4 血球減少
5 薬剤熱
6 薬剤性消化管障害
Ⅴ章 クリティカルケア薬物治療の必須ポイント
1 薬物血中濃度測定
2 頻用される計算式
3 配合変化
4 末梢ルートが適さない薬剤
5 フィルターを通さずに投与すべき薬剤
6 側管投与ルートの取り扱い
Ⅵ章 頻用薬 使いこなしのティップス
1 鎮痛薬
フェンタニル
レミフェンタニル
モルヒネ
ケタミン
ブプレノルフィン
ペンタゾシン
ロピバカイン
ナロキソン
フルルビプロフェン
トラマドール
ロキソプロフェン
アセトアミノフェン
2 鎮静薬
ミダゾラム
プロポフォール
デクスメデトミジン
フルマゼニル
3 筋弛緩薬
ロクロニウム
ベクロニウム
スキサメトニウム
スガマデクス
4 循環作動薬
アドレナリン
ドパミン
ノルアドレナリン
バソプレシン
ドブタミン
ミルリノン
オルプリノン
エフェドリン
フェニレフリン
5 血管拡張薬
ニトログリセリン
硝酸イソソルビド,一硝酸イソソルビド
ニコランジル
6 抗不整脈薬
リドカイン
ランジオロール
アミオダロン
ニフェカラント
ベラパミル
ジルチアゼム
ジゴキシン
デスラノシド
アデノシン三リン酸
7 抗凝固薬〈注射〉
未分画ヘパリン
低分子ヘパリン
アルガトロバン
ダナパロイド
8 抗凝固薬〈内服〉,抗血小板薬
アスピリン
クロピドグレル
プラスグレル
ワルファリン
エドキサバン
アピキサバン
リバーロキサバン
タビガトランエテキシラート
シロスタゾール
9 利尿薬
フロセミド
カンレノ酸カリウム
アゾセミド
トルバプタン
カルペリチド
10 血栓溶解薬
ウロキナーゼ
アルテプラーゼ
11 抗てんかん薬
ジアゼパム
ロラゼパム
ホスフェニトイン
レベチラセタム
ラコサミド
ペランパネル
フェノバルビタール
チオペンタール
バルプロ酸ナトリウム
カルバマゼピン
クロナゼパム
ゾニサミド
12 脳圧降下薬
グリセリン(グリセオール®)
マンニトール
13 止血薬
トラネキサム酸
カルバゾクロム
ビタミンK
プロトロンビン複合体
イダルシズマブ
14 胃酸分泌抑制薬
オメプラゾール
ファモチジン
15 副腎皮質ステロイド薬
ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム,ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム
プレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム,プレドニゾロン
メチルプレドニゾロン
デキサメタゾン
フルドロコルチゾン
16 喘息・COPD用薬
dl-イソプレナリン,サルブタモール,フェノテロール,プロカテロール,サルメテロール
イプラトロピウム,チオトロピウム
メチルプレドニゾロン
硫酸マグネシウム
アミノフィリン注,テオフィリン徐放錠
17 DIC用薬
アンチトロンビンⅢ
リコンビナント・ヒトトロンボモジュリン(rhTM)
18 抗精神病薬,抗うつ薬,睡眠薬
ラメルテオン
スボレキサント
ゾルピデム
抑肝散
クエチアピン
アリピプラゾール
ハロペリドール
リスペリドン
トラゾドン
ミルタザピン
19 輸液
20 電解質
ナトリウム
カリウム
リン
マグネシウム
カルシウム
21 血液製剤
アルブミン
ハプトグロビン
抗破傷風免疫グロブリン
人免疫グロブリン
22 アナフィラキシーショック用薬
アドレナリン(エピペン®)
グルカゴン
23 高カリウム血症用薬
カルシウム
炭酸水素ナトリウム
GI療法
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
ポリスチレンスルホン酸カルシウム
24 高血糖用薬
インスリン持続注射
エンパグリフロジン
シタグリプチン
25 肺高血圧症用薬
ベラプロスト
シルデナフィル
タダラフィル
ボセンタン
アンブリセンタン
エポプロステノール
26 ビタミン剤
アスコルビン酸
チアミン
カルニチン
パントテン酸
27 その他の注射薬
エダラボン
ファスジル
メシル酸ガベキサート
脂肪乳剤
ダントロレン
28 降圧薬
ニカルジピン
ジルチアゼム
ニトログリセリン
ニトロプルシドナトリウム
ヒドララジン
フェントラミン
プロプラノロール
アムロジピン
エナラプリル
アジルサルタン
29 脂質異常症用薬
ロスバスタチン
エゼチミブ
エボロクマブ
ベザフィブラート
30 抗菌薬
アンピシリン(ABPC)
アンピシリン/スルバクタム(ABPC/SBT)
ピペラシリン/タゾバクタム(PIPC/TAZ)
セファゾリン(CEZ)
セフトリアキソン(CTRX)
セフェピム(CFPM)
メロペネム(MEPM)
ドリペネム(DRPM)
バンコマイシン(VCM)
レボフロキサシン(LVFX)
アジスロマイシン(AZM)
薬剤索引(Ⅵ章)
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:27.4MB以上(インストール時:77.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:109.8MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:27.4MB以上(インストール時:77.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:109.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784840753814
- ページ数:1072頁
- 書籍発行日:2021年9月
- 電子版発売日:2021年11月8日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。