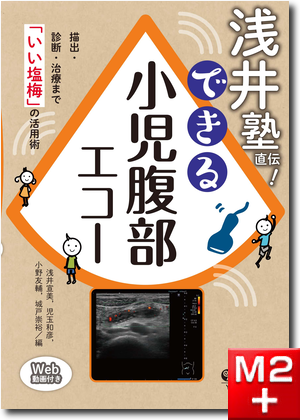- m3.com 電子書籍
- 児玉 和彦
- 浅井塾直伝!できる小児腹部エコー~描出・診断・治療まで「いい塩梅」の活用術
商品情報
内容
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序
私の超音波検査(エコー)人生は平成元年,都立大塚病院で望月幹彦先生に師事することからはじまりました.小児領域を本格化させたのは平成10年都立清瀬小児病院へ異動してからですので,もう20 年以上の月日が経ちました.浅井塾を立ち上げたのは当時の小児外科部長(後の病院長) 林奐先生から小児外科の若手スタッフに超音波診断技術を伝授してくれと依頼されたことがきっかけとなっています.「君から免許皆伝が出るまでは小児外科医単独でエコーはさせない」と言われたことは今でも鮮明に覚えております.清瀬の12年間は現在を語るうえできわめて重要な時間でありました.医局の大勢の先生方からたいへんお世話になりましたが,その中でも公私ともに多大なるご支援を賜ったのがまさしく私の人生哲学の師でもあります未熟児新生児科部長横山哲夫先生です.この紙面をお借りして心より御礼申し上げます.
近年,超音波診断装置の進化は凄まじく,画像診断として有用なスペックが次々と開発されました.具体的には体の深部がグレースケールで明瞭となり,ドプラで低流速の血流シグナルが正確に拾えるようになったことで,正確度の高いエコー診断が可能となりました.
ご存じのとおり,エコーは被曝がなく,非侵襲性でどの場所でもくり返し施行できる画像診断法です.検者の技量にもよりますが,多くの画像情報を得ることが可能で,当院では平日の診療時間にとどまらず,遠隔診療システムの導入で24時間365日いつでも対応しています.機動性にも優れているという利点から,小児領域では特に有用であることはすでに多くの方々に周知されていることと察します.
しかしながら,本来,画像診断法の第一選択であるべきエコーが成人領域と比べ,明らかに普及が停滞していることも既成事実のようです.
過去の日本超音波医学会のシンポジウムでもとり上げられましたが,小児エコーがいまだに発展途上である理由は何でしょう?
① 小児の発育変化:新生児から思春期の15歳までを小児領域とした場合,臓器は年齢とともに刻々と変化するため,検者は年齢相応の正常値と計測値との比較や,生理的変化(臓器の実質コントラストなど)を評価しなければならない.
② 小児では先天性疾患の占める割合が多い
③ 年齢による疾患頻度の違い:急性腹症のなかでも消化器疾患(腸回転異常,消化管閉鎖,腸重積症など)は年齢により中央値が異なる.
④ 成人に比して病勢の進行が速い小児科領域でエコーは治療方針に直結しうる重要な役割を果たしうるが,同時に迅速かつ的確なジャッジが求められるため,検者には大きなプレッシャーとなりうる(腰が引ける).
このような理由が,プローブを握ることに躊躇し,結果として小児エコーが第一選択として確立されていない大きな要因と考えられます.
本書を刊行するきっかけとなったのが,こだま小児科院長 児玉和彦先生との出会いでした.以前から私はエコーの走査技術および画像解析技術と身体診察所見をマッチさせて超音波診断技術を高めることはできないかを思案しておりました.同志である小野友輔先生,城戸崇裕先生からご快諾いただき,児玉先生に提議したしましたところ,ご賛同を得て本書を著するに至りました.
われわれはこれを「小児臨床超音波」とよび,身体診察所見をとり入れた手法が今後の小児腹部エコーの普及のカギとなることを確信しております.
エコーを実施する検者には以下の3 点の技術を有することが必須とされています.
①超音波機器の取り扱いに精通し,スペックを使いこなせること
②見落としなく臓器を走査すること
③記録された情報をレポートとして記載できること
では,実際,エコーはどこで学ぶのでしょうか?
残念ながら「独習」による技術習得はきわめて困難と思われます.
腹部エコーと言ってもカテゴリーは広く,対応する診療科は消化器科,腎臓内科,外科,泌尿器科,血液腫瘍科,新生児科など多岐にわたります.
したがって,小児腹部エコー技術を研鑽するためには,
① 日常的にエコーが行われており,多くの症例を一定期間に集中して経験できる.
② エコーの画像解析を専門的に行い,施行者にフィードバックされるシステムが構築されている.
③ 患児およびご家族を不安にさせないために,常にコミュニケーションをとり,安心感を担保できる指導者がいる
という環境であれば理想的と思われます.
手前味噌になりますが,茨城県立こども病院は前述の条件をすべて満たしています.現在では,3カ月間の集中エコー研修で浅井塾免許皆伝取得が可能となっています.また,定期的に開催しております茨城こどもECHO ゼミナールにもぜひご参加ください.
本書は小児エコーに精通した小児医療関係者が一人でも多く輩出されることを願い,ユーモラスな表現をふんだんに盛り込み,病態生理や身体診察所見を視点の中心とした構成となっています.したがって,既刊の成書とはかなり異なったイメージを抱かれるのではないかと少しばかり危惧しておりますが,小児科の先生方をはじめ,エコーに従事される技師の皆様にはこれまでにない一歩踏み込んだエコーを施行し,結果をフィードバックしていただくことを切に願っております.
本書を刊行するにあたり,推薦の辞をいただきました茨城県立こども病院長 須磨﨑亮先生,茨城県立こども病院名誉院長 圡田昌宏先生に感謝の意を,格別のご配慮を賜りました羊土社編集部の皆様にはこの場をお借りしまして厚く御礼申し上げます.
2021年9月
茨城県立こども病院 小児超音波診断・研修センター
浅井宣美
目次
● 推薦の言葉/圡田昌宏
● 推薦の言葉 ~小児診療における超音波診断の将来像~/須磨﨑 亮
● 序/浅井宣美
● 動画視聴ページのご案内
入門編:小児超音波の基本のキ!
1. なぜ,小児臨床超音波なのか 〜病歴と身体診察と浅井塾流小児臨床超音波〜/児玉和彦
2.超音波装置の基礎/田口 明
3.“どんな手を使ってでも情報をとる” 小児超音波検査/小野友輔
4.急性腹症における臨床エコー/東間未来,浅井宣美
初級編:正常像の描出のポイントと異常像との違い/城戸崇裕
1.肝臓のエコーって,何を見るんですか? サイズ?
2.腎臓の計測を毎回行うのはなぜですか?
3.虫垂炎って,どうしたら否定できるんですか?
4.子どもの胆道系が正常,と言うのは,難しいですか?
5.脾臓のエコーって,何を見るんですか?
中級編:患者さんの主訴から診断に迫る臨床超音波!/小野友輔,児玉和彦
1.おなかが痛い!と言えない乳幼児の腹痛!? 〜エコーはどうしたらいいのですか?〜
2.学童期以降の腹痛で危ないものを見逃さないコツを教えてください!
3.緊急事態!?新生児・乳児の嘔吐
4.おっと!嘔吐!幼児・学童期の嘔吐!
上級編:浅井塾長の臨床超音波!実践指導!
1.発熱・尿路感染症/出澤洋人,浅井宣美
2.急性陰嚢症/浅井宣美,児玉和彦,貴達俊徳,矢内俊裕
3.消化管出血をきたす疾患に対するエコー検査/弘野浩司
4. 腸回転異常症 〜年齢的にありえないと思っていると見落とす症例〜/浅井宣美,本間利生
ホットトピック
1.高安動脈炎 〜正常な景色を知っていないと診断できない症例〜/河合 慧
2.肺エコーについて/星野雄介
● あとがき 〜超音波教育の未来〜/浅井宣美
● 索引
Column
小児超音波物語
①エコー中の会話が重要/小野友輔
②全然関係ないのですが…~/小野友輔
③ IgA 血管炎のピットフォール~目に見えるものがすべてではない~/小野友輔
④どんな手を使ってでも情報をとる,おさらい/小野友輔
⑤腎臓を見張る/小野友輔
⑥炎症性腸疾患は診断に苦慮する場合が…/小野友輔
⑦目稽古/小野友輔
⑧子どもはすべて診させていただく/小野友輔
⑨チーム医療,そしてエコーを行うときの心構え/小野友輔
⑩ピットフォール,細菌性腸炎? 虫垂炎?/小野友輔
⑪ピットフォール,1カ月前からの嘔気で紹介.診断は?/小野友輔
ピットフォール
①ウイルス性腸炎と思いきや…/小野友輔
②腸重積症もどき??/小野友輔
③下痢で紹介なのに便秘?/小野友輔
④右下腹部痛イコール虫垂炎?!/小野友輔
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:18.2MB以上(インストール時:40.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:72.9MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:18.2MB以上(インストール時:40.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:72.9MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784758123815
- ページ数:224頁
- 書籍発行日:2021年10月
- 電子版発売日:2021年11月10日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。