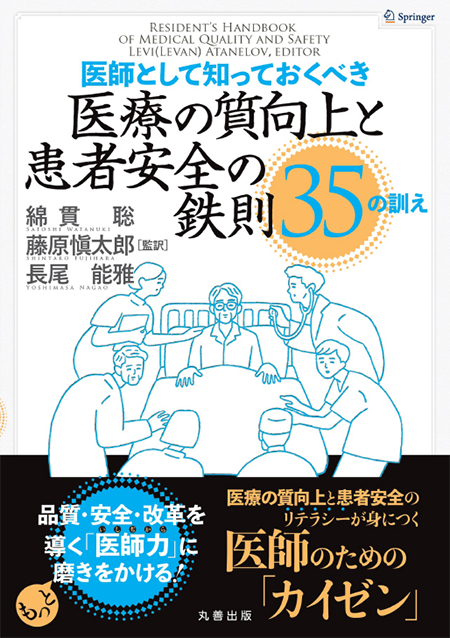- m3.com 電子書籍
- 丸善出版
- 医師として知っておくべき 医療の質向上と患者安全の鉄則 35の訓え
商品情報
内容
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
監訳者序文
本原書『Resident’s Handbook of Medical Quality and Safety』と出会ったのは,2016 年夏にバルセロナで開催された欧州医学教育学会(Association for Medical Education inEurope:AMEE)学術総会でのブックコーナーである.その後,私自身は診断エラー(diagnostic error)という概念を掘り下げる中で診断エラーの要因分析をする手法1)として,fishbone diagram(特性要因図)と出会った.その際に特性要因図は工業製品等の品質管理に取り組むためのツールであり,1962 年に日本の品質管理の礎を築いた石川馨氏が開発されたと知り,医療の質向上の文化が日本に発祥していることに誇りを抱いたことをよく覚えている.
その後,医療の質向上・患者安全を学ぶことの重要性を感じた私は,名古屋大学で安田あゆ子先生(現:藤田医科大学医療の質・安全対策部)・長尾能雅先生が主体となって開催されていた「明日の医療の質向上をリードする医師養成プログラム(ASUISHI)」に2018 年に参加する機会を得た.ASUISHI プログラム2)は医療事故防止のために,トヨタグループの品質管理部門と名古屋大学の患者安全部門が提携し,全国規模での「臨床を熟知し,現場の多様な課題を粘り強く解決する能力に長け,質管理の視点やスキルを併せ持つ医師の養成」を目的として創設されたコースである.
このコースの中で,私自身も病院の課題に向き合い,藤原愼太郎先生・安田先生のご指導のもとで特性要因図を作成し,真因分析を行い,A3 報告書の作成も行った.この過程を通じて,私は自分の無力さを痛感することとなった.また,それまでは問題が発見された場合に,要因が複数あることに思いを馳せることができず,問題の目の前にいた個人に大きな原因があると訝しみ,打ち手(対策実行)を場当たり的に行っていた自らの過去を振り返ることになった.
ASUISHI プログラムを通じて,現場に足を運び現状把握を行い,要因分析を行ったうえで効果と実行可能性を考慮しつつ,対策立案,実行へつなげていくこと〔PDCA サイクル:Plan(計画),Do(実行),Check(確認),Act(改善)〕の大切さとともに,標準化と管理の定着〔SDCA サイクル:Standardize(標準化),Do(実行),Check(評価),Action(処置・改善)〕を両輪として走らせることの大切さを学んだ.これは私自身が実際に院内で診療部門や医療安全対策室での活動を行う際,また日本において診断エラーに関する考え方3)を啓蒙するにあたっての基本軸になっている.
本原書は,レジデントが医療現場で医療の質向上プロジェクトを実践するための入門書として2016 年に刊行された.日本の初期臨床研修では義務化されていないが,米国でのレジデントプログラムではACGME(米国卒後医学教育認定評議会)の指定に準じて医療の質向上プロジェクトを実施することが求められている.また,本原書はジョンズ・ホプキンス大学のLevan Atanelov 氏が中心となって編集され,医療の質向上プロジェクトの実施に必要な基本ツールの解説(特性要因図やトヨタの品質管理の歴史などにも触れられている)とともに,医療の質向上プロジェクトの実際の計画,失敗過程なども示されている.
本書は本来医師向けに作成されているが,医師以外の多くの臨床家の実践記録が含まれており,日本において医療の質向上に取り組む機会の多い看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,薬剤師などの職種の方々にとっても有用な内容が数多く含まれている.本書を医療の質向上プロジェクトを始めるにあたっての足がかりとして活用し,組織の中で仲間を求め,チームを形成し,医療の質向上・患者安全に高い関心をもって取り組む医療職が増えることを期待してやまない.
本書の翻訳にあたり,長尾先生,ASUISHI 卒業生をはじめとする日本の質改善・患者安全の現場で活躍されている多くの方々の協力をいただいた.また,本分野に習熟の浅い私にとって,品質改善の専門家である藤原先生から数多くのアドバイスをいただき,本書の翻訳の質の向上において多大な貢献をいただいた.刊行にあたっては,丸善出版(株)の堀内志保氏,程田靖弘氏に多大なサポートをいただいた.そして最後に,私の日々を支えてくれている家族,職場の方々,皆さんの協力なしにこの書籍の翻訳はなしえなかった.この場を借りて感謝を申し上げたい.
2021年6月吉日
監訳者を代表して
綿貫 聡
目次
第1部 医療の質向上と患者安全でのストロングポイント
1章 医療の質向上の基本用語を学ぼう
2章 米国における医療の質向上と患者安全の歴史を学ぼう
3章 連邦航空局での安全に関するリスクマネジメントの原則を学ぼう
4章 医療の質向上と研究にヒューマンファクターエンジニアリングを活用しよう
5章 臨床での医療情報学と電子カルテの役割を学ぼう
第2部 レジデントプログラム責任者目線と経営者目線でのストロングポイント
6章 医療の質向上にレジデントにも参加してもらおう:未来への投資
7章 レジデントプログラム責任者も患者安全と医療の質向上に関心をもとう
8章 患者安全の質協議会の活動にレジデントを巻き込もう
第3部 実際の医療の質向上プロジェクトでのストロングポイント
9章 入院患者の早期離床を促進する
10章 音声録音を活用して循環器病棟の退院時コミュニケーションを改善する
11章 妊娠中と出産後の禁煙を促進し,維持する
12章 ステロイド静注治療後の多発性硬化症患者の早期退院を促進する
13章 ワクチン接種の中核指標における遵守率を向上させる
14章 ICUでの早期リハビリテーション実施により患者転帰を改善させる
15章 急性期医療でのリハビリテーション内容のばらつきを減らす
16章 CAUTIプロジェクトを通じて医療の質を向上させる:看護学的アプローチ
17章 緊急投薬の遅れを減らす:多職種連携アプローチ
第4部 学術論文の評価と出版でのストロングポイント
18章 論文を執筆するには何が必要か:俯瞰して全体像を描こう
19章 効果的な文献検索をしよう
20章 エビデンスの評価,批判的吟味,執筆,出版のための情報源を活用しよう
21章 学術論文を読み解くための基本原則を学ぼう
第5部 医療の質向上を目的とした対策でのストロングポイント
22章 医療の質向上のためにグループでアイデアを創出しよう
23章 プロジェクトの対象範囲を設定しよう
24章 プロジェクトを選択し,対象範囲を設定しよう
25章 医療におけるコミュニケーションツールを活用しよう:基礎的なこと
26章 プロジェクトマネジメントをツールで見える化しよう:基礎的なこと
27章 医療現場で効果的なチームマネジメントを行おう:基礎的なこと
28章 実践的な医療の質向上ツールを活用しよう
29章 医療の質向上ツールを導入しよう
30章 リーンシグマを医療現場に応用しよう
第6部 医療の質向上に向けた技術的側面でのストロングポイント
31章 疫学の基礎を学び,疫学ツールを患者安全と医療の質向上に応用しよう
32章 医療の質向上のためのデータ分析の基礎を学ぼう
33章 調査の方法を学ぼう
34章 統計解析ソフトRを活用しよう:初学者のための手引き
35章 原書正誤表
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:12.0MB以上(インストール時:29.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:47.9MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:12.0MB以上(インストール時:29.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:47.9MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784621306437
- ページ数:338頁
- 書籍発行日:2021年11月
- 電子版発売日:2022年5月1日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。