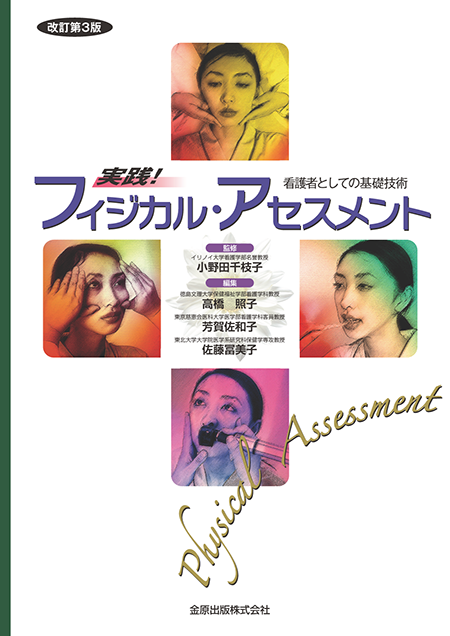- m3.com 電子書籍
- 芳賀 佐和子
- 実践!フィジカル・アセスメント 改訂第3版
商品情報
内容
1. 本書で取り上げているフィジカル・アセスメント技術の対象年齢は、「10歳以上」であるが、高齢者に関するアセスメントについて多くの質問がよせられたため、高齢者に関するアセスメントについて大幅に加筆した。
2. 第III章「フィジカル・アセスメントの実際」では、ページのスタイルを変更し、「チェックポイントと判断のめやす」の項目を新たに立て、アセスメントの結果をどのように判断するかという視点を強化した。
3. 学生や現任者がフィジカル・アセスメント技術を身につけやすくするためのサポートとして、第IV章「フィジカル・アセスメントのスキルアップ情報」を新設した。内容は、フィジカル・アセスメントを学ぶために必要な、ベーシックな解剖学的知識を自分の身体で再確認する楽しいドリル『事前学習課題』とスキルアップを助ける『技術習得のための教材例』である。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
刊行によせて
今日のヘルスケア領域において,看護が有効に機能した理想的な医療を展開するためには,看護者に求められる役割も大きく変化しています。
日進月歩の科学知識,医療技術など新しい情報を常に把握するよう努めるのはもちろんですが,それに加え求められているのは専門職としての判断力です。
言うまでもなく,患者をアセスメントするということは,すべての看護者にとって大切な責務のひとつです。いかなる状況においても,患者の問題を明らかにし,分析(診断)を行い,対処方法を決め,個別的な看護ケアを計画・実施・評価するという流れのなかで,まず基本となるのは患者のアセスメントです。
この患者のデータ収集で最も重要なのは,フィジカル・アセスメントを行い,身体的・生理学的な問題を明らかにすることです。視診,触診,打診,聴診など,的確な技術と鋭い観察によって,看護ケアのための総合的データを得ることができるのです。
かつては患者の血圧測定も,医師のみによって行われていました。時を経て,現在では血圧測定はもちろん,各種のモニタを監視し,耳鏡や検眼鏡のような複雑で精巧な医療機具を駆使するまで看護の実践範囲は拡大しました。また,これまでは血圧測定や心尖脈測定のためだけに用いていた聴診器を使って,正常な呼吸音と肺雑音,正常な心音と心雑音を聴き分けるのも看護者にとって一般的な技術になってきました。臨床の場ではもちろん,在宅看護においても,こうしたアセスメント能力が必要とされます。
このように,時代が要請する専門職としての役割を遂行するために,看護者は十分な準備をしなければなりません。本書に書かれているフィジカル・アセスメント技術を学び,これを実践し,マスターすることで,看護専門職への要請に自信をもって応えられるようになるはずです。
イリノイ大学看護学部名誉教授
小野田千枝子
改訂第3版のポイント
1998年に本書の第1版が発行されてから10年が経過しました。その間にフィジカル・アセスメントに関する教育や看護実践において,大きな変化が起きています。教育場面では看護基礎教育にフィジカル・アセスメントが取り入れられ,教育内容精選に関しての検討がすすめられています。
また,訪問看護の領域では実践場面に積極的にフィジカル・アセスメントを導入する努力が見られます。
2007年には看護基礎教育のカキュラム改訂が行われ,基礎看護学の学習に「フィジカル・アセスメントを強化する内容とする」と明記されました。
このような看護界の変化や読者の声を取り入れ,次の点に留意し改訂を進めました。
①本書で取り上げているフィジカル・アセスメント技術の対象年齢は,「10歳以上」ですが,高齢者に関するアセスメントについて多くの質問が寄せられたため,高齢者に関するアセスメントについて大幅に加筆しました。
②第Ⅲ章「フィジカル・アセスメントの実際」では,ページのスタイルを変更し,「チェックポイントと判断のめやす」の項目を新たに立て,アセスメントの結果をどのように判断するかという視点を強化しました。
③学生や現任者がフィジカル・アセスメント技術を身につけやすくするためのサポートとして,第Ⅳ章「フィジカル・アセスメントのスキルアップ情報」を新設しました。内容は,フィジカル・アセスメントを学ぶために必要な,ベーシックな解剖学的知識を自分の身体で再確認する楽しいドリル『事前学習課題』とスキルアップを助ける『技術習得のための教材例』です。
看護者ひとり一人が看護の専門性を確立する技術の一つとしてフィジカル・アセスメントの技術を学び看護実践にいかしていけるように執筆者一同,願っています。
芳賀佐和子
目次
I. 看護におけるフィジカル・アセスメント
1. フィジカル・アセスメントとは
2. 看護のためのフィジカル・アセスメント
3. フィジカルアセスメント技術の修得
II. フィジカル・アセスメントに共通する技術
1. フィジカル・アセスメントの準備
2. フィジカル・アセスメントの4つの基本技術
3. フィジカル・アセスメントの開始から終了までの時間とアセスメントの進め方
"診断セット"について
III. フィジカル・アセスメントの実際
1.健康歴の聴取:系統的レビュー
一般状態
皮膚・爪
頭頚部
眼
耳
呼吸器
心臓・血管系
乳房・腋窩
腹部
筋・骨格
神経系
2.一般状態のアセスメント
身体的側面
バイタルサイン
生活習慣
記録例(正常)
血圧分類
アセスメントの根拠
3.皮膚・爪のアセスメント
皮膚
爪
記録例(正常)
アセスメントの根拠
4.頭頚部のアセスメント
頭部
頭蓋
頭皮
頭髪
副鼻腔
顔
側頭下顎関節
第V脳神経(三叉神経)
第IIV脳神経(顔面神経)
鼻
外観
内部構造
第I脳神経(嗅覚神経)
口腔
口唇
口腔内
第IX・X脳神経(舌咽・迷走神経)
第XII脳神経(舌下神経)
首
外観
気管
甲状腺
頚静脈拍動
リンパ節
頚椎可動域
第XI脳神経(副神経)
記録例(正常)
前顎洞,上顎洞の誤りやすい触診方法
脳12神経のアセスメント方法
アセスメントの根拠
5.眼のアセスメント
視神経(第II脳神経)
外眼筋機能(第III、IV、VI脳神経)
外観
眼瞼
涙液気管
眼瞼粘膜
虹彩
角膜、前眼房
強膜、レンズ
瞳孔
瞳孔反射(第III脳神経)
網膜
記録例(正常)
アセスメントの根拠
6.耳のアセスメント
聴神経(第VIII脳神経)
外観
外耳,外耳道
記録例(正常)
音叉による聴力のアセスメント
アセスメントの根拠
7.呼吸器のアセスメント
呼吸器の聴診における聴診器の使い方
打診法(右利きの場合)
胸部形態と外観
胸郭
肋骨
呼吸
胸郭の拡張
肺
振盪音
打診音
横隔膜
呼吸音
声音伝導
記録例(正常)
アセスメントの根拠
8.心臓・血管系のアセスメント
心音聴診時の聴診器の使い方
脈拍を触診する場合のポイント
胸部の外観
頚静脈
動脈
振動(スリル)
最大拍動点
心音
記録例(正常)
アセスメントの根拠
9.乳房・腋窩のアセスメント
乳房
乳房(男性)
腋窩
記録例(正常)
アセスメントの根拠
10.腹部のアセスメント
腹部全体
動脈
腸管
肝臓
脾臓
腎臓
記録例(正常)
腹部の異常が疑われる場合のアセスメント
アセスメントの根拠
11.筋・骨格のアセスメント
関節の状態
関節可動域
関節
すべての関節に共通
手指の関節
橈骨手根関節
肘関節
肩関節
胸・腰椎
股関節
膝関節
足関節および足部
四肢の筋力
全身
手指
手首
前腕部
上腕部
下肢
四肢測定時の基準点
脊柱および下肢の形態と歩行
脊柱の形態
下肢の形態
歩行
記録例(正常)
アセスメントの根拠
12.神経系のアセスメント
打腱器
音叉
深部腱反射
上腕二頭筋反射
上腕三頭筋反射
膝蓋腱反射
アキレス腱反射
橈骨腱反射(補助的に行う)
表在反射
腹壁反射(上方)
腹壁反射(下方)
病的反射
足底反射におけるバビンスキー反射
クローヌス
表在知覚
温度覚
触覚
深部知覚
振動覚
深部痛覚
位置覚
ロンベルグ試験
複合知覚立体認知
書画感覚
二点識別覚
小脳機能
指鼻試験
指指試験
拮抗反復運動
指先の細かな動き
手指足指試験
踵 −すね試験
8の字試験
記録例(正常)
反射アセスメントの誤りやすい方法
アセスメントの根拠
IV. フィジカル・アセスメントのスキルアップ情報
1.事前学習課題
皮膚・爪
頭頸部
眼
耳
呼吸器
心臓・血管系
乳房・腋窩
腹部
筋・骨格
神経系
2.技術習得のための教材例
付
付・記録用紙
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:13.5MB以上(インストール時:30.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:54.0MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:13.5MB以上(インストール時:30.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:54.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784307701884
- ページ数:194頁
- 書籍発行日:2008年3月
- 電子版発売日:2023年1月25日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。