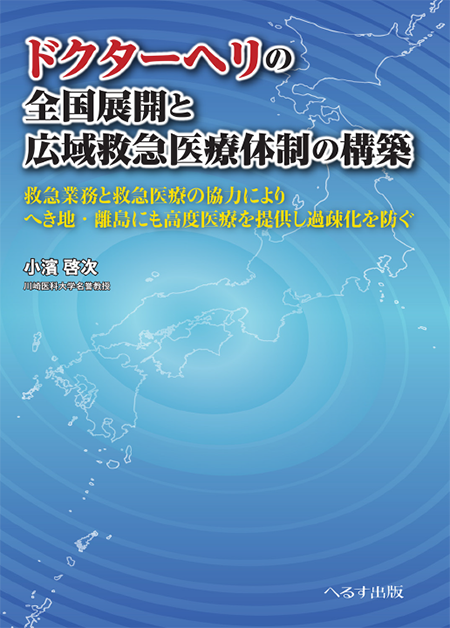- m3.com 電子書籍
- へるす出版
- ドクターヘリの全国展開と広域救急医療体制の構築;救急業務と救急医療の協力によりへき地・離島にも高度医療を提供し過疎化を防ぐ
商品情報
内容
ドクターヘリの歴史を読み解き、これからの救急医療を展望する
ドクターヘリの誕生にかかわった著者だからこそ語れる秘話
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
はじめに
川崎医科大学を定年退職して20年近くになり,定年退職後も著者が創設した学会(日本臨床救急医学会,日本航空医療学会,日本病院前救急診療医学会,へき地・離島救急医療学会,岡山救急医療研究会)を中心に学会活動を続けてきたが,特に日本航空医療学会では,多くの関係者の皆様に大変お世話になった。そのためにお世話になった内容について述べ,感謝の気持ちを表したいと思い,また,へき地・離島にも高度医療を均等に提供するために,ヘリコプターを用いた「広域救急医療体制」を構築して,「均等な高度医療をへき地・離島の皆様にも提供して,過疎化を防ぐ」という著者の当初の願いを記録し,今後のさらなる発展の資料として残すために,今回著者の願いであった表記の題名で本書を上梓することにした。またこの機会に,救急医学専門医としての長年の思いと方策も同時に表現できればと思い,本書で述べさせていただいた。ご一読願えればと思うのである。結果としては,内容が分散した感があるが,救急医学,救急医療を専門としている方々には,ご理解いただけると思うのである。
本書では,著者が最初にドクターヘリを導入するに至った意図と経過を「ドクターヘリの歴史」として示し,そのなかでも特にドクターヘリを運航するためにはどうしても必要であった国としてのドクターヘリの法律の作成と,これも事故現場,災害現場に医師を送り出すためにどうしても必要であった航空法施行規則第176条(捜索又は救助のための特例)にドクターヘリを加えるために,運輸省(現国土交通省),厚生省(現厚生労働省),総務省消防庁と一般社団法人日本航空医療学会,認定NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)とのやりとりがいかに大変だったかについて述べ,ドクターヘリが国民の命を守るために導入された経過が,いかに厳しい状況にあったかを記録として残し,元公人である冨永誠美氏(元警察庁初代交通局長),国松孝次氏(元警察庁長官),篠田伸夫氏(元自治省消防庁次長)の御三方のおかげであることを,医療人として感謝したいと思ったのである。
わが国のドクターヘリは,国が創設して全国に拡げたのではなく,(社)日本交通科学協議会副会長の冨永誠美氏が,1970(昭和45)年頃,交通事故による死亡者が今に2万人になるとして社会問題になっていたとき,ドイツのADAC(ドイツ自動車連盟)で行われていた救急医療用ヘリコプターに医師を搭乗させて事故現場で救命治療を施し死亡者を減少させていることに習い,川崎医科大学の川崎祐宣初代理事長に会い,ドクターヘリの実用化研究を5回にわたって行ったことから始まるのである。この実用化研究で,重症傷病者の救命率の向上と予後の改善が得られることが実証され,これを知って,内閣官房内閣内政審議室の調査検討委員会は,厚生省にドクターヘリ試行的事業として,冨永氏が研究事業として行った同じ方法で,その効果を再検討し,同じ効果が得られたとして,救急医療用ヘリコプター(ドクターヘリ)の導入を厚生省が行うことを認めたことによって,ドクターヘリの運航が,厚生省の管轄で行われるようになったのである。その第1号が川崎医科大学附属病院救命救急センターに,20年後の2001(平成13)年4月1日に配備されたのである。
このとき厚生省は,全国に30か所配備するとしたのであるが,5年経過しても7か所の都道府県からしか,ドクターヘリ配備の要請がなかったのである。それも,本当にドクターヘリが必要な道府県からの要請がなかったのである。これを知ったHEM-Net 理事長の国松孝次氏は,ドクターヘリがなぜ必要か,またドクターヘリとは何かが理解されていないとして,ドクターヘリについての報告書やHEM-Net グラフを発刊して,ドクターヘリの必要性を公的に認めてもらい,さらには国の法律をつくらなければ,全国にドクターヘリが拡がらないとして,国としてのドクターヘリの法律の作成に努力された。また副理事長の篠田伸夫氏が,総務省と交渉することによって,財力のない都道府県に地方交付税処置,または特別交付税措置で,1機目は全額,2機目は8割を総務省が負担してくれるようになったのである。これらのことによって,多くの都道府県がドクターヘリを導入することになったのである。2022(令和4)年に,香川県にドクターヘリが導入されたことによって,京都府以外の全国の都道府県に,ドクターヘリが導入されたのである。
著者が川崎医科大学に呼ばれたのは,川崎学園の初代理事長で病院長も兼務されていた川崎祐宣先生が,大学病院経営のために救急部を開設しようとしたところ,全科の教授が反対して開設できなかったので,当時,学長をされていた水野祥太郎先生(元大阪大学医学部整形外科教授・大阪大学医学部特殊救急部の初代部長も兼務)に相談したところ,大阪大学には,救急診療が専門の医師がいるとの話を聞き,川崎理事長がその救急専門医を川崎医科大学にぜひ呼んで欲しいと要望されたので,水野学長より著者の恩師である恩地教授に救急専門医を紹介して欲しいとの話があり,恩地教授が著者に川崎医科大学へ行くように命令されたのである。著者は,大阪大学医学部麻酔学講座の大学院生であったが,特殊救急部が開設されてからは,救急専門医として最初から特殊救急部に勤務し,大学院修了後は1年間アメリカのユタ大学メディカルセンターに留学し,その後に兵庫県立西宮病院交通災害医療センター(現救命救急センター)に5年間外傷外科学の専門医として勤務していたのである。
詳細は省略するが,川崎医科大学に就職した翌年の1976(昭和51)年4月1日に,理事長名(病院長名)で全科24時間体制の救急部を北米型のER(振り分け外来)として開設した。また1977(昭和52)年1月1日付で,救急部がわが国最初の救急医学講座として文部省から認められたので,医師も教授1名,助教授1名,講師3名が正式の職員として認められた(川崎医科大学には助手〔助教〕の定員はなかった)。大学院生の採用と救急医学専門の研修医も認められた。他科の専門医学と同様の救急医学の講座が,川崎医科大学に完成したのである。
その後,1979(昭和54)年に救命救急センターを誘致し,外傷外科学(Traumatology),救命治療医学(Critical Care Medicine)をICU 10床,HCU 4床,一般病床32床で開始したのである。他科に迷惑がかからないように,救急医学講座でできる範囲の救急診療を行ったので病院(救急医学)の収益が増え,救命救急センターに第2講座の開設を認めてくれ,藤井千穂助教授が第2講座の教授になったのである。
詳細は本文中で述べるが,川崎医科大学附属病院で,岡山県で唯一の救命救急センター開始されたことによって,県北の過疎地から重症傷病者が,長距離を長時間かけて救急車で搬送されることになった(搬送時間として最低2時間は必要であった)。その搬送途上で心肺停止となる傷病者が意外に多かったので,救急専門医としてなんとかしなければならないと思っていたときに,(社)日本交通科学協議会の副会長をされていた冨永誠美氏が川崎祐宣理事長に面会に来られ,今でいうドクターヘリの創設を提言されたのである。このことは,著者が搬送途上の心肺停止傷病者をなんとかしなければならないと思っていたこととも重なり,ドクターヘリの実現につながったのである。
今後は,消防機関と医療機関が協力して病院前救護体制を充実させることが,わが国にとって最も必要と考えられるので,著者はこれまでの経過を明確にして,救急医療のみならず,へき地・離島の医療改革,特に重症傷病者の救命率の向上,予後の改善に役立てばと思い,本書を上梓することにしたのである。重症疾患の救命のためには,ドクターヘリ,ドクターカーを全国に消防機関と協力して配備し,都道府県単位で対応できるシステムを構築して,新しい救命のための広域救急医療体制を構築する必要があると考えている。
令和5(2023)年1月28日
ドクターヘリ発祥の地:岡山県倉敷市にて
川崎医科大学名誉教授(救急医学)
日本救急医学会名誉会員
日本臨床救急医学会名誉会員(元理事長)
日本航空医療学会監事・名誉理事長
日本病院前救急診療医学会監事(元理事長)
へき地・離島救急診療医学会監事(元代表世話人)
認定NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)副理事長
小濱 啓次
目次
第1章 ドクターヘリの歴史
I.総論
1 救急医療用ヘリコプターの実用化研究
2 ヘリコプターの救急医療への活用
3 救急業務と救急救命士の特定行為について
4 大学病院における総合救急診療体制構築の必要性
5 救急医学講座の誕生
6 新しい病院前救急医療体制の構築
①医師が救急業務に関与することの重要性
②阪神・淡路大震災の発生と厚生省予算の復活
③へき地にもドクターヘリが必要
7 ドクターヘリ導入のための協力者
8 広域救急医療体制構築の必要性
Ⅱ.各論
1 1980(昭和55)年以前における救急医療用ヘリコプターの運航について
2 1980(昭和55)年以降における救急医療用ヘリコプターの運航について
3 ドクターヘリ運航に関係した団体等
①社団法人日本交通科学協議会(現一般社団法人日本交通科学学会
②認定NPO 法人救急ヘリ病院ネットワーク(HEM-Net)
③一般社団法人日本航空医療学会
④内閣官房内閣内政審議室
⑤厚生労働省
⑥川崎医科大学
⑦日本病院前救急診療医学会
⑧へき地・離島救急医療学会
⑨総務省消防庁
⑩国土庁
⑪警察庁長官官房交通安全対策室
⑫関西広域連合
⑬浜松救急医学研究会と浜松救急医療用ヘリコプター株式会社
⑭メディカルウィング(医療優先固定翌機)研究運航事業
⑮ D-call Net(救急自動通報システム)
⑯国際航空医療協議会(International Aeromedical Evacuation Congress;AIRMED)
⑰ドクターヘリ基地病院連絡調整協議会
まとめ
Ⅲ.ドクターヘリ創設の流れ
第2章 ドクターヘリ運航に関連する法律,指針,通知,見解について
I.総論
Ⅱ.各論
1 航空法と航空法施行規則
①航空法
②航空法施行規則
2 ドクターヘリのための新しい国の法律の制定,公布,施行
①救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
②ドクターヘリ特別措置法の制定とその意義
③ドクターヘリ特別措置法成立の経過①
④ドクターヘリ特別措置法成立の経過②(日本航空医療学会発表による)
3 航空法施行規則第176 条の改正の必要性
①救急現場にドクターヘリを導入するための航空法施行規則第176 条の改正について
② 3 省庁合意のドクターヘリの出動について
③ 3 省庁合意へのドクターヘリの出動についてへの回答(HEM-Net,日本航空医療学会)
④日本航空医療学会としての3 省庁へのお願い
⑤東日本大震災の発生と航空法施行規則第176 条の改正
4 航空法施行規則第176 条の改正によるドクターヘリの運航
①厚生労働省による航空法施行規則第176 条の改正に伴うドクターヘリの運航について
②厚生労働省指導課長通知に対する日本航空医療学会安全推進委員会見解
③航空法施行規則第176 条改正の経過①
④航空法施行規則第176 条改正の経過②
⑤航空法施行規則第176 条改正の経過③
まとめ
おわりに
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:8.8MB以上(インストール時:22.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:35.3MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:8.8MB以上(インストール時:22.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:35.3MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784867190654
- ページ数:152頁
- 書籍発行日:2023年3月
- 電子版発売日:2023年3月31日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。