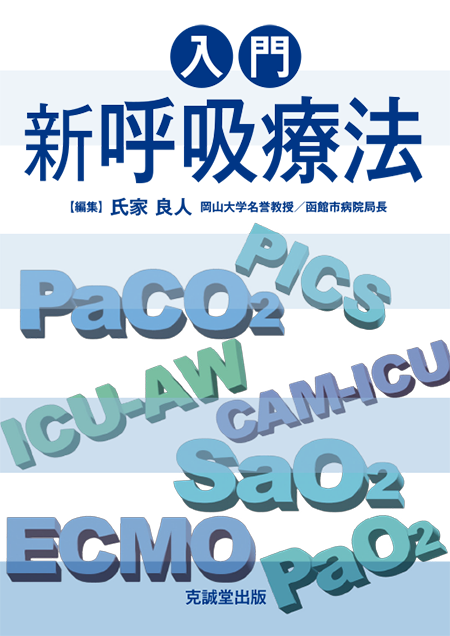- m3.com 電子書籍
- 克誠堂出版
- 入門 新呼吸療法
商品情報
内容
さらには、いまやチーム医療となった呼吸療法は、呼吸療法に携わる医療者にも学んでいただきたい入門書である。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序文
呼吸はヒトの生命活動において、最も重要で最も優先されなければならない機能である。誕生により母体を離れてから、ヒトは起きているときも寝ているときも休みなく呼吸を繰り返し、酸素を摂取し二酸化炭素を排泄し、エネルギー産生を維持している。酸素摂取、二酸化炭素排泄に障害が出てきたとき、また、それを維持するために努力が必要になってきたときには生命の危機が迫っており、医療的介入として呼吸療法が必要になる。
1994 年に「入門 呼吸療法」という名著が克誠堂出版から上梓されている。監修は故沼田克雄先生である。沼田先生は横浜市立大学の教授から1987年に東京大学の第3代目の麻酔科学講座教授になられた方で、1987 年、昭和天皇の手術の麻酔を担当されたことでも知られている。また、この年は、日本において臨床工学技士法が制定された年でもある。
私は1975 年に医科大学を卒業し、1987 年に母校の大学病院ICU の副部長となっている。この頃まで、呼吸療法に携わる医療者は医師であり、看護師はそれを補助し見守っていた。臨床工学技士の誕生は呼吸療法への新たな参入者の誕生であった。一方、当時、理学療法士制度は既にあり、回復期のリハビリテーションに従事していたが、呼吸療法に携わる理学療法士はまだおらず、または、極めて稀であった。しかし、1989 年、京都で第5 回世界集中治療医学会が開催された頃から、肺理学療法とか呼吸理学療法という言葉が聞かれるようになり、理学療法士が呼吸療法に参加するようになってきた。また、施設にもよるが看護師が患者を評価し呼吸療法への関与が大きくなっていった。
1990 年代に入ると、日本胸部外科学会、日本胸部疾患学会、日本麻酔科学会の3 学会が呼吸療法認定士制度の検討を始め、そのような時代背景の中、初版の「入門 呼吸療法」が発行されたと思われる。この本は、その10 年後の2004 年に呼吸療法の進歩とともに改訂されているが、それからほぼ20 年経つ2023 年の今、呼吸療法はさらに大きく変わってきている。
それは、呼吸療法が特別な治療ではなく通常医療といえるほど普及していること、それに伴い、呼吸療法に関わる医療者の幅が広くなっている。また、人工呼吸療法におけるハイフローセラピーや非挿管下のnoninvasive ventilation(NIV)が広く行われるようになり、VILI(ventilator-induced lung injury)やVALI(ventilator-associated lung injury)、P-SILI(patientself-inflicted lung injury)と呼ばれる人工呼吸による肺損傷へ配慮した人工呼吸療法が行われるようになってきている。また、呼吸ECMO もこの10 年で大きく普及した。さらに、呼吸療法中の全身管理も大きく変わり、それらが長期予後をも改善してきている。そのようなことから、「入門 新呼吸療法」として新たに発行することとした。
本書は、購読者の対象を呼吸療法に携わる医師や看護師、薬剤師、臨床工学技士、理学療法士、また、管理栄養士、臨床心理士としている。これらの医療者に呼吸生理、呼吸不全の病態、気道確保、酸素療法の基本的知識、非挿管下や挿管下そしてECMO を用いた人工呼吸療法、呼吸療法中の全身管理やモニタリングを理解していただきたい。さらに、臨床倫理の知識も学んでいただきたい。本書はあくまでも入門書と考えており、呼吸療法を始める医療者にとってなんらかのお役に立てることがあれば幸甚である。
2023年 初春
岡山大学名誉教授/函館市病院局長 氏家 良人
目次
第Ⅰ章 総 論
1 .呼吸療法とは 氏家良人
2 .呼吸の基礎知識 矢田部智昭,西田 修
A .ガス交換,血液ガス,酸塩基平衡
3 .呼吸不全と病態生理
A .急性呼吸不全と病態生理 岡本 師,宮崎泰成
B .慢性呼吸不全と病態生理 桑平一郎
C .神経筋疾患による呼吸不全の病態生理 石川悠加
D .術後呼吸不全と病態生理 惠川淳二,川口昌彦
E .心疾患による呼吸不全と病態生理 西脇 渓,佐藤直樹,竹田晋浩
F .小児における呼吸不全の病態生理 野坂宜之
G .肺感染症の基本 矢野晴美
4 .胸部画像の基本 木岡 睦,三浦祐樹
A .胸部X 線
B .肺超音波
C .胸部CT
第Ⅱ章 各 論
1 .薬物療法 大野博司
2 .呼吸理学療法 玉木 彰
3 .呼吸管理
A .気道確保・気道管理 今泉 均
B .酸素療法 大塚 将秀
C .人工呼吸療法
1 .非侵襲的陽圧換気(NPPV) 長谷川 隆一
2 .挿管下人工呼吸(各人工呼吸モード) 後藤 祐也,升田好樹
D .体外式膜型人工肺(ECMO) 梅井菜央
4 .呼吸療法と全身管理
A .ABCDEF バンドルとPADIS ガイドライン 長島 道生
B .早期リハビリテーション 山下康次
C .呼吸療法と栄養療法 巽 博臣
D .呼吸療法と感染対策 小林 敦子
5 .呼吸療法中の観察とモニタリング
A .パルスオキシメトリー,カプノグラフィー 丸山 史
B .人工呼吸器でわかる指標 三島有華
C .気管支鏡 山内 英雄
6 .各病態における呼吸療法
A .急性呼吸窮迫症候群(ARDS) 大下 慎一郎
B .慢性閉塞性肺疾患(COPD) 室 繁郎
C .気管支喘息発作 原田紀宏
D .間質性肺炎急性増悪 林 宏紀,吾妻安良太
E .小児・新生児の呼吸不全 井坂華奈子,竹内宗之
7 .呼吸療法における倫理 澤村匡史
キーワード索引
資料
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:10.9MB以上(インストール時:29.3MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.8MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:10.9MB以上(インストール時:29.3MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:43.8MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784771961074
- ページ数:250頁
- 書籍発行日:2023年3月
- 電子版発売日:2023年4月4日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。