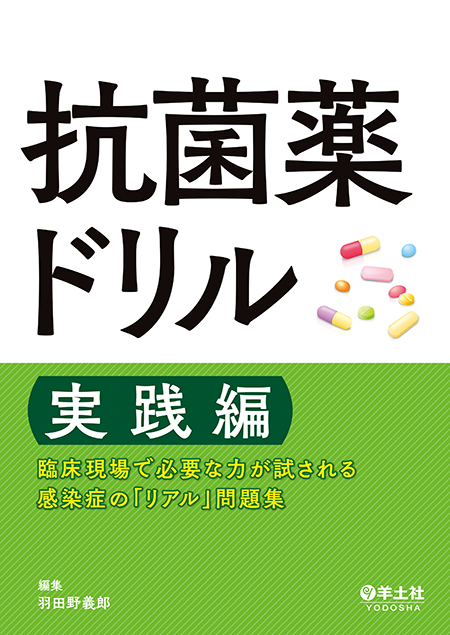- m3.com 電子書籍
- 抗菌薬ドリル実践編 臨床現場で必要な力が試される 感染症の「リアル」問題集
商品情報
内容
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。 詳細は こちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
序
2018 年4 月号のレジデントノートの特集,2019 年2 月の抗菌薬ドリル第1 巻に続き,今回実践編ということで再度戻ってきましたが,第2 巻が世に出るとは思ってもみませんでした.
初期研修中に感染症に興味をもち,臨床感染症の専門研修に入ったのは卒後6 年目,あっという間に専門研修後10 年が経過しようとしています.ここでは,私の個人的な経験を少しお話しさせてください.
初期研修中に肺炎球菌肺炎をペニシリンG で治療する経験を
私が総合内科の後期研修1 年目のとき,ER から肺炎の診断で入院する患者さんの喀痰グラム染色を行ったところ,Geckler 5,肺炎球菌を疑うグラム陽性双球菌のみが多数で肺炎球菌肺炎が疑われました.一般病棟で入院となり,指導医は「ペニシリンG で治療開始しよう」といい,「狭域な抗菌薬で本当に大丈夫だろうか?」と結構あせったのを覚えています.
というわけで患者さんのことを心配した私がなにをしたか?足しげく病棟に通い,患者さんの全身状態,呼吸数,咳や喀痰の性状はどうかなどを,今まで以上にベッドサイドで確認するようになりました.入院2 日目,患者さんは少し悪化している印象だったのですが,指導医の勧めで行ったその日の喀痰グラム染色では,たくさんいたグラム陽性双球菌はきれいに消失,多核白血球のみとなっていました.採血結果では白血球,CRP はさらに上昇していたのですが,これをみると「ああ,ペニシリンG は効いているな,一過性に悪くなっても肺炎球菌に効果はあるな」と,治療はうまくいっているという実感を得ることができました.その後,培養結果は肺炎球菌と判明し,患者さんは元気になり退院となりました(※このような症例では,肺炎球菌ワクチン接種も勧めましょう).
このような症例を数例経験し指導医となった頃,同様の症例を研修医の先生と診療する機会がありました.「ペニシリンG で治療開始しよう」と私が言うと,研修医の先生はかつての私と同様の反応をし「本当に大丈夫なんですか!?」とストレートに言い,そして今までよりもさらに病棟に向かうようになりました(無事軽快して退院されました).
グラム染色を研修医が行うことは,実にいろいろなことを教えてくれます.グラム染色を自分で染色することを通して検査に適する検体とはどのようなものか,代表的抗菌薬・微生物の知識を得る,症例を通しての微生物レベルでの鑑別診断,臨床推論のトレーニングができる,(電子カルテの前を離れ)ベッドサイドでの臨床研修になる,冒頭の症例のように治療がうまくいかないときの胆力?を得られる(かもしれない),最後に培養結果に振り回されない感染症診療が身につくといったことです.その結果,内科研修としての質が上がります.特に,グラム染色で原因微生物が「消えている」と経験した瞬間は,培養結果が出るまで暗闇のなかを歩いているような状況で診療を続けていた私にとっては,目の前がクリアになった瞬間でもあり非常に印象的でした.
そのような経験は,理想的にはcommon な疾患の感染症診療を指導医とともに行うことで得られるのかもしれませんが,common な感染症を診ていることが多いと思われる総合内科医や感染症専門医はまだまだ足りず,感染症専門医は病院全体の診療支援を行うだけで精一杯の施設も多いかと思います.まだまだこれからというところだとは思いますが,この10 年で感染症診療の質は大きく前進したと筆者は感じています.たとえ日本のどこでトレーニングを行おうとも,研修中に上記のような指導医と巡り合わなくても,臨床感染症の基本をこのシリーズで学べるというのをめざし,今回も,日々感染症診療に対峙している先生方に執筆をお願いしました.
この本が医学生や初期研修医,基本をおさらいしたい非専門医はもちろんのこと,昨今臨床推論の教育が盛んな薬学部学生,薬剤師,臨床検査技師,看護師などメディカルスタッフの方々の入門書となれば幸いです.
2020年2月1日
新型コロナウイルスで揺れる東京にて
羽田野 義郎
目次
序
解答記入用紙
略語一覧
1 成人急性上気道感染症
2 インフルエンザ
3 肺炎
4 尿路感染症
5 皮膚軟部組織感染症
6 腹腔内感染症
7 下痢症
8 敗血症
9 感染性心内膜炎・血管内感染症
10 髄膜炎
11 骨・関節感染症
12 周術期の患者へのアプローチ
13 動物咬傷
14 免疫不全と感染症
15 小児の感染症診療
16 妊婦・授乳婦の感染症診療
17 性感染症
18 HIV感染症
19 海外帰国者の健康問題
20 研修医に必要なワクチンの原則
索引
執筆者一覧
コラム
細菌性髄膜炎にメロペネムは投与すべきなのか?
髄膜炎菌
妊産婦のインフルエンザ診療
海外帰国者の診療でレベルアップをめざすあなたへ
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:12.5MB以上(インストール時:30.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:50.0MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:12.5MB以上(インストール時:30.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:50.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784758118668
- ページ数:245頁
- 書籍発行日:2020年3月
- 電子版発売日:2020年3月6日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。