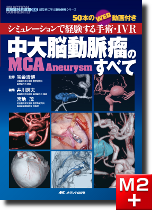- m3.com 電子書籍
- メディカ出版
- 中大脳動脈瘤(MCA Aneurysm)のすべて
商品情報
内容
部位別に脳動脈瘤手術・治療を解説するシリーズ。若手脳神経外科医が最初に担当することが多い中大脳動脈瘤(MCA Aneurysm)を取り上げる。豊富な症例と50本の術前CTA・手術動画でコイリング、クリッピングのコツ、ポイントがよくわかる。
序文
監修のことば
「刊行にあたって」で井川房夫先生も書かれている.動脈瘤破裂による突然死は,実際に遭遇すると,医学の無力さを痛感させられる.僕も,新年早々(2014 年早々),残念な話であるが,長く外来で保存的治療をしていた未破裂脳動脈瘤の知人の訃報の連絡を受けた.重症くも膜下出血で,外科治療の適応もなく,亡くなられた.
医学は言うまでもなく,自然科学の一分野である.自然科学では,観察とデータに基づいて,帰納法(Induction)から結論が導き出される.帰納法を取る限り,予測は確率で表現される運命から抜け出すことはない.例外はいつも存在し,それらは,「人知の及ばぬこと」として丸められる.帰納法の限界である.
一方で,臨床医の判断基準として,少数の法則(Law of Small Number)がある.少数の法則は,本来,ごく少ないサンプルから間違った全体の結論を導くミスリーディングを意味している.しかし,経験則は,しばしば医師の判断やさまざまな選択を左右する.臨床医が,いわゆる大数の法則に屈した近年のRCT を中核としたEBM に対して,不条理な(EBM を支持する側にとっては言われなき)反発を覚えるのは,臨床家が,日常の診療活動では,大数の法則より,少数の法則に従う習性を持っているからである.医師の判断・選択は,大数の法則を科学的根拠としつつも,しばしば,印象的な少数の経験に影響され,ヒューリスティックな選択が行われる.
前置きが長くなった.
本書は,現在,日本の動脈瘤治療を担う少壮気鋭の脳外科医によって書かれた.どの著者も一流の外科医ではあるが,経験症例数は合計しても,UCAS の数には遠く及ばない.個々人の経験は少なく,母集団のごくごく一部をサンプリングした程度のものである.本書の一流の筆者らもそうであるし,これから,第一例目の中大脳動脈瘤を経験する若い脳外科医も,一生の間に経験できる手術にはおよそ限りがある.
だからこそ,その経験を共有し,学習曲線を急峻なものにする必要がある.できることであれば,最初の一例から,本書の著者らの成績のレベルに達するべきである.患者にとっては,自身が,医師にとって反省すべき一例となることは許容されない.
外科治療における緩い学習曲線の問題を克服することが,私たち外科医に求められていることである.100%に限りなく近い安全性を達成することができれば,UCAS の結果の如何によらず,脳動脈瘤の外科治療・血管内治療は全例に推奨されるべきものとなるはずである.中大脳動脈瘤は,その可能性に最も近い対象である.
本書では,中大脳動脈瘤という,脳外科医にとって,外科治療成績の極限値に到達する可能性の最も高い動脈瘤治療のすべてが網羅されている.これ以上の専門書を想像することは私にはできない.本書から,経験値の高い術者も低い術者も,経験を共有し,大数の法則に支配されず,また,少数の法則に惑わされることなく,一例一例を一期一会の動脈瘤として治療できると確信する.
北海道大学大学院医学研究科脳神経外科 宝金清博
刊行にあたって
私は,脳神経外科医になった後,親しかった同級生の内科医が30 代の若さで破裂脳動脈瘤のためこの世を去るという出来事にあった.当時は直接治療を行える責任者の立場にはなかったが,脳神経外科医でありながら何の力にもなれなかった自分に対し,憤りと無力感を覚え,「破裂脳動脈瘤を安全に治療できる医者にならなければお前の存在価値はない」という神の声を聞いた.それからは,日本で破裂脳動脈瘤の治療を安全に行えるようにすることが自分の使命と考えている.
脳動脈瘤の治療は血管内コイル塞栓術が増えつつあるが,日本では2012 年でも約70%近くで開頭クリッピング術がなされており),現在は,世界で最も多くのクリッピング術がされている国かもしれない.中大脳動脈瘤は,その形態からコイル塞栓術が不向きな部位であり,クリッピングが選択される率が高い.したがって,血管外科医だけでなく,普段は血管内治療を主に行っている医師や,それほど経験がない脳神経外科医も術者となり得る疾患である.一方,中大脳動脈瘤の位置は脳深部ではなく,シルビウス裂を剥離すれば,比較的容易に到達する部位である.しかしながら特に破裂動脈瘤では,くも膜下血腫のため,中大脳動脈のM3,M2 の位置の同定や判定,オリエンテーションは必ずしも容易ではなく,自分の予想に反し,動脈瘤が思いのほか浅く存在し危険を伴うこともある.したがって,さまざまなバリエーションに対し安全に手術を行うためには,ある程度の経験が必要である.
近年,画像診断機器が飛躍的に進歩し,術前の画像診断で脳,骨,動静脈の走行から十分なシミュレーションを行えば,親血管を同定したり動脈瘤中枢血管を見つけたりすることにより,安全に動脈瘤に到達できる.したがって,術前CTA などの画像診断をもとにしたシミュレーション,術中修正の仕方が非常に重要となる.また,動脈瘤と周辺組織との剥離やネッククリッピングも重要で,術前シミュレーションにて周辺の動静脈との剥離の必要性,ネックの形状を把握することにより,安全に行うことができる.これらを会得するために,これまで脳神経外科医は1 例1 例,術前画像と術中所見から修正を繰り返し,自分の経験として体得してきた.しかし,血管内治療のラーニングカーブの急峻さに比較して,クリッピング術のカーブの鈍さは問題であり,画像診断と動画が進歩した今日では,術前画像と術中動画から経験値をカバーできると考えられる.
そこで今回,筆者らは,術前CTA を中心とした画像診断からシミュレーションを行い,その後,実際の手術をカラー画像・動画で見て,中大脳動脈瘤のさまざまなパターンから,陥りやすいシミュレーションのピットフォールなどについて解説し,自分の経験値を補足すべく本書を企画した.
一方,中大脳動脈瘤では血管内治療でコイリングを行うことは,他の部位ほど多くないが,治療せざるを得ない場合もある.血管内治療においても,親血管であるM1 と動脈瘤の向き,ネックの大きさ,M2 の方向,位置などを術前CTA などの画像でシミュレーションすることにより,術中のポイントを把握できる.しかし,実際の治療では,術前のシミュレーションでは把握できなかった点,ピットフォールなどもあり,これらを疑似体験することは非常に重要と考える.開頭手術のみならず,血管内治療においても術前シミュレーションと実際の治療とのギャップを埋めることは必須であるため,血管内治療も含めて解説した.
それぞれのパターン別に症例を提示しており,読者はまず,自分自身が治療するつもりで術前画像・動画(動脈,静脈,骨画像)より術前のシミュレーションを行い,術中に血管や動脈がどのように見えてくるかを想定していただきたい.シミュレーション動画はゆっくり動くため,自身の動画ソフトで順行,逆行させ,詳細に把握できる.その後,実際の手術画像・動画で,シルビウス静脈,M3-M2,動脈瘤がどのように見えてくるかを見て,自分のシミュレーションが正しいかどうか確認する.これを違うパターンの症例で繰り返すことにより,いろいろなバリエーションを経験でき,実際の手術でも対応できるようになる.すなわち,本書でぜひ「疑似手術体験」を積んでいただければ幸いである.
島根県立中央病院脳神経外科 井川房夫
目次
・監修のことば
・刊行にあたって
・執筆者一覧
・WEB 動画の視聴方法
【1章 中大脳動脈瘤概論】
〔1〕中大脳動脈の血管解剖
〔2〕シルビウス静脈の解剖
〔3〕中大脳動脈とシルビウス静脈の画像診断とシミュレーションの実際
〔4〕中大脳動脈瘤の疫学と特徴
【2章 中大脳動脈瘤のクリッピング】
〔1〕術前検査と術前シミュレーションのポイント
〔2〕中大脳動脈瘤の分類
〔3〕手術アプローチとシルビウス裂の開放
〔4〕中大脳動脈瘤の特徴とクリッピングの方法
〔5〕中大脳動脈瘤のkeyhole clipping 術
〔6〕シミュレーションと手術の実際
[A]長いM1凸タイプ①
[A]長いM1凸タイプ②
[B]長いM1凹タイプ①
[B]長いM1凹タイプ②
[C]短いM1上向き瘤タイプ①
[C]短いM1上向き瘤タイプ②
[D]短いM1下向き瘤タイプ①
[D]短いM1下向き瘤タイプ②
[E]M1動脈瘤①
[E]M1動脈瘤②
[E]M1動脈瘤③
[F]広頚 / 血栓化 / 巨大①
[F]広頚 / 血栓化 / 巨大②
[F]広頚 / 血栓化 / 巨大③
[G]末梢,その他①
[G]末梢,その他②
[G]末梢,その他③
【3章 中大脳動脈瘤のコイリング】
〔1〕術前検査と術前シミュレーションのポイント
〔2〕脳血管内治療の実際
〔3〕シミュレーションと治療の実際
[A]simple
[B]軸と突出方向がずれている瘤,不整形瘤
[C]広柄(reversed branch)
[D]広柄(terminal type)①
[D]広柄(terminal type)②
[D]広柄(terminal type)③
[E]巨大 / 血栓化①
[E]巨大 / 血栓化②
【4章 応用編】
〔1〕中大脳動脈瘤のトラブルシューティング(クリッピング編)
〔2〕中大脳動脈瘤のトラブルシューティング(コイリング編)
〔3〕巨大中大脳動脈瘤のトラップ+バイパス
〔4〕解離性,細菌性,その他の動脈瘤治療
[A]クリッピング
[B]コイリング
・おわりにあたって
・索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:954.9MB以上(インストール時:2.0GB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:3.7GB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:729.1MB以上(インストール時:1.8GB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:2.8GB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784840448956
- ページ数:264頁
- 書籍発行日:2013年3月
- 電子版発売日:2014年8月1日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。