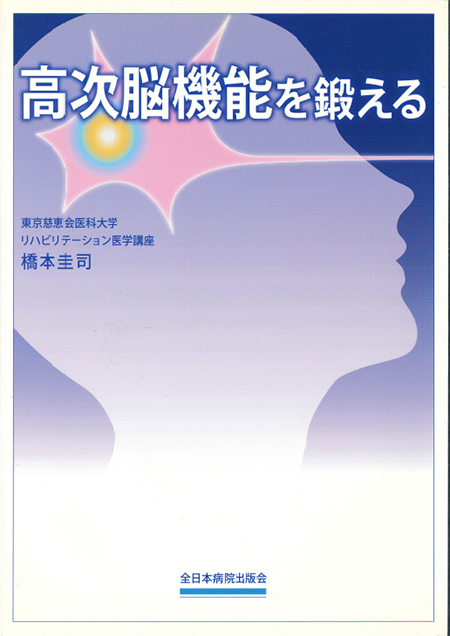- m3.com 電子書籍
- 全日本病院出版会
- 高次脳機能を鍛える
商品情報
内容
症例ごとにオーダーメイドな対応が必要とされる中、筆者自身が実践し、効果のあったものだけをまとめた書。 医療従事者のみならず、患者・ご家族などにも自宅で役立つ対処法をわかりやすくイラストで解説!
序文
私が医師になり立ての頃,我が国における高次脳機能障害に関する治療・支援の実態は,その診断や評価に重きが置かれており,何ができないか,何が問題かといった議論が主体であったように思われる.しかしながら,高次脳機能障害を抱えた患者とその家族にとって,診断や評価だけが重要なわけはなく,それをいかに克服するか,それと共に生きていくかといった切実な問題が目の前に横たわっていた.
その後,2000年には日本脳外傷友の会が設立され,偶然にも,その年の 7月に私は神奈川リハビリテーション病院に医局からの派遣で勤務することになった.翌 2001年から 5年間,国の施策として,高次脳機能障害支援モデル事業が行われた.偶然に偶然が重なり,神奈川リハビリテーション病院では,通常の医局派遣では考えられないほど長い,約 5年弱にわたって,高次脳機能障害者の治療・支援に関わることになった.
本書では,筆者が,東京都リハビリテーション病院,神奈川リハビリテーション病院,東京医科歯科大学難治疾患研究所,東京慈恵会医科大学附属病院,NPO 法人日本脳外傷後遺症リハビリテーション支援ユニオン(JUTRA)で経験したあらゆる臨床経験,そして,米国のニューヨーク大学ラスクリハビリテーション医学研究所脳損傷者通院プログラムやリハビリテーションホスピタルオブザパシフィック脳損傷病棟の見学などを通じて,我が国において実践可能なあらゆる高次脳機能障害治療・支援の実際を記した.
その一方で,高次脳機能障害に関するすべての治療・支援法については,まだ十分な科学的検証がなされているわけではない.本書で紹介した内容は,あくまでも,自分自身で実践した結果,効果のあったものだけを記している.つまり,何が問題かではなく,何ができるかを筆者なりに考えた結論がそこにある.しかしながら,高次脳機能障害者の治療・支援は,マニュアル通りには行かないことが多く,症例ごとにオーダーメイドである必要がある.したがって,読者が本書に記された方法のいずれかを活用していただいた結果,うまくいかなかったとしても,筆者の経験とは異なっていたということでご容赦いただきたい.
最後に,高次脳機能障害治療・支援に関して,神奈川リハビリテーション病院でご指導いただいた大橋正洋先生,渡邉修先生,ニューヨーク大学ラスクリハビリテーション医学研究所の見学の機会をお与え下さった小澤富士夫様,立神粧子様ご夫妻,東京医科歯科大学や NPO 法人 JUTRA でお世話になっている中村俊規先生とオレンジクラブのスタッフならびに訓練生とそのご家族の皆様,東京慈恵会医科大学でご指導いただいている安保雅博先生,そして,本書のイラストと表紙のデザインをご担当下さった寺田輝代様,寺田健太様親子に心からの感謝を捧げる.
2008年 5月
橋本圭司
目次
はじめに
I 高次脳機能障害を理解する
●高次脳機能とは
●高次脳機能障害とは
●高次脳機能障害の症状
II 高次脳機能障害の診断を理解する
●高次脳機能障害診断基準
●画像診断
●神経心理学的検査
●脳機能診断
III 脳機能循環を理解する
●脳の局在
●脳機能循環
●人全体として整える
IV 神経心理循環を理解する
●神経心理循環(Neuropsychological Spiral)とは
●正の神経心理循環(Positive Neuropsychological Spiral;PNS)とは
●負の神経心理循環(Negative Neuropsychological Spiral;NNS)とは
V リハビリテーションの原則
●「できない」ではなく「できる」を伸ばす
●環境を整える
●リハの順番
●診断の重要性
●薬の調整
VI「耐久力」を鍛える
●易疲労性とは
●易疲労性の症状・サイン
●易疲労性への対応法
●耐久力を鍛える
VII「抑制力」を鍛える
●脱抑制とは
●脱抑制の症状・サイン
●脱抑制への対応法
●抑制力を鍛える
VIII「意欲・発動性」を鍛える
●意欲・発動性の低下とは
●意欲・発動性の低下の症状・サイン
●意欲・発動性の低下への対応法
●意欲・発動性を鍛える
IX「注意・集中力」を鍛える
●注意・集中力の低下とは
●注意・集中力の低下の症状・サイン
●注意・集中力の低下への対応法
●注意・集中力を鍛える
X「情報獲得力」を鍛える
●失語とは
●失語の症状・サイン
●失語への対応法
●情報獲得力を鍛える
XI「記憶力」を鍛える
●記憶障害とは
●記憶障害の症状・サイン
●記憶障害への対応法
●記憶力を鍛える
XII「遂行機能」を鍛える
●遂行機能障害とは
●遂行機能障害の症状・サイン
●遂行機能障害への対応法
●遂行機能を鍛える
XIII 自分に気づく
●病識の欠如とは
●病識の欠如の症状・サイン
●病識の欠如への対応法
●自分に気づく
XIV 認知訓練(オレンジクラブでの実践)
●見当識を高める(見当識訓練)
●耐久力を高める(計算・漢字ドリル)
●注意・集中力を高める(新聞抹消課題)
●情報獲得力・記憶力を高める(新聞要約訓練)
●遂行機能を高める(すうじ盤)
XV 家族指導
●高次脳機能障害を理解する
●神経心理循環を理解する
●適切な対応法を理解する
●自分自身を鍛える
XVI 明日に向かって
●高次脳機能障害は良くなる
●高次脳機能障害のリハビリテーションの場は病院だけではない
●一部の願いをみんなの願いへ
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:26.5MB以上(インストール時:57.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:106.0MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:8.8MB以上(インストール時:21.9MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:35.2MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784881170410
- ページ数:65頁
- 書籍発行日:2008年6月
- 電子版発売日:2014年9月12日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。