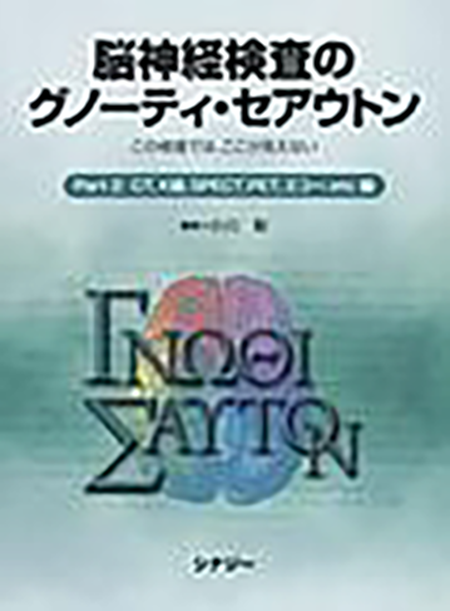- m3.com 電子書籍
- 小川 彰
- 脳神経検査のグノーティ・セアウトン Part2 CT,X線,SPECT,PET,エコー,etc編 この検査では,ここが見えない
商品情報
内容
「グノーティ・セアウトン」とは、デルポイのアポロン神殿の入口に刻まれた古代ギリシアの箴言である。ソクラテスがこれを自身の哲学の基としたことで有名となり、世界に広く伝えられた。意味は「汝自身を知れ」であり、言い換えれば「自分が知っていることの限界を謙虚に自覚し、根拠のないことを正しいと思い込んでいないかを認識しなさい」ということである。
脳神経領域の検査、診断、治療の進歩発展はきわめて速く、いまの常識が10年後には非常識に変わる時代である。われわれがいま常識と考えていることも、もしかすれば非常識の域にあるのかもしれない。
本書はまさに日進月歩を遂げつつあり、日々常識が塗り替えられつつある「脳神経領域の最新検査の」グノーティ・セアウトンを目指したものである。本書をお使いになる先生方は、参照すればするほど本書の“すごさ”と“奥深さ”を実感していただけるものと思う。
(編者「序」より)
序文
本書のタイトル「グノーティ・セアウトン」(ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ)とは,デルポイのアポロン神殿の入口に刻まれた古代ギリシアの箴言である.日頃あまり聞きなれない言葉かもしれない.しかし,ソクラテスがこれを自身の哲学の基としたことで有名となり,世界に広く伝えられた.現在なお世界の多くの大学で「学是」して使われ,学問・教育の基本に位置づけられている.意味は「汝自身を知れ」であり.言い換えれば「自分が知っていることの限界を謙虚に自覚し,根拠のないことを正しいと思い込んでいないかを認識しなさい」ということである.ソクラテスの言葉「一つだけ知っていることは,自分が何も知ってはいないということ」(He who knows but one knows none)にも通じるものがある.
脳神経領域の検査,診断,治療の進歩発展はきわめて速く,いまの常識が10年後には非常識に変わる時代である.われわれがいま常識と考えていることも,もしかすれば非常識の域にあるのかもしれない.事物の根幹に関わる不変の知見と,いままさに変わりつつある知見を整理しつつ「汝の置かれている“立ち位置”を正確に知る」ことが求められている.
本書はまさに日進月歩を遂げつつあり,日々常識が塗り替えられつつある「脳神経領域の最新検査の」グノーティ・セアウトンを目指したものである.簡潔に1冊で仕上げる予定であったが脳神経分野の新知見はあまりに多く,2冊の大作となってしまった.これは脳神経検査の進歩があまりにも速いことに起因しており,ご容赦願いたい.
著者の先生方を見れば,まさに,日本の脳神経領域を実質的に牽引している素晴らしい方々が名を連ねている.公務多忙の折,貴重な時間を割いていただき素晴らしい論文をお書きいただいた.その意味でも本書はまさに現時点の最新知識の「塊」である.本書をお使いになる先生方は,参照すればするほど本書の“すごさ”と“奥深さ”を実感していただけるものと思う.
最後に,発刊にあたって,表に裏に大変なご努力をいただいたシナジー出版事業部の諸君に御礼申し上げ「序」の言葉としたい.
2010年10月5日
岩手医科大学学長
小川 彰
森 昌朋
目次
1. CT
CTA,MRAのみでは診断困難な頚動脈高度狭窄病変
CTでは診断が困難なくも膜下出血がある
3D-CTAで見誤る脳動脈瘤の形態
未破裂脳動脈瘤の破裂リスクはわからない
軽症くも膜下出血を見逃すな:診察のポイントと画像診断のコツ
くも膜下出血急性期の画像診断で見落としやすい動脈瘤
CTで見落とす頭蓋内出血
意識障害を伴う外傷性くも膜下出血で,頭部CTのみでは橋延髄接合部損傷がしばしば見落とされる
特発性正常圧水頭症の患者の診療において,通常アキシャルCTを用いて病態をどのように評価できるか:とらえるべき確実な所見とその限界
新生児の脊椎3D-CTは,二分脊椎と誤認しやすい
2. X線
脳血管撮影の原理とピットフォール
くも膜下出血で発症した内頚動脈非分岐部動脈瘤:初回脳血管撮影所見の解釈
潜在性脳血管吻合:通常の脳血管造影では描出困難な頭頚部血管ネットワーク
シングルプレーンでは脳動脈瘤塞栓術中の瘤外コイル逸脱を見落とすことがある
バルーン閉塞試験のピットフォール
3. SPECT
脳血流SPECT 検査では不完全脳梗塞の診断はできない
脳血流定量測定でPaCO2を無視すると,バイパス適応を誤って判定することがある
脳血流画像上の脳血流量低下かつ脳循環予備能低下は,必ずしも貧困灌流ではない
脳血流SPECT 検査では高次脳機能障害の局在診断は可能か
頭部201Tl-SPECT 診断におけるピットフォールと限界
再発悪性グリオーマと脳放射線壊死の鑑別は,Gd-MRI,201Tl-SPECTではできない
頭部外傷急性期に神経症状が増悪する場合,同時にhemispheric hyperperfusion が発生していることがある
4. PET
PETによる脳腫瘍診断は,その仕組みと限界を知ることで有効な利用ができる
脳腫瘍診断におけるPET 検査の意義と目的
脳腫瘍および非腫瘍性病変のPET
メチオニンPET が陰性だからといって,脳腫瘍でないとはいえない
メチオニンPETの落とし穴
メチオニンPETは,腫瘍性病変以外でも陽性を示す場合がある
Cushing 病の早期診断:微小腺腫の局在診断に有用な検査とは
5. エコー
頚動脈エコー検査のあてにならない情報とは?
2 次元超音波検査では知りえない頚動脈の3 次元情報
可動性プラークの描出:CAG,CTA,MRI,頚動脈エコーのうち,どれが有用か?
眼動脈血流の観察で,脳血管障害としての眼症状の評価は可能か?
頚部血管エコー検査では,頭蓋外内頚動脈解離を評価できない
経頭蓋Doppler(TCD)の結果からは,脳血管攣縮をきちんと判定できない場合がある
脳動脈瘤クリッピング術中のICG アンギオグラフィ:micro-Doppler flow meterでピットフォールを補う
6. 電気生理学的検査
開頭手術における経頭蓋刺激運動誘発電位モニタリングのピットフォール
電気刺激による脳機能マッピングや覚醒下手術時のモニタリングで症状出現部位が必ずしもfunctional tissueとは限らない
術中運動誘発電位測定で運動麻痺を見誤ることがある
術中運動誘発電位(MEP)モニタリングのピットフォール
側頭葉てんかんでは,頭皮上脳波の側方性(laterality)とMRI 所見が乖離することがある
視床下核の解剖学的な同定と電気生理学的な同定は異なることがある
7. 知能・心理検査
MMSEやHDS-Rだけではわかりにくい内頚動脈狭窄症の高次脳機能障害
MMSEやHDS-R が高得点の認知症のおばあちゃん,低得点なのに認知症と診断されないおじいちゃんが存在する
ワダテストの記憶評価を検証する
8. 感染症,血液・生化学,病理検査
タップテスト(髄液排除試験)により特発性正常圧水頭症(INPH)の診断は100%可能か?
グリオーマの病理診断:ピットフォールに陥らないために
βHCGの測定では,HCG 産生腫瘍の動向は測れない
下垂体機能検査だけでは見えない下垂体機能と派生する疾患
ADH,ANP,BNPの測定では,中枢性塩類喪失症候群の鑑別はできない
シャント感染など,異物に付着した細菌の抗生剤感受性は,通常の薬剤感受性試験ではわからない
9. その他の検査
光トポグラフィによる脳機能計測のピットフォール
頚動脈硬化病変と耳朶皺サイン:頚部エコーやMRAを撮る前に
抗リン脂質抗体は多くの種類があり,通常の検査で見落とすことがある
拡散強調トラクトグラフィーや脳電気刺激では評価できない運動機能評価を必要とする脳神経外科手術
脳槽シンチグラフィーだけでは,脳脊髄液減少症は診断できない
虐待でない乳児硬膜下血腫も存在する
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:38.9MB以上(インストール時:84.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:155.6MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:58.5MB以上(インストール時:146.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:234.0MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784916166364
- ページ数:276頁
- 書籍発行日:2010年11月
- 電子版発売日:2014年4月11日
- 判:A5変型
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:2
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。