- m3.com 電子書籍
- へるす出版
- 改訂第5版 救急隊員標準テキスト
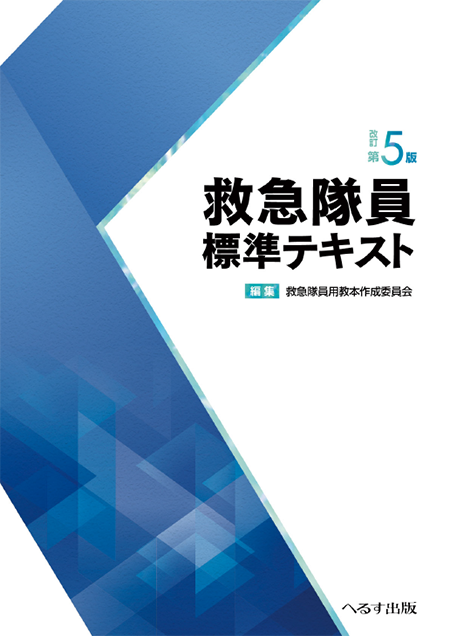
改訂第5版 救急隊員標準テキスト
救急隊員用教本作成委員会 (編) / へるす出版
商品情報
内容
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
編集にあたって
「救急隊員標準課程テキスト」が上梓されたのは1992年であり,その改訂版として「救急隊員標準テキスト」が発行されたのは約10年後でした。その後はほぼ6年ごとに改訂作業が行われ,今回改訂第5版を発行することになりました。
救急医療・医学を取り巻く環境は,刻一刻と変化し,進歩を遂げています。
メディカルコントロール体制のますますの充実強化に伴い,救急医療に従事する方々には最新の知見と技術だけでなく,地域の救急医療全体を視野においた「新しい意識」が求められています。また,救急隊員の観察や処置の能力向上を目的に,広く普及しているACLS,PSLS/PCEC,JPTEC に加え,日々新しい教育プログラムが開発提供されています。これらのプログラムは今後さらに改良が加えられ,救急医療とそれに関連する多職種を「つなぐ」ツールへと進化する可能性も想定されます。
改訂第5版の編集方針として,最新の知見に基づいて改訂を行うことは当然のこと,本書が「救急救命士標準テキスト」の入門書的な位置づけではなく,“ 救急はこれを読めば大丈夫” といえる,本書のみで完結した内容とすることをコンセプトに掲げています。病態の理解に先立ち「現場でまず何を判断し,何を行うべきか」に重点をおいた記述を心がけ,編集を進めました。同時に全編にわたって内容の見直しを行い,とくに救急症候の緊急度・重症度の判断につきましては,総務省消防庁の「緊急度判定プロトコルVer.2.0」を反映した総論を新たに設けました。その他,記載の重複がみられた感染防止や消毒の項目などを整理し,より実践活動に役立つ内容を意識した改訂を行っております。
また,第4版の発行より現在までに行われた,「JRC 蘇生ガイドライン」「救急蘇生法の指針」の改訂(2015年)や「准救急隊員」の創設(2017年)といった法律の改正など,わが国の救急医療における重要な動向にも対応しています。
本書の執筆・編集に際しては,改訂第4版に引き続き純粋に医学的な内容以外はすべて消防関係者に執筆していただき,医師はその医学的内容について校閲しました。同時に医師の執筆した内容は消防関係者の「現場目線」から査読していただき,活発な意見交換を行いつつ編集作業を進めました。執筆にあたられた各地の消防本部の救急隊員・救急救命士の実力と本書編集作業における消防関係者の奮闘には目を見張るものがありました。消防関係者が自ら後輩たちを教育・指導するための,医療側と消防側の密な協力関係を改めて感じた時間でもありました。
本書の編集方針が十分に反映され,救急隊員が必要とする知識について過不足なく平易に記述されたか否かの判断は読者に委ねるとして,編集委員一同精一杯の努力をしております。もし,それが実現できていないとすれば編集委員長の責任であります。幾たびも加筆修正に対応いただいた執筆者の方々,ご多忙のなか長時間を割いて編集作業にあたられた編集委員に改めて感謝申し上げる次第です。
本書が,救急隊員,消防職員として活躍されている方々に広くお読みいただき,日々の活動の糧となり,一人でも多くの傷病者の命が救われることを願ってやみません。
2018年12月吉日
「救急隊員用教本作成委員会」編集委員長
埼玉医科大学総合医療センター病院長
堤 晴彦
目次
第1編 救急業務の総論
1 救急業務の意義と沿革
2 救急業務の運用体制
3 救急医療体制
4 関係機関との連携
5 救急業務の関連法規
6 社会保障と社会福祉
第2編 救急業務の各論
1 基本的救急活動
2 救急活動の記録
3 救急活動と通信連絡体制
第3編 救急医学
1 救急医学の基礎
2 観察と判断
3 救急症候と緊急度・重症度判断
4 特殊病態と緊急度・重症度判断
5 応急処置
第4編 災害と多数傷病者対応
1 災害とは
2 多数傷病者対応
3 他機関との連携
第5編 救急資器材
1 観察用資器材
2 呼吸循環管理用資器材
3 創傷等保護用資器材
4 搬送・固定・保温用資器材
5 その他の応急処置用資器材
第6編 感染防止
1 感染防止
2 感染予防に関する法律
付録
1 救急医療機関での診療
2 病院実習
3 付表
索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:32.4MB以上(インストール時:75.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:129.7MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:32.4MB以上(インストール時:75.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:129.7MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784892699597
- ページ数:330頁
- 書籍発行日:2018年12月
- 電子版発売日:2020年11月18日
- 判:A4判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。


