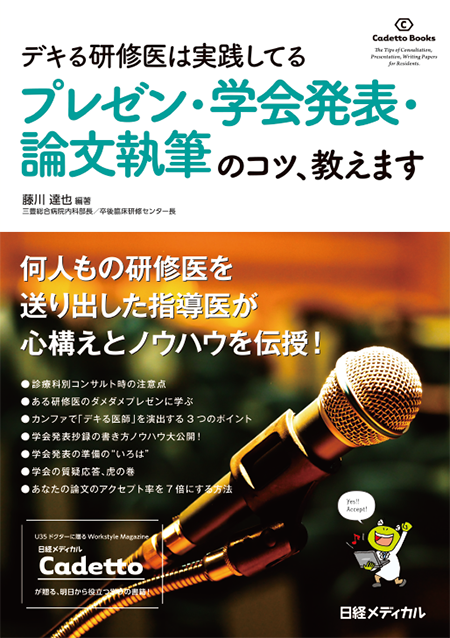- m3.com 電子書籍
- 日経BP
- デキる研修医は実践してる プレゼン・学会発表・論文執筆のコツ、教えます
商品情報
内容
●診療科別コンサルト時の注意点
●ある研修医のダメダメプレゼンに学ぶ
●カンファで「デキる医師」を演出する3つのポイント
●学会発表抄録の書き方ノウハウ大公開!
●学会発表の準備の“いろは”
●学会の質疑応答、虎の巻
●あなたの論文のアクセプト率を7倍にする方法
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
はじめに
皆さんは病院で他の先生やスタッフとのコミュニケーションに自信があるでしょうか?
コミュニケーションと言っても、世間話や噂話の類いではありません。社交的かどうかという意味でもありません。ここで言うコミュニケーションとは、医師業務にかかわるやりとりのことです。つまり他診療科の先生や指導医へのコンサルテーション、医局のカンファレンスでのプレゼンテーション、そして国内外の学会の場で発表し、質疑応答や議論すること、さらには皆さんが診療中に気がついた新しい知見を論文にして世界に発表することです。そこには医療現場ならではの“お作法”があります。
私はどちらかと言えばこうしたコミュニケーションに苦手意識を持っていました。特に医師になりたての頃は、指導医の先生に教えてもらいながらもある程度の経験を積むまではどこか不器用で、たどたどしかったと記憶しています。
そんな苦手意識を持っていた私でさえ、ある程度の臨床経験を積み、他診療科の先生とスムースなコミュニケーションが取れるようになり、そしていくつもの学会発表を経験し、いくつも英語論文を発表するはじめにことができました。また、研修医を指導する立場になり、いくつかの病院で数多くの研修医を指導してきました。
本書はそんな私と私が勤務する三豊総合病院で同じく研修指導する立場の先生方とで、コミュニケーションのノウハウをまとめたものです。
前半の第1章から第4 章では、主にコミュニケーションに関する心構えとノウハウ、つまり医師になったらいや応なく経験するコンサルテーション、症例の概要を伝えるプレゼンテーション、そして国内学会で発表するために何が必要なのかを紹介しています。日常の臨床風景で遭遇しそうな状況を多数設定しており、研修医の皆さんが研修を受けるときに気をつけること、持つべき心構えを散りばめました。コンサル、プレゼン、学会発表と聞いて「難しそうだ」「うまくできるかな?」と感じました? 大丈夫! 誰でも皆、最初は初心者です。そして本書は、毎年、毎日、研修医の先生方と接し、教え教えられている立場として、現場目線で書いています。
医師としてぜひチャレンジしてほしい国際学会での発表、そして英語での論文執筆についてはどうでしょうか? そもそも経験がないばかりか、考えてみたこともないという方が多いのではないでしょうか。
でも、実は皆さん、興味がありますよね? あなたの先輩、上級医が海外の学会に出向いて英語で発表し、英語で論文をまとめて有名雑誌に掲載された、なんてこと、一度は耳にしたことがあるでしょう? そして憧れますよね。
私の場合、医師になって数年経過した頃から自ら進んで取り組みました。皆さんと同じで、憧れたからです。だから抵抗はありませんでしたし、たとえ目が回るほど多忙なときも、業務外の時間を費やしても、苦痛に感じることはありませんでした。後半の第5 章、第6 章では、皆さんが日常診療で学んだことをブラッシュアップさせることができる海外学会での発表や英語論文執筆について、具体例を交えて解説しました。当院で研修を終えた先生は、他院で診療をしながらもトップジャーナルへの論文投稿や国際学会で活躍した様子を報告してくれます。本書は皆さんも同じように活躍していくためのノウハウをお伝えできるものと信じています。
何も一気に全てできるようになる必要はありません。本書は、医師になった皆さんが経験していくであろうことから順に1つずつ解説しています。初めてのことに取り組むとき、本書を思い出してください。ここに心構えとノウハウが書いてあります。
本書が研修医、若手の先生方の日々の診療における円滑なコミュニケーションの助けになること、そしていずれ専門の分野に進んだ暁には皆さんが日々経験し、学んだ知見を全国、そして世界に向けて発信するために役立つことを願っています。
2021年1月 藤川達也
目次
第1章 どうする? 他診療科へのコンサルト(藤川)
1 デキる研修医はコンサルトが違う
2 他科コンサルト時のノウハウ(概論)
3 さあ、他科コンサルトだ!!(実践編)
4 一緒に当直する指導医へのコンサルト
5 看護師などスタッフへの指示・依頼
6 大公開!他科コンサルト時の注意点
第2章 症例プレゼンってどうすればいいの?(安田)
1 症例プレゼンって何?
2 ある研修医のダメダメプレゼン
3 まずは患者さんの情報収集!
4 TPOに合わせたプレゼンを作る
5 プレゼンで「デキる医師」を演出する3つのポイント
6 成長した研修医のイケてるプレゼン
第3章 学会発表準備のイロハ(山内)
1 何のために学会発表をするの?
2 まず何から始めるの? 発表演題テーマの選び方
3 テーマが決まったら次は文献検索!
4 抄録を書き始めるときの準備
5 抄録の書き方ノウハウ大公開!
6 上級医・教授との打ち合わせってどうする?
7 スライドの作り方
第4章 国内学会発表、いよいよ本番(安原)
1 学会デビューへの道のり
2 いざ会場へ!準備はOK?
3 いよいよ発表だ!
4 質問が来た…どうする?
ミニコラム これさえあれば学会もコワクナイ? ~質疑応答 虎の巻~
5 ちょっと待って。降壇してからも大切
6 帰宅してから(反省、他の学会に、論文に)
ミニコラム 「さあ打ち上げだ!」会場手配のコツ
ミニコラム Zoomで学会発表!さあどうする?
第5章 海外学会で発表だ!(藤川)
1 研修医で国際学会デビュー(これぞアカデミック活動)
2 あなたの英語は大丈夫?
3 演題登録はどうやるの?
4 やった、アクセプト!学会までに何をしておく?
5 さあ発表だ。日本とは勝手が違うので要注意。
第6章 論文発表までの道のりを学ぼう(藤川)
1 「英語論文なんて専門医になってから」と思ってませんか
2 診察室にはいつもカメラを持参しよう
3 論文執筆前の心構え
4 投稿する論文誌はどう見極める?
5 論文を書く前に準備したい4つのこと
6 何科の疾患が論文になりやすい?
7 参考文献の選び方、読み方、教えます
8 患者さんから同意書を頂くときに ~論文の意義も伝えたい~
9 クリニカルイメージ論文のひな型、大公開
10 意外に頭を悩ます共著者問題
11 あなたの論文のアクセプト率を7倍にする方法
ミニコラム あらぬ剽窃疑い
12 「いざ投稿!」実際に何をする?
ミニコラム 多重投稿にはご注意を
13 便りのないのは良い便り?
ミニコラム 果報は寝て待て
14 いずれ評価する立場になるんですよ
15 最終目標はアクセプト?
おわりに
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:9.7MB以上(インストール時:21.9MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:38.7MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:9.7MB以上(インストール時:21.9MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:38.7MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784296109029
- ページ数:228頁
- 書籍発行日:2021年3月
- 電子版発売日:2021年3月26日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。