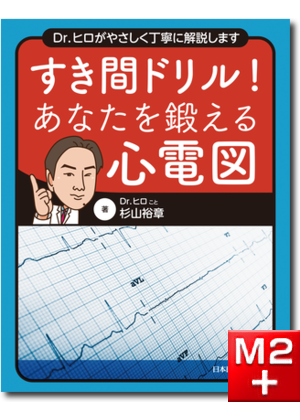- m3.com 電子書籍
- 日本医事新報社
- すき間ドリル!あなたを鍛える心電図
商品情報
内容
心電図は撮って終わりでなく、きちんと読み解く必要があります。
教科書的な典型的な心電図だけでなく、「日常の何気ない心電図」を多数掲載。
実は心電図が苦手で……という方にこそ読んでいただきたい1冊です。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
巻頭言
この書籍は,週刊「日本医事新報」に令和2年1月11日(No.4994)~同年12月26日(No.5044)にわたり,
『“すきドリ”すき間ドリル! 心電図~ヒロへの挑戦状~』
として連載された心電図クイズの内容をまとめたものである。
「週刊」ペースでの寄稿は初の経験であり,令和2年はほぼ毎日,症例(心電図)選択,原稿作成および校正作業に追われた1年間であった。通常の臨床業務に加えて,他の定期連載や著作物の作成など,いま振り返ってみると,自身の医師人生で最も忙しかったように思う。
問題はすべて筆者オリジナルであり,実際にあった症例をベースとしている。わずかに脚色を加えた部分もあるが,ほぼ“素材100%”─ これぞリアル・ワールドからの出題である。
問題作成にあたっては,満遍なく“心電図力”をつけてもらえる内容を意識した。問題・解説を通して伝えたいメイン・テーマとして,①波形異常,②不整脈,③虚血性心疾患,④ノンセクションの4つを想定し,月単位でほぼ1回ずつ登場するイメージで臨んだ。
なるべく均等になるよう配慮したつもりであったが,“自転車操業”的な作業で,症例によっては複数のテーマに関係することもあり,結果的に多少の偏りが存在することになった。具体的には,不整脈:21問(41%),虚血性心疾患・胸痛関連:13問(25%)を中心に,その他(波形異常,ノンセクション):17問(33%)のような問題構成である。この51問を,週刊誌掲載順ではなく,ほぼランダムに並べ替えてある。その分, 解説にくり返しがあったり, 後半の問題で判読メソッドを詳しく取り上げたりしているように見える部分もあるが,その辺はお許しいただきたい。
また,解説についても筆者なりの“コダワリ”がある。「心電図は得意ですか? それとも苦手?」─ コメディカルや医学生,研修医・レジデントや実地医家の先生などにレクチャーをするとき,筆者ははじめにこう質問することが多い。すると,(一部に巻頭言は謙遜もあろうが)「得意でない」や,時には「全然ダメ・超苦手」とまで言う方々のほうが多い印象を持っている。皆さん自身の状況も思い浮かべてみて欲しい。
心電図の教科書は多い。医学書のコーナーに行けば,非常にたくさんの心電図本が見つかるのに,多くの人たちがなかなか心電図を“味方”にできないのはなぜだろうか?
「胸痛ならST変化に着目すれば良い」
「動悸を訴えたら頻脈がないか見る」
「めまい・ふらつき・息切れなら徐脈チェック」
といった型にはめられた考え方や,“図説”よろしく,「この疾患ならこの心電図」と説く書籍が目立つためでないか(「~マニュアル」や「ポケット~」,「ここだけ・これだけ~」などが典型的なものだ)。こうした従来型の心電図教育法では限界があり,そのような本でいくら勉強しても“心電図の壁”を克服することは難しいと思う。
筆者はこの状況を「数学」や「物理」の学習と近いものがあるように感じている。受験生だったときを思い起こして欲しい。
“こういう問題ならこの順でこう解く”─ こうした「パターン」をある一定数覚えると,自分が知っている範囲であれば答えることができるようになる。これは心電図の世界もまったく同じ。
「胸痛を訴える患者のST上昇型急性心筋梗塞」
「突然の動悸で受診した患者の発作性上室頻拍」
「めまいや息切れでやって来る患者の完全房室ブロック」
などは“お決まり”の「パターン」問題だ。いくらか“場数”をこなして,ちょっと慣れたら誰でもできるだろう。
ただし,難関校の試験問題は往々にして“その先”が問われる。より本質的で深い理解をしていない者は,まったく経験したことのないタイプの問題には太刀打ちできないことが多い(だから“難関校”なわけだが)。同様にリアル・ワールドで遭遇する心電図も“何でもあり”という意味で非常に“難関”なのだ。実臨床では,「気分不良・めまい」を契機に発症したり,時には「無症状」の心筋梗塞,「失神」してしまう発作性上室頻拍など非典型例が溢れている。しかも,いつ・どんなタイミングでやって来るかもわからない。そんな“難問”に対応するには,「漏れのない系統的な心電図判読」と「所見に対する“本質的”な理解と解釈」が必要ではないだろうか。心電図を“味方”につけるには,この両輪がそろわないと絶対に不可能で,「~と言えば~」のような“1:1対応”的な考えでは一生涯「苦手意識」を背負うことになるだろう。
この筆者の持論を“証明”すべく,他書とは一線を画す内容で心電図や不整脈のテキストをこれまでに作成してきた(処女作から数えて既に9作品を世に送り出してきた)。
今回の書籍は10冊目だが,スタンスはブレていないつもりだ。まず, どんな心電図にも先入観なく向かい合い, 異常所見をすべて拾い上げる。“練習”するほどスピードは速くなるだろう。基本,筆者はどんな心電図を見せられても,“瞬間”, 1秒とかからない。
その上で目の前の患者情報を“乗せて”心電図を解釈しよう。心電図を「見て」,患者を「診る」ときにどう「考える」のか,Dr.ヒロ流をとくとご覧あれ。
このプロセスを地道にくり返すことで,いつしかホンモノの“心電図力”が身につくだろう。この書籍がそのお役に立てれば,筆者にとっては望外の喜びである。
本書刊行にあたっては,日本医事新報社にお世話をいただいた。まず,週刊誌での“すきドリ”連載を担当してくれた嶋野裕介氏に感謝である。著作に関して一切の妥協を許さない筆者の姿勢から,多大なご迷惑をかけたことは容易に察しがつく。
「毎週締切り」という非常にタイトなスケジュールにもかかわらず, 校了日のギリギリまで,平均して4~5回,多いときは7~8回の校正をくり返したこともある。しかも,たった一度ではなく,1年間の全原稿がその調子である。途中から,嶋野氏は管理職の業務ほか多忙であることを知ったが,校正頻度をゆるめなかったのは,いつもながら反省した。でも,確固とした記憶として,一度たりとも嶋野氏以外と編集・校正のやりとりはしなかった。各所との交渉・調整が大変だったと思うが,筆者の“特性”をよく理解し,気持ち良く作業を進めさせてくれた。できれば,また近いうちに別の切り口の連載を手助けしてもらえないかと秘かに思っている(笑)。
そして,連載にいったんの区切りをつけた令和2年末から,書籍化の担当をしてくださった村上由佳女史も“第2の功労者”として感謝の念を申し上げたい。彼女は,同年中に分担執筆の一著者として参加した別の書籍を担当しており,その敏腕ぶりは知っていた。ただ,その編集作業に“水を差す”ほど,筆者の書籍化の際の作業が遅かった。連載をやり切った達成感,他の執筆業務との兼ね合い,その他,なかなか言葉にしづらい案件も重なり,1~2カ月間まったく本書の業務にタッチできなかった。
そんな中でも辛抱強く見守って下さり,いったん動き出したらまたいろいろと要望の多いわがままな筆者の要求にも真摯に対応してくれた。10冊目という,記念すべき“作品”が十分に納得できるレベルの自信作に仕上がったのは,村上氏のおかげと言っても過言ではないだろう。
閑話休題。
この書籍は令和3年の春に皆さまのお目にかかることになる。最後の最後に質問。春先にどんな歌を聴くか。
筆者は高校生の時からスピッツが,大,大,大好き─ 個人的には,すべてのバンドで“一番”だとさえ思っている。
数ある名曲の中,春に向かう時期に筆者は『春の歌』をheavy rotationしている。何度も歌詞を読み直す。草野マサムネの優しい歌声,そして歌詞がいい。辛かったこと,甘酸っぱいことや,夢に向かって一心不乱だった日々,すべての自分の記憶たちに曲が妙にシンクロしている気がする。
『春の歌』 (作詞・作曲:草野正宗)
重い足でぬかるむ道を来た トゲのある藪をかき分けてきた
食べられそうな全てを食べた
長いトンネルをくぐり抜けた時 見慣れない色に包まれていった
実はまだ始まったとこだった
「どうでもいい」とか そんな言葉で汚れた
心 今放て
春の歌 愛と希望より前に響く
聞こえるか? 遠い空に映る君にも
平気な顔でかなり無理してたこと 叫びたいのに懸命に微笑んだこと
朝の光にさらされていく
忘れかけた 本当は忘れたくない
君の名をなぞる
春の歌 愛も希望もつくりはじめる
遮るな 何処までも続くこの道を
歩いていくよ サルのままで孤り
幻じゃなく 歩いていく
春の歌 愛と希望より前に響く
聞こえるか? 遠い空に映る君にも
春の歌 愛も希望もつくりはじめる
遮るな 何処までも続くこの道を
NexTone許諾番号PB000051202号
今まで事あるごとに,何十曲,何百回とスピッツの歌に感動し,励まされた。この曲もそのひとつだ。本当に数え切れないほど素敵な“詩”も熟読してきた。
もう,それからだいぶ時が過ぎ,自分も中年になった。東京から関西に移住して,だいぶ時間もたった。誰にどんなことを言われようとも,支えてくれる貴重な家族も得た。それでも,なかなか自分の思い通りにいかない現状に押しつぶされそうになったことも,一度や二度ではない。そこかしこに“障壁”も感じていた時期だってある。加えて, 令和2年は, まさに新型コロナウイルス一色の年であった。
でも,今も筆者の心の中は,日々新しい何かを求める情熱であふれている。コロナウイルスの“嵐”が去るのはもうじきだ。日本,いや世界のすべての人が,新しい一歩をまた踏み出そうとしている。かがんで蓄えたエネルギーでさらに一段高くジャンプするのだ。『春の歌』はそんな状況にぴったりだ。
人生,まだまだこれから。筆者にとっても,そんな人生の新しい“1ページ”を祝うテキストとして本書をお届けしたい。
令和3年3月
寒日に夏めいた暖かさが交差する京都より
Dr.ヒロこと杉山裕章
目次
Dr.ヒロ’s 心電図判読メソッド
問題編
解答編
索 引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:42.1MB以上(インストール時:87.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:168.5MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:42.1MB以上(インストール時:87.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:168.5MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784784962822
- ページ数:281頁
- 書籍発行日:2021年5月
- 電子版発売日:2021年5月14日
- 判:B5変型
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。