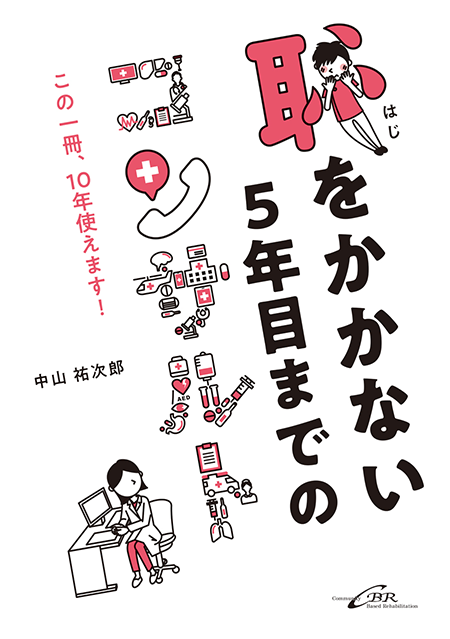- m3.com 電子書籍
- シービーアール
- 恥をかかない5年目までのコンサルト~この一冊、10年使えます!
商品情報
内容
「おめーなぁ! それじゃあ何にもわかんねぇよ」。コンサルトをした際に、先輩医師からこんな激烈なお叱りを受けた経験はありませんか。または、せっかく丁寧に情報を伝えたつもりなのに、「何様のつもり?」「長いけど伝わらない」などと辛辣なフィードバックを受けることもしばしば。そうこうしていくうちに「コンサルトなんてやりたくない」「どうして上の先輩がやってくれないの」と、コンサルトに苦手意識をもつ初期研修医が増えるのも無理はありません。
そんなコンサルトに苦手意識をもつ若手医師のみなさんに朗報です。このたび、医師であり、小説家である、中山祐次郎先生が「10年先まで使えるコンサルト本」をコンセプトに、コンサルトの極意をお伝えします。
本書では、どんなコンサルトをし、どんなコンサルト状を書けばよいか、また、どんなタイミングでコンサルトをすればよいかを小説家という一面を持つ中山祐次郎先生が極限までわかりやすく解説しています。また、文章のプロである中山先生だからこそ、読み物としても大変おもしろい。さらに、スペシャルアドバイザー(通称「ブレイン」)として、読者と近い感覚をもった1~4年目の医師に入ってもらい、忌憚のない意見をもらい何度もブラッシュアップを重ねて本書が完成しました。中山先生曰く「売れるに決まってる。だって、どうしても必要なのにこれまで無くて、内容がとてもいいんだから」。
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
はじめに
中山祐次郎
***
朝から湿り気のまじった空気の中、国産中古の愛車を飛ばして13分、いつもの病院駐車場へと着く。車を降りると、初夏に独特の陽射しが、それも梅雨の前の希望に満ち溢れた陽射しが目を射す。
最近夜泣きが減っていたというのに、昨夜は0時きっかりに赤ん坊が泣き出したのであった。15分待っても寝ないのでミルクをあげ、抱っこひもでゆらゆらと揺らす。広くはない部屋の端から歩き、斜めに一番遠い端まで歩く。真っ暗なので、無印良品のソファに足をぶつけないよう注意しながらだ。端までたどり着くと、また向こうの一番端まで歩く。腹腔鏡手術の無理な姿勢で痛めた腰が、ズキズキと痛む。明日はロボット手術だから座ってやれるものの、なるべく睡眠時間は確保したい。
部屋ウォーキングが30往復を超えた頃、ベビーが一度大きなあくびをした。チャンスとばかり、畳み掛けるように31 往復目を踏み出す。
ベビーが寝たのは、結局1時を過ぎてからのことだった。油断してすぐにベビーベッドに置くと「背中スイッチ」が発動して起きてしまい、恐ろしいことに振り出しに戻る。1時間ぶりに座ると、足が疲れ切っているのが初めて感じられた。
朝の医局で大急ぎで白衣をはおり、病棟へ。7時半からの回診に間に合いホッとする。8時過ぎに回診は終わり、それから患者さんからの問い合わせ電話が2件。他科の患者で手術にヘルプに入った人を診に行く。ロボット手術のための指示を出しに、手術室へ。シミュレーターで少し手を動かしウォーミングアップもしておく。腰は痛い。患者は9時入室だ。朝食はその直前に取ろう。そう思い急ぎ足で行った売店でサンドイッチを買うと、院内用iPhoneが鳴った。
「もしもし、お忙しいところすみません。研修医の〇〇ですが、救急外来に腹痛の患者さんがいまして……」
***
皆さん、初めまして。消化器外科医の中山祐次郎と申します。2006年に鹿児島大学医学部を卒業し、以来15年、外科医として働いてきました。
冒頭の、いち中堅外科医の生活を描いた小説風の文章に驚いた方もおられるかと思いますが、じつは私、小説家としても働いています。2021年4月にテレビ朝日系列でドラマ化した「泣くな研修医」シリーズは、実に38万部を超える大好評をいただいています。ありがとうございます。
医師として、小説家として、若手医師の皆さんにどうしても伝えたいものがある。そう思ったのは2018年のことでした。当時、臨床を一年休んで京都大学公衆衛生大学院の学生をしていた私は、この本の編集者、横尾さんと出会います。メガネ姿の真面目そうな横尾さんと何度も何度も、何時間も「いまの若手医師にとってどうしても必要で、しかもまだ無いものはなにか」を長時間にわたり話すうちに、「コンサルトの本」を作ろう、となったのです。
病院でいつも困っている「コンサルト」について、総論、つまりどんなふうにコンサルトをし、どんなコンサルト状を書くか。そして各論、つまり胸痛で心筋梗塞を疑ったら最低限何を検査してどのタイミングで怖い怖い循環器内科医にコールするか。それを解説した本は、これまでどこにもありませんでした。
冒頭の文章では、若手医師の皆さんに中堅外科医の生活を少しでもご想像いただければと書いたものです。こんな、バタバタしている中堅医師へのコンサルトですから、伝える技術が必要なことは間違いありません。それを、「コンサルトする側」「される側」の豊富な経験を踏まえて、皆さんになんとかお伝えしたい。そして、忙しく、怒られることの多い臨床現場を少しでもストレスフリーにしたい。そんな気持ちで書きました。失敗して流す涙はいらない、そう私は思っています。
この本は、中山が以下の5点に強いこだわりを持って作りました。
1.総論は、中山がすべて書く
中山がおびただしい数の失敗の上に学んできたコンサルト・スキルを、作家の筆で「面白く読める」ものにすることにこだわりました。あかんコンサルト、最高のコンサルトなど……何度でも読みたくなる、そんな総論とコラムになりました。時間がなくてもざっと最後まで読める本、が本書です。
2.各論は、コンサルトを受ける学年(中堅)の医師にお願いする
重鎮医師ではなく、研修医や若手医師から直接電話をもらう学年の医師に書いてもらうことにこだわりました。「現場で何が求められるか」をもっとも端的に伝えてくれることになります。
3.中山の知り合いの、親しい友人医師にお願いする
同時に、知り合いの医師(大学時代からの友人など、付き合いの深い友人ばかり)に依頼することで、もらった原稿に対して1ミリも遠慮のないツッコミをしました。「これ、どういうこと?」「ここ、わかりにくいです」など、領域によっては10回以上書き直してもらったところも。普通の医学書では、2~3往復が普通だと思いますし、遠慮がありますが、本書ではとにかくしつこくやり取りをしました。そう、刀鍛冶が刀を何百回も叩いて鍛えるように。
4.「10年後も通用する」をモットーに
各論で、私が各執筆者のドクターたちにお願いしたこと。それは、「10年後も通用する内容にして!」ということでした。医療体制が変わり、検査が変わり、エビデンスが蓄積されて行ったとしても、その症候と疾患を貫く真実はあるはずだ。そう中山は考え、こうしつこくお願いをしました。
5.磨き上げる
この本は、内容がほぼ出来上がってから、3人の「ブレイン」と呼ばれる若手医師の皆さんによってじっくりとあらゆる角度からチェックされ、アイデアが出されました。たとえば各論の最初のフローチャートは、ブレインのご意見で追加されたコンテンツです。3人の1~4年目(当時)のブレイン医師たちが、荒削りな本書を丁寧に整え、ブラッシュアップをしてくださいました。
これら5点にこだわった結果、この本を作るのになんと3年もかかってしまいました。
ですが、執筆者の先生・ブレイン医師・編集者の横尾さんとともに作り上げた今。
私は金曜深夜の医局で、静かな興奮に満たされています。
この国の8000を超える病院で、30万人以上の医師が何十万回、何百万回もなんとなく行ってきた「コンサルト」という行為。これが、いま音を立てて次のステージへと進んでいくのです。何を大袈裟な、と言う方もいるでしょう。しかしコンサルトとはコミュニケーションのこと。コミュニケーションが円滑でない医師たちによる治療が、どうして最善のものになりえるでしょうか。この本は、医師たちのぎこちないコミュニケーションを滑らかにする潤滑油のように、日本全国の病院へと行き渡っていきます。
そして、本書で取り上げられなかった症状たち。本書が医師たちにしかるべき評価を受けたなら、改訂版として年々進化していくことでしょう。
この場をお借りして、ブレインとして本書を磨き上げてくださったkokupo先生、さとみな先生、荒木貴裕先生には心より感謝と御礼を申し上げます。編集者として多数の執筆者の先生方に何度もやり取りをしていただき、文字通り数え切れない回数の打ち合わせ・メール・電話をした株式会社シービーアールの横尾直享さん。本書は必ずやロングセラーになります、これからもよろしくお願い致します。そして各論を執筆いただいた中山の大切な友人の皆様に、心からの御礼を申し上げ、謝辞とさせていただきます。
2021年5月
初夏のふくしま、医局のデスクにて
目次
執筆者一覧
登場人物紹介
第一章 コンサルトのキホン
1–1.なぜコンサルトは難しい?
対話:ある日の医局風景①
コンサルトは誰も教えてくれない
本当は難しくないコンサルト
1–2.コンサルト,電話の秘訣
対話:ある日の医局風景②
電話の極意① 結論から言え
電話の極意② 何をして欲しいか言え
電話の極意③ 短く言え
対話:できる電話コンサルト
1–3.コンサルト依頼状の秘訣
対話:ある日の病棟風景
コンサルト状の極意① 失礼がない
コンサルト状の極意② 必要な情報がある
コンサルト状の極意③ 長過ぎない
1–4.やってはいけない,コンサルトの禁忌
禁忌① コンサルトするとキレる先生
禁忌② 患者さんからの評判が悪い先生
禁忌③ 対応が遅い先生
1–5.コンサルトにまつわるけっこう微妙なハナシ
診に来てくれたとき,診察に立ち合うかどうか問題
対面で詳しく話したとき,依頼状書くべきか問題
コンサルト後、改善しないときどうしようか問題
case1 胸痛で循環器内科
case2 腹痛で消化器内科
case3 腹痛で消化器外科
番外編① 緊急手術で麻酔科
case4 腹痛で産婦人科
case5 頭痛で脳神経外科
case6 貧血で血液内科
第二章 症状別 実践で役立つコンサルト
case7 呼吸苦・呼吸不全で呼吸器内科
番外編② COVID–19 肺炎診療
case8 整形外科コンサルトに必要な「きず」の見方・伝え方
case9 骨折,捻挫,脱臼で整形外科
case10 高齢者の転倒で整形外科
case11 関節痛でアレルギー膠原病内科
case12 乏尿・無尿(急性腎障害)で腎臓内科
コラム1 最低のコンサルト
コラム2 「御侍史」「御机下」の本当の意味
コラム3 今スグ使える,日本語を丁寧に言い換えるリスト
コラム4 「誰にコンサルトするか問題」―地雷・ドボン先生回避に看護師を攻略せよ
コラム5 最高のコンサルト
コラム6 ベテラン外科医vs. 若手消化器内科医のアッペバトル
コラム7 #1 #2プロブレムリストは必要?
結びに代えて 「学年が上がるとコンサルトは適当でもいい」説
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:4.4MB以上(インストール時:10.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:17.6MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:4.4MB以上(インストール時:10.8MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:17.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784908083624
- ページ数:143頁
- 書籍発行日:2021年6月
- 電子版発売日:2021年6月26日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。