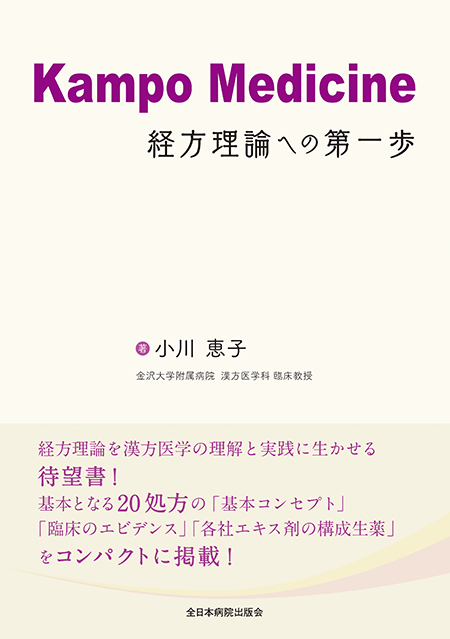- m3.com 電子書籍
- Kampo
- Kampo Medicine 経方理論への第一歩
商品情報
内容
基本となる20処方の「基本コンセプト」「臨床のエビデンス」「各社エキス剤の構成生薬」を巻末にコンパクトにまとめています!
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
はじめに
本書は,漢方医学の診断に必要な知識を解説し,特に診察法について詳細に説明することによって,実際に診療に応用できることを目的としています.漢方医学では,四診による患者さんの綿密な観察が処方決定に非常に重要だからです.
また,本書には「経方理論」への橋渡しの役割もあります.経方理論は,江部洋一郎先生によって構築されましたが,江部先生は天才で頭の回転が速いことから,『経方医学』を当初から読んで理解するのは難しい部分もあります.そのため,『経方医学』を読む前の知識を網羅したつもりです.
後漢末(紀元前200 年頃),張 仲景により『傷寒雑病論』が編纂され,宋代(11 世紀)に『傷寒論』と『金匱要略』に再編され,以降,数多くの注釈書が著されています.日本では,中国系伝統医学は漢方医学として独自の進化を遂げ,江戸時代には吉益東洞が万病一毒説と古方『傷寒雑病論』への回帰を掲げ,古方派が誕生しました.さらに昭和初期に入り,西洋医学と同化させるために概念の意味も変化し,口訣に基づく処方決定が主体となり,実際の臨床で容易に処方できることが重視されて発展してきました.体系として『傷寒論』を明確に説明できる理論は,江部洋一郎先生が「経方理論」を確立するまではありませんでした.
私は,ある程度漢方医学を勉強した後,漢方医学の治療を自由自在に行うためには「概念」が重要だと感じていました.その頃、漢方医学を思考する際に用いている「概念」は論理的に曖昧であり,流派によって微妙に異なり,思考するのに限界がありました(現在使われている概念が間違っているというわけではありません).特に現代では,高齢化や医学の進歩による医原性の病態も出現し,より複雑化する現実的な問題や疾患に取り組まなければなりません.明確に定義された概念をもたずに病態把握をし,処方の自由を得ることはできないと思っていたとき,「経方理論」に出会いました.
経方理論の特徴は以下のとおりです.
①流れを重視
人体の外殻と胸・心下・膈などの構造を明らかにし,気がどこで産生され,どこをどのように流れるかを具体的に示している.
②概念の明確な定義
今までに曖昧に用いられることが多かった概念を明確に定義し(気血津液の定義を参照),不要な概念は使わなくても診断・治療できるように構築されている.
③『傷寒雑病論』解説による理論の証明
『傷寒雑病論』の簡潔な条文と処方の背後に内在する生理(機能的な人体構造論),病理および薬理の体系を用いて,全処方を説明できている.
④生薬の役割の明確化
経方理論の薬論は,『神農本草経』と『名医別録』に基づき,しかも経方理論からみた役割が具体的に明確に述べられている.⑤人体の生理に則っている
日常的にごく普通に見られる人体の生命現象から普遍的な法則を導き出している.例えば,胃気の上衝のように,気の循環を前提とし,どの部位でどのようにブロックされるとどのような病態になるかということを明確にしている.
江部先生の「漢方における処方の自由は,経方理論の上にのみ可能であるというのが,われわれの信念である.」という言葉に,私は付け加えたいと思います.
なぜその漢方治療をするのかについて,きちんとした説明ができる理論を手に入れることができれば,他の分野の専門家ともっと協力できるようになるでしょう.経方理論は,そのような横断的な関係を築くための理論になるでしょう.そして,この方向性こそがより多くの患者さんの役に立つでしょう.
また,巻末では,主要な処方の使い方のポイントと,各会社による構成生薬の量の相違,処方する際に知っておくと良い研究結果をまとめました.文量が多くなってしまっているため,必要最小限にとどめましたが,ご自分でほかの処方についても同様にまとめてみても良いかもしれません.
最後に,この本を書くにあたって,ご指導頂いた故江部洋一郎先生,諸先生方,秘書の皆さん,金沢大学漢方医学科の皆さん,予定よりも時間がかかったにもかかわらず優しく見守り,校正して下さった出版社の方々,そしていつも温かく見守ってくれ,挫折しそうなときには叱咤激励してくれる家族や友人に感謝申し上げます.
2020年5月
小川 恵子
目次
0.はじめに
0-1 漢方医学的診察とは
0-2 四診の順番
0-3 知っておくべき漢方医学的概念
1.望診
1-1 見た目が大切
1-2 望診を構成する要素とその表現
2.聞診
2-1 聞く,とは?
2-2 聞診の要素とその表現
3.問診
3-1 何を尋ねるのか?
3-2 問診からわかること
4.切診
4-1 切診とは?
4-2 脈診
4-3 腹診
column短脈と胆気不足について
5.生薬
5-0 生薬の基礎知識
5-1 四気
5-2 五味
5-3 気の生薬
5-4 血水(津液)の生薬
6.判断する:実際に処方してみよう
6-1 判断に必要なこと
6-2 経方医学的考え方
6-3 判断の例
7.漢方薬の副作用
8.感染症の漢方治療―初期のかぜを中心に―
column 『傷寒論』が書かれた時代の感染症
column COVID-19
column スペイン風邪
巻末 基本の20処方
生薬および製剤一覧・索引
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:7.0MB以上(インストール時:17.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:27.9MB以上
AndroidOS 最新バージョンのOSをご利用ください
外部メモリ:7.0MB以上(インストール時:17.5MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:27.9MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784865192759
- ページ数:208頁
- 書籍発行日:2020年7月
- 電子版発売日:2021年7月21日
- 判:A5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。