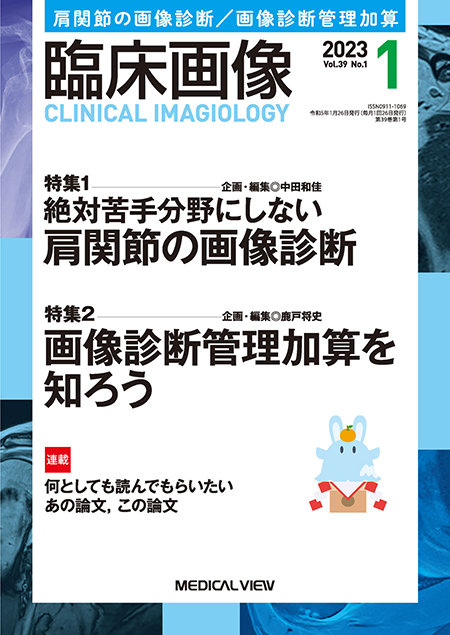- m3.com 電子書籍
- 雑誌
- 臨床医学:その他
- 臨床画像
- 臨床画像 2023年1月号 特集1:絶対苦手分野にしない 肩関節の画像診断/特集2:画像診断加算を知ろう
商品情報
内容
肩関節専門医が画像診断に期待すること
肩関節MRI読影のための必須事項
腱板損傷 ほか
≫ 「臨床画像」最新号・バックナンバーはこちら
≫ 臨床画像(2023年度定期購読)受付中!
※都合により,紙版の誌面と異なり割愛される箇所があることがございます(「肩関節の解剖」(p6〜16)は未収載となっております。).
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
特集1:絶対苦手分野にしない 肩関節の画像診断
序説
肩関節は解剖が複雑で,その機能,疾患,撮影方法などを理解して読影することは敬遠されがちです。骨軟部領域を専門としない画像診断医にとっては適切なトレーニングの機会がない,レポートの内容にかかわらず臨床医からのフィードバックがないなどの状況が苦手意識に拍車をかけていると思われます。本特集はすでに肩関節に対して苦手意識のある画像診断医の先生方,これから肩関節の画像診断に取り組む若手画像診断医を対象としました。
胸部や腹部ではモダリティごとの読影の手順がそれぞれの読影医にあるように,本特集を通じて肩関節全体を評価する方法を身につけることを目的にエキスパートの先生方に各項目を担当していただきました。臨床で遭遇する頻度の高い基本的な疾患が繰り返しさまざまな観点から解説されています。エキスパートの先生方の,診断の手順やコツ,必ずチェックすることにしている読影のポイントがちりばめられています。また,関節MR造影(MRアルトロ)については施行しない施設も多いため,通常MRIでの所見が中心となっており,日々の読影の際に参考になると思います。練習帳のようなつもりで活用していただき,自分の読影方法と解説を対比させることで,少しでも肩関節の画像診断に対する苦手意識が少なくなることを願います。
最後に,限られた誌面のなか,本特集の趣旨に沿い,素晴らしい原稿をご執筆いただいた先生方にこの場を借りてお礼申し上げます。
中田和佳
特集2:画像診断管理加算を知ろう
序説
本企画は「画像診断管理加算を知ろう」と題し,画像診断管理加算の歴史,算定要件,取得からその維持における工夫,種々の問題点,また今後の展望について幅広く考えていくものです。
画像診断管理加算(特に画像診断管理加算3)は読影,撮像指示,被ばくなどの管理を行い,画像診断業務の質の向上を目指すものです。誕生から四半世紀以上が過ぎました。放射線診断医にとっては画像診断管理加算の取得や維持は,病院経営に寄与できることで病院内における放射線診断医のプレゼンスを示すことができます。
一方,全国的にみても放射線診断医は数が少なく,現場は慢性的なマンパワー不足に常に悩まされています。特に画像診断管理加算2以上では,翌営業日までに80%以上の読影完了やそのほかさまざまな要件が課せられています。そのため,病院経営上の理由などから生じる画像診断管理加算の無理な取得や維持は,放射線診断医の過重労働につながるという弊害も懸念されています。
今回,画像診断管理加算の歴史や今後の展望を語るだけでなく,市中病院や地方の大学病院における画像診断管理加算の取得・維持のための工夫や苦労などをさまざまな視点から語っていただきます。
まず,順天堂大学 放射線診断学講座の隈丸加奈子先生と内川 慶先生からは,1996年から開始された画像診断管理加算誕生の経緯とその歴史・変遷,そして2022年の改定の要点をご紹介いただきます。兵庫県立尼崎総合医療センター 放射線診断科の金柿光憲先生からは,市中病院の立場から画像診断管理加算2取得への取り組みや維持における工夫,その問題点をご紹介いただきます。また,福井大学医学部 放射線医学の小坂信之先生と辻川哲也先生からは,地方の大学病院の立場から画像診断管理加算3取得への取り組みや維持における工夫,その問題点をご紹介いただくだけでなく,その打開策をご提案いただいています。最後に,診療報酬に詳しい国立国際医療研究センター国府台病院の待鳥詔洋先生からは画像診断管理加算の考え方や課題,今後の展望を語っていただきます。
いずれの記事もさまざまな立場,視点から画像診断管理加算を語っていただき,画像診断管理加算を再考できる大変充実した内容になっていると確信しております。また,若手の放射線診断医の先生においては画像診断管理加算を詳しく知るよいきっかけになると思います。
私見ですが,画像診断管理加算は画像診断業務における質の向上,また病院の収益に貢献できる面でとても重要なものだと考えております。しかし一方で,画像診断管理加算の無理な取得や維持は放射線診断医への過重な負荷になり,「諸刃の剣」になりうるとも思っています。この制度にはまだ不十分な面が多くあるようにも感じています。本稿をとおして,改めて放射線診断医が画像診断管理加算の取得・維持における工夫を考えるだけでなく,その問題点を考え直し,声を上げていくきっかけになればと思っております。
鹿戸将史
目次
特集1:絶対苦手分野にしない 肩関節の画像診断 企画編集:中田和佳
序説 中田和佳
解剖 米永健徳
肩関節の超音波所見 西頭知宏
肩関節専門医が画像診断に期待すること 笹沼秀幸
肩関節MRI読影のための必須事項 佐志隆士
腱板損傷 福庭栄治
上腕二頭筋長頭腱病変腱板疎部病変 福田健志
不安定肩 天野大介
凍結肩 常陸 真
肩関節炎 杉本英治
特集2:画像診断加算を知ろう 企画編集:鹿戸将史
序説 鹿戸将史
画像診断管理加算:歴史と今回改定について 隈丸加奈子
市中病院における画像診断管理加算2取得までの取り組み 金柿光憲
大学病院での画像診断管理加算3の取り組み 小坂信之
画像診断管理加算のphilosophyと今後の課題 待鳥詔洋
連載
・何としても読んでもらいたい あの論文,この論文
[第6回] 美しく居心地のよい心臓画像の論文 天野康雄
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:30.4MB以上(インストール時:63.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:121.7MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:30.4MB以上(インストール時:63.1MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:121.7MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784008004301
- ページ数:109頁
- 書籍発行日:2022年12月
- 電子版発売日:2022年12月22日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。