- m3.com 電子書籍
- 臨牀消化器内科 2018 Vol.33 No.1 NASH 2018
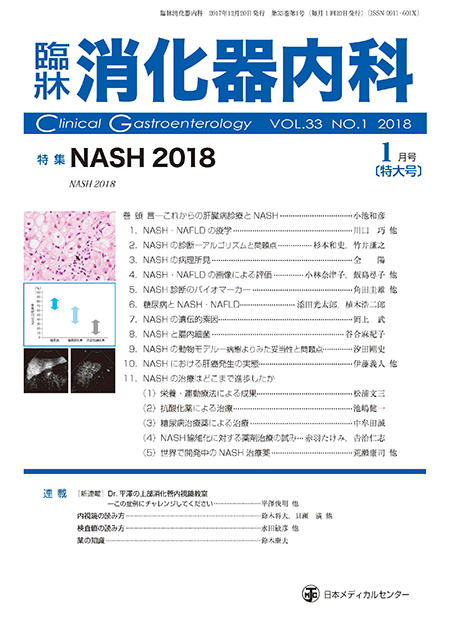
臨牀消化器内科 2018 Vol.33 No.1 NASH 2018
商品情報
内容
【特集】NASH 2018
・NASH・NAFLDの疫学
・NASHの診断―アルゴリズムと問題点
・NASHの病理所見
他
>『 臨牀消化器内科』最新号・バックナンバー
序文
巻頭言
日本肝臓学会が創立されてから,2018年で54年目である.創立以来,肝臓学会の発展は,ウイルス肝炎研究の進歩と歩を一にしてきた.ご存じのように,5つ目に発見されたC型肝炎ウイルス(hepatitis C virus;HCV)の発見後,ウイルス肝炎研究と薬剤開発は急速に進歩してきた.ことに,この3~4年の治療薬(抗ウイルス薬direct‒acting antiviral;DAA)の進歩は著しい.治療例の95%以上でHCV排除が達成できる時代になってきた.では,ウイルス肝炎については,もう片付いてしまい,やるべきことはないのであろうか?あるいは,これから肝臓医がやるべき仕事はなくなってしまうのであろうか?
答えは,むろん,どちらも「否」である.前者に関しては,HCVが排除されても肝臓病がすぐに治るわけではない.発癌リスクは残り,場合によっては高留まりする.継続した診療(ケア)が必須である.B型肝炎は,まだウイルス排除もできない.
後者については,「勝って兜の緒を締めよ」である.C型肝炎に打ち勝ったと気を緩めてはならない.新たな敵がすでに現れている.HCVもB型肝炎ウイルスもいない「非B非C型肝細胞癌(肝癌)」が,勢いよく増えている.わが国の初発肝癌における非B非C型肝癌の占める割合は30%を超え増加中であり,推定される患者実数も,1991~2010年の20年間に5倍以上に増加している.最近,増加が言われている膵癌や大腸癌でも,2倍強の増加であることを考えると,非B非C型肝癌の急増は看過できない.
非B非C型肝癌はヘテロな疾患の集合体と考えられるが,そのメインは,なんと言っても非アルコール性脂肪肝炎(nonalcoholic steatohepatitis;NASH)である.本誌「臨牀消化器内科」におけるNASHの特集は15年間で4回目となる.2003年,2007年,2013年,そして今回の2018年である.本誌では,同一のテーマで特集するときにはもっと間隔を開けるのが通例であるが,NASHに関する最近の進歩は著しく,また読者の興味も強いということで何度もの特集を組んでいる.
わが国におけるNASH患者数については,正確な算出がまだなされていない.米国のような肥満国家に比べると平均BMIは低い.しかし,日本人を含むアジア人では,軽度のBMI上昇でも代謝系に影響が出やすいことも言われている.NASHの成因に関しては多くの動物モデルが作製され研究が進められているが,まだ不明な点が多い.NASHは複数要因による症候群と考えられるが,最近のGWAS(ゲノムワイド関連解析)によるSNP(一塩基多型)解析によってPNPLA3を含むいくつかの遺伝子の多型性が非アルコール性脂肪肝疾患(nonalcoholicfatty liver disease;NAFLD),NASHへの感受性を規定することが明らかにされてきている.
NASH診断上の大きな問題点は,酒を20~30g/day以上飲むと,NASHの診断がつかないことである.さらに,一日飲酒量20g以上,60g以下という「そこそこ飲む」人たちは,NASHともASH(アルコール性脂肪肝炎)とも診断がつけられず,現在のところ正式な病名がない状態である.わが国での非B非C型肝癌症例の多数例解析では,このような「病名のない肝癌」が非B非C型肝癌の約半数を占めていることも明らかになっている.これらの肝癌病態解明とともに,NASH/ASHの病名も変更するのが望ましいと考える.
肝癌の合併とその頻度については,米国からはNASH肝硬変での肝癌発生はC型肝硬変の半分程度というデータが出ている.米国ではC型肝炎での発癌率は日本より低い(患者年齢層,感染期間の差などが要因とされている)ので,日本でのNASH肝硬変での肝癌発生はC型肝硬変のおよそ1/3程度ではないかと思われる.日本での前向き観察でも,この程度の肝発癌頻度のようである.
治療薬も,現在,多くの治験が行われているが,第Ⅲ相臨床試験まで行っているものは多くはない.脂肪肝を軽減するだけならビタミンEでもよい.肝線維化,肝細胞風船化,NASH を根本的に治す薬の上市が待たれる.
小池 和彦
目次
巻頭言
1.NASH・NAFLDの疫学
2.NASHの診断―アルゴリズムと問題点
3.NASHの病理所見
4.NASH・NAFLDの画像による評価
5.NASH診断のバイオマーカー
6.糖尿病とNASH・NAFLD
7.NASHの遺伝的素因
8.NASHと腸内細菌
9.NASHの動物モデル―病態よりみた妥当性と問題点
10.NASHにおける肝癌発生の実態
11.NASHの治療はどこまで進歩したか
(1)栄養・運動療法による成果
(2)抗酸化薬による治療
(3)糖尿病治療薬による治療
(4)NASH線維化に対する薬剤治療の試み
(5)世界で開発中のNASH治療薬
[連載]
Dr.平澤の上部消化管内視鏡教室―この症例にチャレンジしてください
SMT様の病変
内視鏡の読み方
終末回腸に多発する潰瘍・狭窄により再発性腸閉塞をきたした回腸結核の1例
検査値の読み方
自己免疫性肝炎における自己抗体―抗平滑筋抗体測定の意義について
薬の知識
クローン病治療薬ブデソニド(ゼンタコート®)
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:156.1MB以上(インストール時:339.4MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:624.4MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:26.4MB以上(インストール時:66.0MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:105.6MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、M2Plus Launcherが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784888755027
- ページ数:140頁
- 書籍発行日:2017年12月
- 電子版発売日:2019年3月6日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:2
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※今日リンク、YNリンク、南山リンクについて、AndroidOSは今後一部製品から順次対応予定です。製品毎の対応/非対応は上の「便利機能」のアイコンをご確認下さいませ。
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍(iOS/iPhoneOS/AndroidOS)が必要です。
※書籍の体裁そのままで表示しますため、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。


