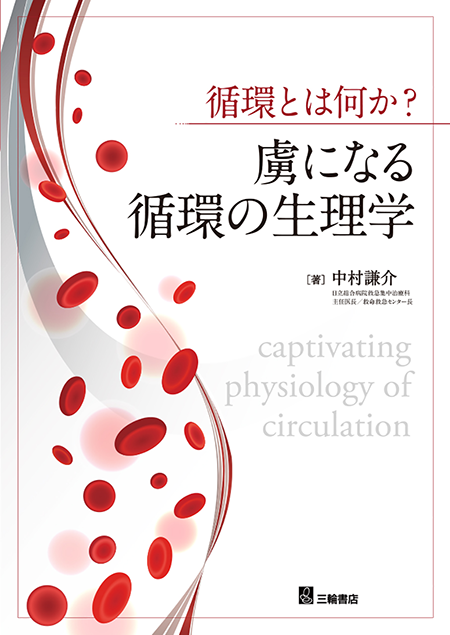- m3.com 電子書籍
- 臨床医学:内科系
- 循環とは何か? 虜になる循環の生理学
商品情報
内容
~循環とは何か?~
この普遍的ともいえる問いに自信をもって答えられる医療従事者は少ないのではないでしょうか。循環が大事とわかっていても何をもって循環となすのか、循環生理には生化学、解剖学、物理学などさまざまな学問が関わっています。
本書はその難解な循環の生理学をいまだかつてないほどに深くかつわかりやすく解説し、実臨床に必要となる循環の知識を楽しく勉強できるようにしたものです。経験豊富な救急集中治療医である著者が織りなす循環管理や循環作動薬の深淵もふんだんに盛り込まれ、循環の捉え方や考え方が変わります。循環に興味のあるすべての人に贈る極上の1冊 !
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
推薦の言葉
本書は、救急医療の現場の第一線で活躍されている中村謙介氏による最先端の循環管理の教科書で、集中治療を学ぶ初学者から熟練した臨床家に至るまで幅広い読者層に読み応えのある内容豊富な書物である。本書は中村氏独自の視点でもって、循環生理学を学ぶ者や集中治療の現場にいる者にとって混乱しやすい事柄を、明瞭にかつわかりやすくかみくだかれて説明されているという点では、他書にない特徴である。このため内容はきわめて豊富であるが、辞書として扱うような分厚い教科書とは異なり、本書は各章ごとに独立して書かれていながらも、一気に通読して読むことのできる読み手を飽きさせない読み物になっている。こういった教科書ができ上がるにあたっては、中村氏の明晰な頭脳と集中治療の第一線の現場での豊富な臨床経験に加えて、多くの現場の医療者に正しく有益な知識を伝えたいという、中村氏の教育者としての熱意の結果であるといえるだろう。
本書は救急医療、集中治療に携わる多くの医師、看護師、技師などの現場の医療者にとどまらず、医学部の学生が読んでさえもよく理解できるように細かい配慮をもって、理解しやすく書かれた幅広い読者層を想定した書物ではあるが、驚くべきは本書をじっくりと一度通読すると、基礎科学に関しては循環生理学や流体物理のかなり深い議論に対しても理解が深まり、また実践的な臨床に関しては、血行動態がかなり難しい心疾患の外科手術の周術期管理や人工心肺管理などにも、十分に対応できるような知識が包含されている点である。一切の難しい概念や記述を省いて書かれた本書には、自然と正しく実践的な知識が身につくようになっている点においては、驚異的な教科書といえる。
本書のはじめに中村流循環管理として、循環の2 要素を酸素運搬oxygen delivery と組織灌流perfusion に分けて説明しているが、この考え方は実は、流体の保有するエネルギーが運動エネルギーと内部エネルギー(ポテンシャルエネルギー)の総和から成り立つことに裏づけされ、たとえ高流量で早い流速で血液が流れていても(運動エネルギーだけ大きくても)、血圧が低ければ(内部エネルギーが低ければ)、血球が組織に酸素を引きわたすだけのエネルギー準位がないことになり、動脈系においては圧に相当する内部エネルギーの割合が大きいために、perfusion を確保するため、まずは血圧を一定レベル以上に保つ管理をするべきという、実践的なメッセージがこめられている。
中村氏は情熱的なすぐれた臨床医であるだけでなく、若手の育成に心をくだかれる温かい教育者ではあるが、氏の人柄に直接触れる機会がない臨床家にとっても、基礎科学に支えられながら循環管理や薬剤の管理までも学ぶことのできる本書によって、待ったなしの集中治療現場にかかわる多くの医療者たちが、迷いなく自信をもって実践に臨めるよう、中村氏の情熱と叡智と経験の恩恵がもたらされることを心より望むばかりである。
2020年9月吉日
京都府立医科大学大学院医学研究科
心臓血管外科・心臓血管血流解析学講座
成人先天性心疾患センター
板谷慶一
目次
序章 循環を極めよう
1-1 循環とは何か
1 そもそも「循環」って何?
2 循環とは酸素運搬oxygen deliveryと組織灌流perfusionである
3 酸素だけで循環による運搬を代表させてよいのか?
第1章 循環の2要素を極める
1-1 酸素運搬oxygen delivery
1 酸素の絶対量CaO2を考える
2 酸素運搬(oxygen delivery)を考える
1-2 組織灌流perfusion
1 組織灌流(perfusion)を考える
2 臓器血流量と血圧の関係
3 各臓器のperfusion
4 カテコラミンを使うと血流が悪くなる?
5 血圧はどれくらいにすればよいのか?
6 Perfusionの指標は何か? →尿量
7 SvO2はoxygen deliveryの指標ではあるがperfusionの指標ではない
1-3 循環を読み解く
1 Oxygen delivery とperfusionを見る循環管理
2 もっとも大事なのは血圧
3 実際にoxygen deliveryとperfusionを見て考えよう!
4 どのようなときにショック→循環破綻を疑うのか
5 ショックへの具体的対応
6 Cryptic shockに循環の2要素から迫る
第2章 循環に関わる因子を極める
2-1 心拍出量と前負荷/後負荷
1 はじめに
2 前負荷と後負荷
3 前負荷と心拍出量―スターリングの法則
4 後負荷と心拍出量
2-2 静脈系の圧と循環を極める
1 静脈系の圧と循環
2 スターリングの式で考える肺水腫
3 Critical PCWP の変化
4 スターリングの法則で考える循環管理戦略
5 臓器うっ血とCVP
6 心不全管理ではさらに心仕事量を加味する
7 最終的に心拍出量はどれくらいあればよいか?
2-3 改訂スターリングの法則とグリコカリクス理論
1 膠質浸透圧COPをつめる
2 血管内皮細胞輸送のメカニズム
3 グリコカリクスとglycocalyx-junction-break model
4 改訂スターリングの法則
2-4 静脈還流venous return
1 静脈還流(venous return)
2 心臓が悪いと肺水腫を起こしやすいのはなぜ?
3 Unstressed volumeとstressed volume
2-5 血液と粘稠度
1 はじめに
2 粘稠度(viscosity)とは何か
3 血液の粘稠度の規定因子
4 粘稠度の測定?
5 毛細血管における赤血球の流れ方
6 血流における血管径と血液粘稠度
7 グリコカリクスの粘稠度に対する役割
8 粘稠度の循環への影響
9 輸血とoxygen delivery
10 結局ヘモグロビンはいくらで管理すればよいか
11 真に輸血すべきか否かはどのように見極めればよいか
第3章 循環作動薬を極める
3-1 昇圧薬(血管収縮薬と強心薬)
1 はじめに
2 昇圧薬
3 カテコラミンの作用機序
4 各昇圧薬の特性と使い方
3-2 降圧薬
1 降圧薬の基本
2 静注降圧薬
3 降圧薬のエビデンスとパラダイム
3-3 利尿薬
1 はじめに
2 循環作動薬としての利尿薬の位置づけ
3 各利尿薬の作用機序
4 静注利尿薬のレパートリー
5 利尿薬のエビデンス
6 浸透圧利尿薬のエビデンス
3-4 抗不整脈薬
1 抗不整脈薬
2 心臓の電気生理から考える不整脈診療
3 Vaughan Williams分類とSicilian Gambit分類
4 静注抗不整脈薬のレパートリー
5 抗不整脈薬のエビデンス
6 心房細動の治療戦略
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:29.0MB以上(インストール時:63.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:115.9MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:29.0MB以上(インストール時:63.6MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:115.9MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784895907026
- ページ数:256頁
- 書籍発行日:2020年10月
- 電子版発売日:2020年11月13日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。