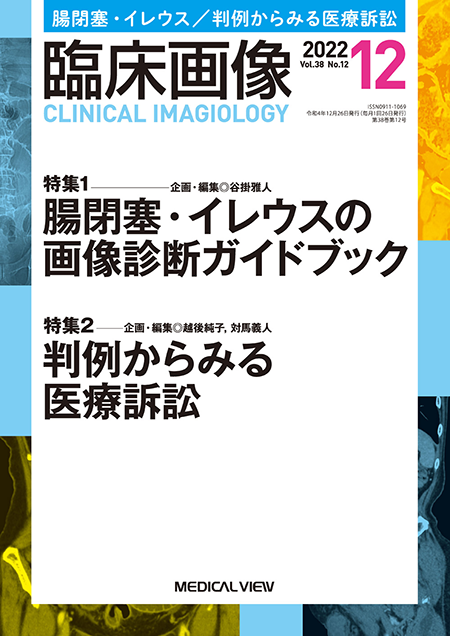- m3.com 電子書籍
- 雑誌
- 臨床医学:その他
- 臨床画像 2022年12月号 Vol.38 No.12 特集1:腸閉塞・イレウスの画像診断ガイドブック/特集2:判例からみる医療訴訟
商品情報
内容
序説
腸閉塞の開腹所見と治療
ほか
≫ 「臨床画像」最新号・バックナンバーはこちら
≫ 臨床画像(2022年度年間購読)受付中!
※本製品はPCでの閲覧も可能です。
製品のご購入後、「購入済ライセンス一覧」より、オンライン環境で閲覧可能なPDF版をご覧いただけます。詳細はこちらでご確認ください。
推奨ブラウザ: Firefox 最新版 / Google Chrome 最新版 / Safari 最新版
序文
特集1:序説
今回の企画,「腸閉塞・イレウス」の特集は,編集会議において「やれたら絶対におもしろいが実現は困難が伴う」と判断されたものだったそうです。そんな企画がなぜか私のもとに舞い込んできました。
腸閉塞,イレウス……古から知られ,かつcommonな疾患,治療方針を誤ると命取りになり,そして画像診断が有用な病態です。一方で,どこまできちんと診断されているか,と振り返ってみるといかがでしょうか。
私はしばしば開腹手術を見学しに行きますが,診断名は間違っていなくとも,画像からは想像のつかなかった状況を目のあたりにし,自分の診断の甘さ,底の浅さを痛感することが少なからずあります。そこから推察するに,腸閉塞・イレウスの画像診断の一番の問題点は,目先の画像診断のみで結論付けてしまい,実際の腸管がどのようになっているのかを想起するという,画像診断本来の目的がおざなりになっている所にあるのではないか,と考えました。今回の特集の実現が,その解決のきっかけになればと思い,引き受けさせていただくことといたしました。
構成は,できるだけ実用的に診療に沿った内容となるように心がけております。
実際にどうなっているのかを想起するためにはまず実物を知ることが必要です。そこで,日本医科大学 消化器外科 山田岳史先生らに依頼し,開腹所見,治療について述べていただき,術中写真を豊富に盛り込んでいただきました。
画像診断の第一歩は腸閉塞かイレウスかの鑑別,次いでその原因検索です。小腸については公立甲賀病院 井本勝治先生ら,山形大学 豊口裕樹先生に,大腸については那覇市立病院 又吉隆先生に十分に解説をいただきました。
さらに一歩踏み込んだ診断,特殊な背景下にみられるものについて,内ヘルニアの診断を昭和大学藤が丘病院 竹山信之先生らに,術後にみられるものを大分市医師会立アルメイダ病院 松本俊郎先生らに,小児については国立成育医療研究センター 野坂俊介先生に解説をいただきました。
ご多忙ななか,素晴らしい内容をご執筆くださいました各先生方には,この場を借りて深くお礼申しあげます。
各先生方からいただいた原稿を目にして真っ先に連想したのが,きれいな写真が沢山掲載された「旅行のガイドブック」です。ガイドブックはすでに決めた旅行先の情報を調べるのにも役に立ちますが,時間のあるときに手に取って目を通すのも楽しいものです。そのように活用していただき,いつも,いつまでも手元に置いていただけることを願って,今回のテーマを「腸閉塞・イレウスの画像診断ガイドブック」とさせていただきました。
初学者の方にとっては,少々とっつきにくい部分もあるかもしれません。しかし,経験を積んで改めて読み直すと,その都度期待に応えてくれる1冊だと思います。腸管マニアの方にはきっと最初から最後まで楽しんでいただけると確信しております。
それでは,奥の深い腸閉塞,イレウスの世界をご堪能ください。
谷掛雅人
特集2:序説
本特集では,IVRに関連した裁判例および画像診断の読影結果が正しくなかった裁判例について取り上げ,基本的に,治療医と法律家の双方の視点で解説した。
個々の症例と同様,裁判にも,まったく同じものは1つとしてない。そのため,事実関係の相違点およびそれについての証拠関係によっては,価値判断が変わってくることもある。今なお,裁判所の判断枠組みは踏襲されており,少し古い判例もあるが,裁判所の判断の考え方を理解するのに重要と思われるものを選んでいる。読者の方々には,不幸にして裁判に巻き込まれた場合に,裁判官がどのように判断するのか,医療者との着眼点の違いを意識して,お読みいただけると幸いである。
通常,医療訴訟での主要な争点は,治療上の過失の有無および説明義務が果たされていたかである。今回の全事例に共通していることは,問題となった治療行為により,最終的に患者が死亡している。このように,結果が重大であるほうが,紛争化しやすいといえる。
治療上の過失は,大雑把にいうと,やってはいけないことをやってしまったという積極ミスと,やるべきことをやらなかったという消極ミスの2つに分けられる。今回は積極ミスが争点になっている。
1例目は,肝細胞癌のTAIおよびTAEにおいて,手技上の過失(積極ミス)が認められたが,2例目は,脳動脈瘤のコイル塞栓術において,手技上の過失は否定された。他方,3例目は,経皮的胆道内瘻化のトラブルが引き起こした胆汁性腹膜炎において,手技上の過失(積極ミス)は認められていないが,合併症が適切なタイミングで治療されなかったという,適時にやるべきことをやらなかった過失が認定された。
積極ミスは,結果が悪かったから,すべてに認められるわけではないことが,これらの対比からも理解いただけると思われる。結果が悪かった場合,多くのケースにおいて後智恵で結果を避ける方法やよりよい治療は思いつくであろう。しかし,回避する方法があったというだけで,法的過失が問われることにはならない。その別の方法が義務とまでいえるか,すなわち,治療法の見解が分かれるようなものではなく,ほとんどの医師が別の方法を選択したであろうというレベルまで達した場合には,通常,過失を問われてしまう。
しかし,そのレベルに達しない場合に過失を問われないということではなく,立証によって裁判官に与える心証によって判断に開きが出る。特に,医療者にとって,実際に行ったということと,裁判で証明できるかという点が一致するものではないことにも注意が必要である。詳細は,1例目の解説をご覧いただくとよい。
4例目は,2例目と同一事件の最高裁判決で,医療行為そのものではなく,未破裂動脈瘤の予防的治療における説明義務のみが争われ,違反を認めた事案である。経験豊富な病院内弁護士によって,実務上の経験を踏まえて解説されている。手技上の過失が否定されたとしても,結果が悪かったからこそ,説明義務違反の問題が最後まで残りやすいことも留意すべき点である。
最終稿では,「画像検査結果が適正に反映されなかったことに関連する複数の裁判例」を類型化し,紹介している。
越後純子
目次
特集 1 腸閉塞・イレウスの画像診断ガイドブック
企画・編集:谷掛雅人
序説 谷掛雅人
腸閉塞の開腹所見と治療 山田岳史ほか
小腸閉塞,外ヘルニアの画像診断 井本勝治ほか
小腸イレウス 豊口裕樹
絞扼性小腸閉塞の画像診断 谷掛雅人
大腸閉塞,イレウス 又吉 隆
内ヘルニア 竹山信之ほか
術後のイレウス,腸閉塞 松本俊郎ほか
小児のイレウス,腸閉塞 野坂俊介
特集 2 判例からみる医療訴訟
企画・編集:越後純子 対馬義人
序説 越後純子
肝TAE後,塞栓物質の胃血管への流入 (東京地方裁判所 平成7年2月27日) 徳江浩之ほか
未破裂脳動脈瘤治療に対するコイル塞栓術において 脳梗塞により死亡した1例(東京高裁 平成17年5月25日) 松丸祐司
PTCD後,ドレナージ不良による腹膜炎 (大阪地裁 平成14年9月26日) 松枝 清ほか
未破裂脳動脈瘤治療におけるIC(説明義務) (最高裁および東京高裁差し戻し審) 北野文将
画像検査結果が適正に反映されなかったことに関連する裁判例 越後純子
便利機能
- 対応
- 一部対応
- 未対応
-
全文・
串刺検索 -
目次・
索引リンク - PCブラウザ閲覧
- メモ・付箋
-
PubMed
リンク - 動画再生
- 音声再生
- 今日の治療薬リンク
- イヤーノートリンク
-
南山堂医学
大辞典
リンク
- 対応
- 一部対応
- 未対応
対応機種
iOS 10.0 以降
外部メモリ:36.6MB以上(インストール時:76.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:146.3MB以上
AndroidOS 5.0 以降
外部メモリ:36.6MB以上(インストール時:76.2MB以上)
ダウンロード時に必要なメモリ:146.3MB以上
- コンテンツのインストールにあたり、無線LANへの接続環境が必要です(3G回線によるインストールも可能ですが、データ量の多い通信のため、通信料が高額となりますので、無線LANを推奨しております)。
- コンテンツの使用にあたり、m3.com電子書籍アプリが必要です。 導入方法の詳細はこちら
- Appleロゴは、Apple Inc.の商標です。
- Androidロゴは Google LLC の商標です。
書籍情報
- ISBN:9784008004212
- ページ数:133頁
- 書籍発行日:2022年11月
- 電子版発売日:2022年11月18日
- 判:B5判
- 種別:eBook版 → 詳細はこちら
- 同時利用可能端末数:3
お客様の声
まだ投稿されていません
特記事項
※ご入金確認後、メールにてご案内するダウンロード方法によりダウンロードしていただくとご使用いただけます。
※コンテンツの使用にあたり、m3.com 電子書籍が必要です。
※eBook版は、書籍の体裁そのままで表示しますので、ディスプレイサイズが7インチ以上の端末でのご使用を推奨します。